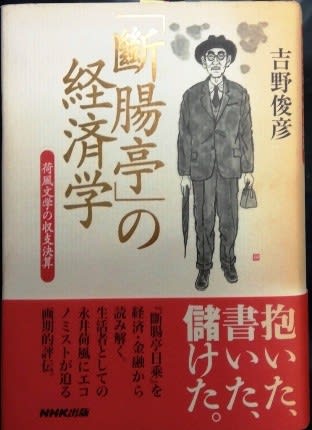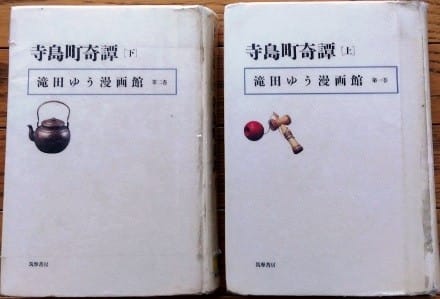吉野俊彦「『断腸亭』の経済学ーー荷風文学の収支決算」(NHK出版、1999年)を読んだ。
図書館で借りてきて読み始めたのだが、内容が面白かったので古本屋で探して買ってしまった。送料込みで609円だった。定年退職後は本は増やさない方針なのだが、この本は手元に置いておきたいという思いを抑えられなかった。
著者は日銀所属のエコノミストだが、鴎外研究などをものした著述家でもあった。しかも著者は、晩年に荷風が暮らした市川の生まれ育ちで、昭和20年代に自宅近くの八幡駅前で何度か荷風を見かけたことがあったという。さらに荷風の疎開先である岡山で勤務した経験から、同地での疎開生活の記述にも地理勘がある。
そして、「断腸亭日乗」に見られる印税、預貯金、株式・不動産売買などの収支、日用品の価格、交通費から買春、身請けなど女性に要した出費などの詳細な記述の中に荷風の経済観念の鋭さを読み取り、昭和経済の変動をうかがう昭和経済史の第一級の資料として「断腸亭」を読み解いたのが本書である。
大正・昭和初期、準戦時期、戦時期、戦後期の時系列で書かれているが、各時代の冒頭にその時代の経済情勢の簡潔な記述があり、高校日本史の復習にもなった(131頁金融恐慌、202頁井上デフレなど)。戦後の金融緊急措置例の経過では、戦前の預金が戦後の預金封鎖で紙切れ同然になってしまったといっていた亡父や、終戦後に大学の1か月分の非常勤手当で吉祥寺駅北口から10分、東京女子大近くの売地が買えたのに(買わなかった)という亡母の嘆きを思い出した(386頁)。
表紙の帯に書かれた「抱いた、書いた、儲けた。」という惹句が、荷風の女性関係、文筆活動、経済生活というまさに本書の内容を要約している。
<抱いた>について。
荷風の女性関係は、基本的に売買春である。著者は、その頻度や費用を「日乗」から丹念に広いあげる。昭和4年5月4日以降の「日乗」の日付欄には「●」や「○」の印がついていることがある(190頁)。岩波版第2期全集の後記にもこの印について詳細な言及があるが、その意味については説明がないという。著者は、これは荷風がその日に性交渉があったことを示す印だろうと推測する。
荷風が関係を持った女性の氏名と関係をもった期間は荷風自身が「日乗」に列挙しているが(本書520頁以下に一覧あり)、著者は、「日乗」から「○」「●」印をすべて洗い出して、昭和4年(荷風50歳)41回(/年間)から、昭和19年(65歳)28回までを一覧表にしている(192頁)。最後にこの印がついたのは昭和32年3月18日(荷風78歳)の日記の「○」印だった(449頁)。
そして荷風が一時期妾とした山路さん子や関根うたを身請けした際の代金がともに1000円だったことも日記に記されている(194頁)。荷風が通った玉の井(戦後は小岩や海神にも出没したらしい)などの私娼の料金は、戦時中は一晩30円だったのが(214頁)、終戦後はショート100円、泊まり400円に上昇したとある(373頁)。いずれにしても、印税だけで数億円を稼ぐ年もあった荷風にとっては痛くも痒くもない出費だっただろう。
<書いた>について。
荷風が書いたことについては、これまでの荷風関連書でも十分に論じられているが、著者独自の考察として、荷風の出版物の定価や部数が詳しく記録されている点がある(後の<儲けた>と重複する)。例えば大正末期から昭和初期にかけての改造社版および春陽堂版円本の対比(141、152頁)、岩波文庫に収録された荷風作品の増刷部数の一覧表などがついている(270頁)。
「日乗」に見られる荷風の斜に構えた世相批判の指摘も随所にある。関東大震災を、それ以前の(第一次大戦)戦後の浮かれた世相に対する「天罰」であると書き(108頁)、自分の春陽堂版全集が売れるのは「世を挙げて浮華淫卑に走りし証拠」などと書いている(116頁)。戦時中に軍部が戦地の兵士の慰問用として「腕くらべ」の増刷を要求してきたことを荷風は「何等の滑稽ぞ」と記している(296頁)。
<儲けた>について。
経済面では荷風は相当裕福な一生を送ったが、荷風を「ランティエ」とする見方に著者は異論を述べる。ランティエとは年金や預貯金の利息などで仕事もせずに生活できるフランスの富裕層を意味するが、荷風は確かに親から相続した不動産や預貯金、株式などを豊富に持っていた。しかし、荷風の経済基盤は相続した株や不動産の売却益などの不労所得よりも、荷風自身の文筆活動による印税収入によるほうがはるかに大きかったと著者は見る。当初は借地だった「偏奇館」敷地の買取りの経緯などでも、銀行を相手にした荷風の経済感覚の鋭さが指摘される(343頁)。
とくに昭和初期に起った円本ブームの頃(昭和2年)の日記には、荷風の所得税額は「2万6千円以上」と書いてある(157頁)。この「所得」とは実際の収入から経費を差し引いた金額であり、当時の税務実務では文筆家は収入の50%を経費として控除することが認められていたから、実際の収入は倍の5万円以上あったはずで、その額は現在の貨幣価値に換算すると数億円に上ったという。荷風は相続した余丁町の不動産売却や株への投資などでも儲けているが、その経済基盤はけっして「ランティエ」のようなものではなかった(401頁)。
ただし、晩年の荷風は文化勲章による年金と、芸術院会員としての俸給が支給されることを楽しみにしており、昭和27年12月16日の文化勲章年金証書受領の記事から、亡くなる1か月前の昭和34年4月2日の「年金45万円受取」まで毎年年金受領の記事があるから(477頁~)、晩年の荷風は「ランティエ」といっても差し支えないだろう。
そして、本書最終章「荷風とケインズ」では、著者は、恩師中山伊知郎のエッセイを引用する。中山は、経済学者にとどまらず企業家、投資家でもあり巨万の財産を有したケインズと、(当時の作家の中では富裕層とみられた)荷風との共通点を指摘する。それは二人の蓄財の目的である。
中山によれば、2人の蓄財に共通していた目的は、「いやな仕事をしないための自由」「一切の世間的な付合いを絶って勝手に生活できる自由」の確保であった。そのためには金なしで生きる生活もありうるが、2人はこの自由を得るために金銭的に備えた点で共通するというのである(517頁)。
著者も中山の説に共感し、荷風が(残高2000万円以上ある)預金通帳を常に持ち歩いていて紛失したり(新聞記事になった)、亡くなった際の枕元にも通帳入りのバッグが置いてあったことを揶揄する意見があったが、これらのエピソードは 荷風の精神的自由を象徴するものであったとして本書を結んでいる。
最後に今回も、miscellaneous な話題をいくつか。
まず驚いたのは、戦前の荷風が長年住んだ麻布の「偏奇館」に「ペンキ館」とルビが振ってあったことである(15頁)。どこかに荷風自身が、ペンキ塗りの建物なので「ペンキ館」と呼んだことが紹介してあった。「へんき館」だとばかり思っていた。
つぎに、売春防止法以前の売買春に関して、誰も解説してくれないので分からなかったことを知ることができた。
売買春が行われる場所である「待合」「料亭」そして「芸者家」(芸者置屋?)を「三業」といい(「自宅」「別宅」の場合もある)、待合は場所を提供するが賄い施設はもたず、食事はすし屋などから出前を取るが、料亭は自前の賄い施設をもっているという違いがあること、芸者を呼ぶ場合には芸者家ではなく検番を経由しなければならないことが説明してあった(85頁)。
それらの場所にやってくる女性のうち、芸を売るのが芸妓(体を売る場合もある)、体を売るのが娼妓だが、その他にカフェ女給、素人もいた(81頁)。娼妓は、公認されているが性病検査などの義務がある公娼と、非公認の私娼に分かれる。実際には私娼も黙認されていたが、時おり抜打ちの取締り(臨検)があった。「ひかげの花」はそのような私娼がモデルである(229頁)。
著者の説明で、荷風「濹東綺譚」や「日乗」の背景はかなり理解できた。
荷風の慧眼ぶりを示す例として、中央公論社版全集刊行の経緯がある。岩波と中公がともに全集刊行の申し込みをして競い合ったが、結局中公での刊行が昭和15年11月に決まり、中公は5万円の手付けを支払っている。驚くのはその契約書で、中公側は刊行開始時期を「昭和20年12月1日以降」と明記しているのである(274頁~)。まるで4年後の昭和20年8月の終戦を見越したような日程である。
しかも、実際に終戦になった翌日の8月16日に、荷風は中央公論社長の嶋中雄作宛てに手紙を出しており(367頁)、さっそく嶋中は熱海に疎開中の荷風を訪ねている。おそらく全集についての話合いであろう。その後、中公の内紛(林達夫氏が退社した!)、社長の急死などもあったが(428頁)、中公版全集は完結した。
戦後の荷風は寡作で、見るべき作品もないが、著者はその理由として、心身(色欲)の衰えのほか、「荷風全集」の刊行に集中したことを指摘している。「日乗」の記述も、昭和24年のドッジラインによるインフレの終息以降は経済生活の記述は姿を消し、経済史的資料としての価値は消滅したとする(472頁)。
戦後になって市川に荷風を訪ねてきたかつての愛妾関根うたへの荷風の対応はきわめて冷淡である(500頁)。これも荷風の「いやな世間と付き合わない自由」の行使なのだろうか。映画「放浪記」のラストに、戦後に売れっ子作家になった林芙美子のもとに金を無心に来る親戚や慈善団体を林が追い返す場面があったが、あのような事情でもあったのだろうか。
2024年9月27日 記