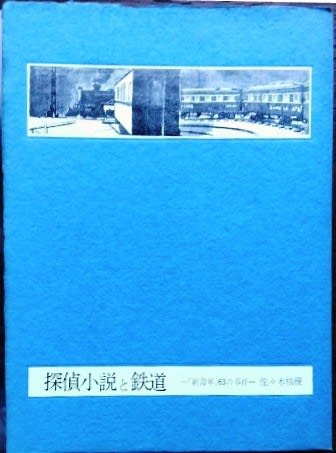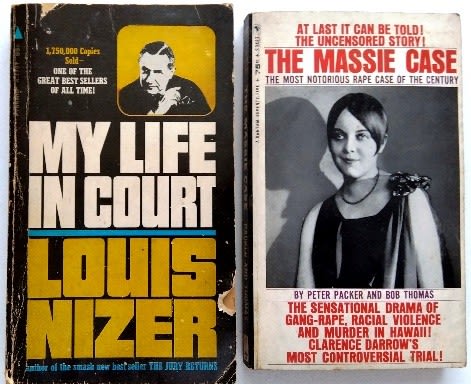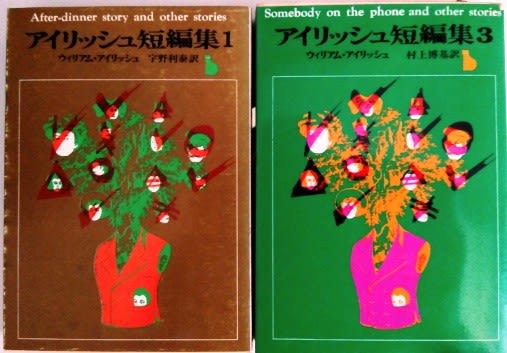川本三郎「荷風語録」(岩波現代文庫、2000年)を読んだ。
「小説をつくる時、わたくしの最も興を催すのは、作中人物の生活及び事件が開展する場所の選択と、その描写である」と荷風自身が「濹東綺譚」(本書173頁に引用あり)で書いているように、荷風作品の情景描写には荷風が下町散歩の観察から得た情報が細部にまで再現されている。
本書は、川本が「荷風と東京」という視点から、荷風作品に見られる往時の東京風景を作品の発表年代順に再録(抄録もある)したものである(ⅳ頁)。第1部「明治・大正の作品」、第2部「戦前の作品」、第3部「戦後の作品」、第4部「『断腸亭日乗』の世界」という構成で、各部の冒頭に川本の解題がつく。
「語録」という書名から、本書は「老い」とか「家族」とか「娼婦」とかいったテーマ「語」や場所ごとに、荷風の考えや見方がわかる文章を集めた本かと思ったが、しかしこれは嬉しい誤算で、実際には「荷風短編傑作選」とでもいった内容の本であった。
ぼくは、川本が「老いの荷風」や「荷風好日」の中で評価していた戦後の荷風の小品ーー「勲章」「にぎり飯」「吾妻橋」などを読んでみたいと思っていたので、これらを本書第3部で読むことができたのが最大の収穫だった。第3部に収められた「草紅葉」「老人」も良かったが、できれば「羊羹」も読みたかった。
「勲章」の主人公は、浅草オペラ館の楽屋に出前を運んでくる爺さんである。日露戦争に召集された自慢をしたところ、ある日踊り子らにおだてられ、楽屋に置いてあった舞台衣装の軍服を着て、日露戦争の際の勲八等の勲章をつけた写真を荷風に撮ってもらい、いつになく嬉しそうな顔を見せる。しかし、その写真の現像ができる前に爺さんは人知れず死んでしまう(「勲章」昭和17年)。同じくオペラ館で、いつも楽屋手前の通路で風呂焚きをしていた爺さんは、戦後の薪不足で解雇され、その後の消息は分からない。誰にも知られずに死んでしまったのだろう(「草紅葉」昭和21年)。
オペラ館の踊り子で、荷風原作のオペラ「葛飾情話」にも出ていた栄子は、三社祭の当日、いつも世話になっているからと言って、おっかさんが作った強飯を楽屋の荷風に差し入れる。その後オペラ館を去った栄子は東京大空襲でどうなったのか。荷風は「栄子が父母と共にあの世へ行かず、娑婆に居残っている事を心から祈っている」と書く(同、226頁)。
この2作品と「吾妻橋」が荷風の戦後作品ベストスリーだとぼくは思った。
その他、空襲で生き別れになった(内縁の)夫が死んだものと思って別の男と結婚した女が、生きていた夫と偶然に再会してしまう話は(「にぎり飯」昭和22年)、戦後それほど珍しくなかった「失踪宣告」ものだが(ソフィア・ローレン「ひまわり」など)、内縁だったので法的な問題は小さいし、話の結末もややあっけない。
「老人」(昭和25年)の登場人物は、亡くなった妻の葬儀を終えた夫(元は病院の会計係だった)と、離れて遠くに住む中年になった一人娘と従妹の3人だけ。葬儀を終えた3人は、残された夫の今後について語り合う。夫は、なかなか上京できないだろうからといって妻の着物を形見分けに持って帰ることをすすめ、娘たちはそそくさと品定めをする。「東京物語」の長女杉村春子を思い出すが、「老人」では父親のほうから形見分けを言い出している。
「吾妻橋」(昭和28年)の主人公道子は、浅草の街娼である。貧しい大工だった父親は空襲で亡くなり兄も戦死したため、周旋する者があって街娼となる。小津安二郎「風の中の雌鶏」の娼婦役、文谷千代子が思い浮かんだ。ある日道子は思い立って亡母の墓所を探しに松戸の寺を訪ねる。遺骨のまま放置されていた亡母のために、道子は7000円を払って墓石を建立する。1日で1500円稼げるから7000円くらい何とかなる。道子のモデルは「断腸亭日乗」に出てくる、あの浅草駅ホームで荷風が300円を渡した娼婦だという。やっぱり荷風は300円(後日さらに300円)を渡して小説のネタを仕入れていたのだ・・・。
どの作品も、山の手の人間が勝手に抱く「下町情緒」に訴える雰囲気はあるが、浅草や立石をほとんど知らないぼくには、これらの作品の場所が浅草、立石でなければならない必然性は分からなかった。浅草、立石を知らなくても、登場する老人や娼婦たちの好ましい性格は十分に伝わってきた。道子たちは「駅馬車」や「ウィンチェスター銃 73」の娼婦(後者はシェリー・ウィンタース)を思わせる。
第3部に収録された諸作品は、いわゆる「人情もの」として読めた。石川淳は戦後の荷風作品を酷評したというが、石川に嫌われたとしても、ぼくは人情ものとして好ければそれでいいと思う。
第1部では、荷風の「散歩」の原点というべき「日和下駄」(大正4年)がいい。
身長180センチを超える荷風は、いつも日和下駄を履き蝙蝠傘をもって散歩に出た(76頁~)。雨が降っても、泥濘を歩くにも便利だからという。日和下駄というのがどんな下駄なのかぼくは分からないが、革靴の中に雨水が漏れるより、いっそ裸足に下駄履きのほうがマシであるという気持ちは分かる。
13、4歳頃の荷風は、麹町永田町の自宅(親の官舎)から、半蔵門、吹上御苑、竹橋、平川口、一ツ橋に出て、神田錦町の私立英学校まで歩いて通ったという。これだけでも結構な距離だが、登下校の際に寄り道をして通学路の近辺を歩いたのが荷風の散歩の始まりだという。
その後の東京市中の散歩は、生まれてから今日に至るまでの過去の生涯に対する追憶の道を辿り、日々名所古跡を破壊してゆく時勢の変遷に無常悲哀の寂しい詩趣を感じるためであったという(78頁)。荷風は「ノスタルジー作家」である。
川本の第1部解説によれば、荷風は、四ツ谷見附から東京の市電(街鉄)に乗ると「女学生と軍人が多い」と書いている(5、6頁)。荷風は女学生と軍人を毛虫の如く嫌っており、それが築地への引越しの一因だったと川本は推測する。安岡章太郎も、青山は軍人が作った町だったと書いているという(5、6頁)。戦前の六本木には陸軍第一連隊があり、青山には陸軍大学、市ヶ谷には陸軍省があった。
川本は「現在の感覚では考えられないが、山の手は戦前までは軍人の町だった」と書く(6頁)。ぼくは浅草や玉の井のことは分からないが、祖父が(荷風が毛虫の如く嫌う)軍人で、余丁町の官舎から青山、六本木に通っていたと聞いていたので、青山や六本木が軍人の町だったことはよく分かる。須賀町にあった出版社のサラリーマン時代、信濃町から青山への外苑東通りを歩くと、その昔祖父もこの通りを通ったのだと時空を超えた感慨を覚えた。われわれのDNAには先祖の記憶が刻印されていると聞いたが、本当だろうか(デジャブ)。
荷風の住んだ余丁町の近くには市ヶ谷監獄があった。そこで大逆事件の幸徳秋水らが処刑されたことは「断腸亭日乗」に書いてあったが、荷風は「花火」(大正8年)で、この事件ほど「嫌な心持のした事はなかった」と書き、これを契機にいわゆる「戯作者宣言」をしたという(14、5頁)。余丁町から三輪田に通っていた伯母は、監獄前の通りで足枷をはめられた囚人服(着物)姿の囚人が帚で道を掃いていて、その脇を通るのが怖かったという思い出を話していた。
第2部に収録「つゆのあとさき」(昭和6年、抄録)の主人公は、その頃から流行し始めたというカフェの女給である。芸妓(吉原)、公娼(どこ?)、私娼(玉の井、浅草)の区別も十分に実感できないうちに、新たにカフェ女給(銀座?)という職種が登場してきた。
民法の講義で「カフェ丸玉女給事件」という判例を読んだ(大審院判決昭和10年4月25日)。女給が馴染客から400円をもらう贈与契約を結んだが、客が履行しないとして訴えた事件。大審院は、この債務は客が任意に履行すれば女給は受領してよいが、任意に履行しない場合には裁判所に訴えても裁判所は履行を命じないとして(「自然債務」という)、請求を退けた。
※久しぶりに判決を見たら、何と差戻審で女給側が逆転勝訴していた。女給の窮状を認定するその理由づけが荷風的である。
「寺じまの記」(昭和11年)。題名の「寺じま」とは何だろうと思っていたら、これは玉の井の旧町名「寺島町」に由来するという(103頁)。この話は、玉の井の娼家の構造とそこに棲む娼婦の顔貌までもが微細に描写されている。当時の読者にとって、風俗店ガイドブックの用も果たしたのではないか。
第4部「断腸亭・・・」はこれまでに書いたので省略。
2024年7月12日 記