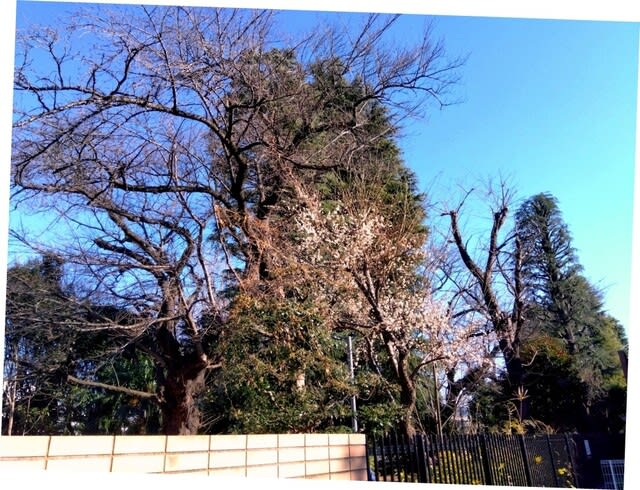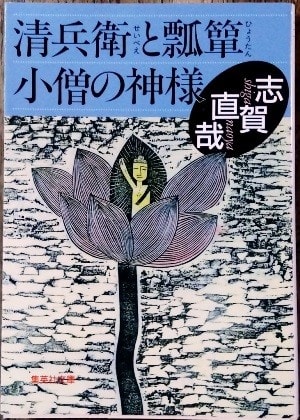村松友視+管洋志(写真)「アジア幻想 ーー モームを旅する」(講談社、1989年)を読んだ。1989年と言えば平成元年ではないか!
2007年3月8日の日付の「マーケットプレイスで購入」というレシートが挟んであったが、出品者や値段はない。古本で買ったまま放ってあったもの。
昨日2月6日は3か月に一度の眼科の定期検査。診察を待つあいだの時間つぶしに持参した。眼科の検査の前に本を読むのは検査数値に悪影響を及ぼすのではないかと心配だが、毎回診察までに2時間近く待たされるので、本でも読んでいなければ間が持たない。
昨日は9時半過ぎに受付をしたが、すでに50人以上の順番待ちがいた。11時半すぎになってようやく事前の視力検査の順番が回ってきた。視力検査が済んだ段階で順番は5人待ちくらいになったのだが、ぼくの前の順番の高齢の女性患者が1人で25分もかかったため、それからさらに1時間近く待たされた。
そんな次第で、村松「アジア幻想」は100ページ近く読めたが、視力、眼圧ともに前回より数値が悪くなっていた。幸い眼底は悪化していなかった。
ようやく診察を終え精算も済ませて屋外へ出ると12時半。眼底検査のために瞳孔を拡大させる目薬を差されたため、冬の日差しがまぶしく、青空も真夏のように青く輝いて見えた(下の写真。ぼくの目にはこの写真より10倍まぶしく見えていた)。横断歩道を渡るときも白線がギラギラと輝いて下を向いて歩けない。
もとの勤務先に行って、後輩とランチをして帰る。下の写真は「能楽書林」のファサード、ぼくが好きな神保町の風景の一つである。


さて「アジア幻想」だが、「モームを旅する」という副題がついていて、サマセット・モームのアジア旅行を村松が追体験した旅行記に、同行した写真家菅洋志の写真が添えられている。
モームの南洋ものに登場するシンガポール、クアラルンプール、バンコクを村松が旅しながらモームを追体験する随筆だが、モームは狂言回しというか脇役で、村松が主人公の旅行記と考えたほうがよい内容。「モームを旅する」という副題にはあまり期待しないほうがよい。
全体は4章に分かれていて、「幻想ーー?マークの誘惑」「湿潤ーーシンガポール ラッフルズ・ホテル」「芳烈ーークアラルンプール アペリティフ・シャワー」「熱鬱ーーバンコク 極東メリー・ゴー・ラウンド」という章題がついている。
「?マーク」というのはモームのあだ名だそうで、謎めいたモームの表情や性格を意味するらしい。つづく3章は「PENTHOUSE」誌1985年5~7月号に連載されたもの。そういえばそんな雑誌があったような気もする。掲載された雑誌の性格がそうだったのか、今読んでもかなり気障な印象を受ける。
モームは一時期(40歳の頃だった)イギリス諜報機関のスパイを務めたが(「アシェンデン」)、それは1917年、ロシアが革命の真っただ中のことだった。ケレンスキー政権を支えるという重大な任務を与えられていたのだった(200頁)。そうだったのか。「アシェンデン」を読んだときはそんな重大な任務を帯びていたとは気づかなかった。モームはロシア嫌いだという印象を持っているが、もう一度「クリスマスの休暇」を読み直してみよう。
さて、村松だが、かつてモームも泊ったラッフルズ・ホテル、マジェスティック・ホテル、オリエンタル・ホテルに泊ってモームの幻影を探るのだが、雰囲気が残っていたのはラッフルズ・ホテルだけで、マジェスティック・ホテルは面影を残していたのはコロニアル風の白亜の外観だけで、内部は現代的な美術館になってしまっている。ただレトロなエレベーターと、隣りの建物から聞こえてくる古いタイプライターの音に、わずかに往時を偲ぶことができるだけであった。王国として一貫して英国の植民地となることを拒否したタイのバンコクは、「コロニアル風」を装うことも拒否しつづけたため、モームもバンコクには強い違和感を表明していた。
モームは南洋ものでも決して現地人を主人公とすることはなく、植民地の支配者側の人間としてこの地にやってきたイギリス人(西洋人)を主人公とし、コロニアル風であることを好んだという。モームの南洋ものには現地人を主人公とする作品はなかっただろうか。人間を「環境の生き物」と考えるモームなら、南洋ものの主人公は現地人の方がふさわしいと思うが、イギリス人が南洋に駐留するうちに「環境」によって変わっていくというのも「環境の生き物」らしいか。
序章の「?マーク」の謎も、結局は解けないままに村松の旅は終わる。
もっとたくさんのモーム作品が登場するかと思ったが、南洋ものでは「雨」がやや詳細に語られる以外は残念ながらほとんど登場しない。モームの南洋ものには上の3都市以外にももっとたくさんの作品があるが、村松はモームの南洋ものをそんなには読んでいない感じがした。
南洋ものではなく、「要約すると」「作家の手帳」などの回想録や、「人間の絆」「お菓子と麦酒」のような自伝的な作品のほうがよく引用される。「大衆作家」として評価されながら「純文学作家」としてはイギリスでは評価されなかったというモームの作家としての地位に何度か言及があった。「20代の頃は残忍だといわれ、30代の頃は軽薄だといわれ、40代の頃はシニカルだといわれ、50代の頃は腕達者だといわれ、60代の今は浅薄だといわれる」というモーム自身の有名な言葉も2、3度登場した。これに村松は、20代で珠玉の短編を、30代で長編を、40代で評伝を、50代で自伝を書き、60代で芸術院会員になるという日本の文壇の噂を対置している(61頁)。
高齢になってもハイティーンからのファンレターが届いたというエピソードが2、3度出てきたが、本当だろうか。確かにぼくたちが大学受験生だった1968、9年ころはモームは受験英語界で頻出作家だったから、モームを読んだ受験生は多かったとは思うが。
2025年2月6日 記
追記 どういう文脈だったか忘れたが(※モームも一九も晩年まで世間の評価を得られなかったという文脈だった)、本書に十辺舎一九のことが出てきた。一九はいまテレビで話題らしい(ぼくは見ていない)蔦屋重三郎の食客だったという(46頁)。
蛇足 ここ数日ラジオ放送100年を記念してNHKラジオ深夜便がニッポン放送のオールナイト・ニッポンとコラボした番組を放送しているのだが、面白くないというか喧しい。オールナイト側が鈴木杏樹や名取裕子のためか、NHKの男性アンカーのテンションが高すぎる。ラジオ深夜便とオールナイト・ニッポンとはあまりにも性格が違いすぎる。深夜放送だからというだけで「コラボ」できるものではないだろう。おかげでラジオを切ってさっさと寝ることができるのはありがたいが、熟睡して昨夜は「絶望名言」の時間も寝過ごしてしまった。
追記2 昨日(8日)朝のNHKラジオ番組に前回の芥川賞受賞者が出ていた。アナウンサーから作品における「文学性(芸術性だったかも)と娯楽性」の関係について聞かれて、シェークスピアのように発表当時は娯楽作品として多くの人に読まれながら、後世になって文学研究の対象となるような作品が理想と語っていた(ように思う)。
村松も本書の中でモームのイギリス文学界における評価の低さについて何度か言及していて、村松自身が大衆小説(読物)と文学作品との区別にこだわりがあることが感じられた。後で調べると、昨日朝のゲストは「ゲーテはすべてを言った」という小説の鈴木結生という人だった。ラジオで聞いた限りでは「ダヴィンチ・コード」のような作品内容のようだった。伏線というかサイドストーリーとして学者による資料の捏造事件が出てくるらしい。ゲーテには興味がないけれど、捏造事件(あの事件に着想を得たのだろう)のほうには興味が湧く。(2025年2月9日 追記)