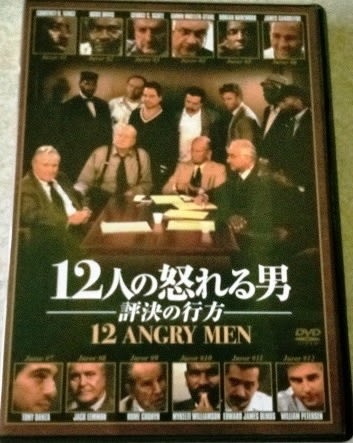
『リヴァイアサン』第2部でもう1つ、追加しておくことがあった。
イギリスの陪審制についてのホッブズの記述についてである。
第23章「主権者に仕えて国政を代行する者」と題する章の中に、「陪審制」にかかわると思われる文章がある。角田訳では「あらゆる民事裁判において各臣民は・・・、係争中の問題が起こった土地の人間を裁判官とした。そして、それに対しては異議の申し立てが許されており、それは、十二人の裁判官が異議なく承認されるまで許された。判決を下すのは、この十二人であった。」自分自身の裁判官を戴くのであるから、その判決が最終的なものとされるといった文章が続く(138頁)。
読みやすい角田訳にしては、「それに対しては」、「それは」といった指示代名詞が何を指しているのか明確でない。
この部分はイングランドの陪審裁判のことを言っているのだと思うが、ホッブズはなぜか、“jury”という語はいっさい使わない。
陪審裁判はノルマン制服の後にイングランドに入ってきた制度であり、前にも『少年たちの迷宮』か何かで書いたことだが、その制度趣旨は、「クラッパムの乗合馬車に偶然乗り合わせた12人の地域住民の意見が一致した場合には、彼らの判断、結論は当該地域のコミュニティ・スタンダードとして認められる」というものだと言われる。
陪審員は12名で構成されるが、陪審員候補者の中には被告側(あるいは訴追側)に対して偏見を持っている者が含まれうるため、被告側は(訴追側も)一定数の陪審員候補者を理由なしに忌避することができる。原文の“exception”(Oxford World Classics, p.162)は「異議」とも訳すことができるが、異議は(裁判官によって)却下されることがあるのに対して、陪審員に対する「忌避」申立ては濫用に及ばないかぎり原則として無条件で認められる。水田訳『リヴァイアサン(2)』(岩波文庫、133頁)では「忌避」と訳している。
もう1つ、この部分に出てくる“judges”を角田訳、水田訳ともに「裁判官」と訳し、角田訳では“twelve men”も「十二人の裁判官」と訳している。“(were)judged”を、角田訳は「判決を下す」と訳し、水田訳は「裁判される」と訳している。
しかし陪審員(審理陪審)の任務は事実認定すなわち事実関係の有無に限られ、有罪無罪の「評決」は行うが、「判決」を下すのは(陪審員ではなく)裁判官である。『哲学者と法学徒との対話』をみても、ホッブズは相当な法知識をもっていたことが分かるから、ホッブズは、あえて「陪審(員)」(“jury”“juror”)という言葉を使わなかったと思う。
したがって、この部分の“judge”を「陪審(員)」とまで訳すのは意訳にすぎるだろうが、「裁判官」と言い切ってしまうことにも疑問がある。“judges”は「判断者」、“(were)judged”は「判断される」くらいにとどめておいたほうがよいのではないか。もし『リヴァイアサン』か他の著書のどこかに、ホッブズが「陪審員」を「裁判官」ないし「裁判官の代行者」と考えていたことを示す文章があるのなら、以上はぼくの不勉強による誤りである。
全臣民の同意に基づく主権者権力(sovereign power)の行使である司法権の中の、その一部である事実認定を、地域で選ばれた12人の素人に委ねる陪審制度はホッブズの政治理論にとってどのような位置にあるのだろうか。説明しにくいのではないか。トクヴィルはアメリカの陪審制度を民主主義の中核と理解したが、民主政に好意的ではなく、一般人民の愚昧を嘲笑するホッブズが陪審制度に好意的であったとは思えない。
現役時代だったら、教員控室で出会った同僚の政治思想史研究者や英米法の専門家に気軽に質問できるのだが、今では独り言をいうしかない・・・。
2021年7月28日 記
※ 適当なっ写真がなかったので、アメリカ映画だが『12人の怒れる男たち』(ヘンリー・フォンダのではないリメイク版)のカバーを。









