A群から分蜂したニホンミツバチは二か所に固まったのですが、
三時間ほどかかって菊桃の蜂球のほうに移動してきました。

蜜蜂を巣箱に入れるので、蜂球にスプレーをかけます。

こうすると濡れるのが嫌なので、蜂球がきれいに固まります。


ポリを上につけて細工した巣箱を下に置いて、

蜂球を箱の中に落とします

少し逃げる蜂はいますが、おおむね箱の中に入ったので、

箱にふたをして定位置にセットして終わり。

蜜蜂が逃げないようにふさいだ入り口のタオルもとります。

蜜蜂たちは落ち着いているようです。

幹に残ったミツバチは虫取り網ですくって移動。

ちょうど作業が終わった時に突然の雷。
激しい雨も降ってきました。

蜜蜂が大好きなイブキジャコウソウに群がる蜂さんたち。

開花予定のキンリョウヘン

花が咲いたキンリョウヘンに誘われて
明日は分蜂群が入居するかもしれません。
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
応援クリック してね


最後まで読んでくださってありがとう
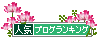
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

三時間ほどかかって菊桃の蜂球のほうに移動してきました。

蜜蜂を巣箱に入れるので、蜂球にスプレーをかけます。

こうすると濡れるのが嫌なので、蜂球がきれいに固まります。


ポリを上につけて細工した巣箱を下に置いて、

蜂球を箱の中に落とします

少し逃げる蜂はいますが、おおむね箱の中に入ったので、

箱にふたをして定位置にセットして終わり。

蜜蜂が逃げないようにふさいだ入り口のタオルもとります。

蜜蜂たちは落ち着いているようです。

幹に残ったミツバチは虫取り網ですくって移動。

ちょうど作業が終わった時に突然の雷。
激しい雨も降ってきました。

蜜蜂が大好きなイブキジャコウソウに群がる蜂さんたち。

開花予定のキンリョウヘン

花が咲いたキンリョウヘンに誘われて
明日は分蜂群が入居するかもしれません。
 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ応援クリック してね



| 社説:コロナと自治体 最前線の責任は大きい 2020年4月23日 朝日新聞 緊急事態宣言が全国に広がったいま、すべての自治体がコロナ対策の最前線に立つ。 改正特措法で知事に権限を与えられた都道府県はもちろん、全市区町村が住民の命と暮らしを守り、地域社会を維持する責任を果たさねばならない。 政府のコロナ対応は、現金給付の方法や一斉休校などで、どたばたが目立つ。地方向けに積んだ1兆円の臨時交付金も、肝心の使い道を制限しようとして批判され、方針を転換した。 こうしたなか、自治体からは地域の事情を踏まえた施策が繰り出されつつある。 北海道はいち早く自主的な緊急事態宣言で外出自粛を呼びかけ、一定の効果をあげた。東京都が設けた感染拡大を防ぐための「協力金」も、個人への補償を否定する政府との発想の違いが評価されている。 市区町村も続々と独自策を打ち出している。新潟市のドライブスルー方式でのPCR検査、大分県別府市などでの非正規職員の期間つき採用計画などが話題だ。このほか、公立学校の給食費や保育料の免除、地場産品の買い上げ、手作りマスクの配布、地域限定の親子食事券といった取り組みも広がる。 ただ、前例のない局面だけに課題も山積みだ。 たとえば、多くの都道府県が行う休業要請に伴う「協力金」は地域ごとに金額に差がある。各地の家賃相場を考慮すれば、一律でなくてもよいが、極端な開きは好ましくない。 格差を縮めるには政府の支援が必須だろう。すでに全国知事会は交付金増額を求めており、それに応じるべきだ。具体的な配分方法にも自治体の意見をとり入れたらどうか。 政府からの「指示待ち」の自治体が多いのも問題だ。財政的な事情があるにせよ、対応が遅れて地域経済が立ち直れなくなれば取り返しがつかない。 かつて、鳥取県西部地震の際に当時の片山善博知事が国の反対を押しきり、住宅再建に最大300万円の支給を決めた例もある。国の施策が住民の要望にそぐわないなら、地域から是正を訴える気概を持つべきだ。 折しも、この4月で地方分権一括法の施行から20年の節目を迎えた。安倍政権のもとで分権改革の影は薄いが、政府と自治体は「主従」ではなく「対等」の関係なのだ。 近年の空き家対策、ヘイトスピーチ規制をはじめ、公害対策や情報公開など自治体が政府に先んじて対処策を示し、それが全国に広がった事例も多い。 コロナ禍に対して、地域がどう立ち向かうのか。住民に身近な自治体ならではの知恵と工夫が求められている。 |
| 社説:スーパー入店 消費者も利用に節度を 2020年4月24日 中日新聞 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京都がスーパーなどでの買い物回数を減らす要請を行った。「三密」状態の回避が狙いだ。やむを得ぬ措置だが消費者側により節度ある利用を求めたい。 小池百合子都知事が発表した要請は買い物を三日に一回程度に抑制することが軸だ。事業者へは買い物かごを減らすほか、高齢者や妊婦、障害者の専用時間を設けることも求めた。政府の専門家会議が店内感染に警鐘を鳴らしており要請は認めざるを得ない。 長引く外出自粛の影響で家族連れで店に入るといったケースが激増している。 それに伴い、店内で「子どもが走り回る」「品薄に過剰なクレームをつける」「マスクを着用しない」「手に取った品物を繰り返し棚に戻す」「指につばをつけお札を数える」などが、従業員にとって懸念のある事例として浮かび上がっている。 感染の危険を増大させるだけでなく、従業員に大きな心理的負担をかける行為だ。消費者は、こうした問題行為を慎むよう強い自覚を持つべきだ。 都の要請が実現されても課題は残る。小さな子どもを持つ一人親の場合、一緒に入店するしかない。一時預かり所を設けるなど行政主導の支援がほしい。 回数抑制で買い占めが加速したり客の流れ次第では行列ができる可能性がある。専用時間の設定も難題だ。要請後、トラブルの恐れは強まるだろう。一方、店側は離職者が増えて人手不足にも苦しんでおり、対応に人員を割けないのが実情だ。 警備会社と連携したり、アルバイト減で困る学生を雇い、仕事を手伝ってもらうなどの工夫が求められる。その際、自治体は一部費用の補助を検討すべきだろう。 小売りの現場で働く人々も高いリスクの中で懸命に仕事を続け、社会に多大な貢献をしている。医療従事者同様に感染から守る必要がある。ただ行政の強い指導の下で規制を実施することには共感できない。 今後、スーパーで大規模な感染が起きた場合、その店舗は長期間、閉鎖を余儀なくされる。それは地域の生活拠点を一時的にせよ失うことでもある。 スーパーなど生活必需品を手に入れる店舗での身勝手な振る舞いはより許されないはずだ。そうした行動の結果が、消費者に跳ね返ってくる恐れがあることを自戒も込めて強調したい。 |
最後まで読んでくださってありがとう

 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね


















