読書が好きなので、3つの図書館から合計20冊の本を借りて読んでいます。
2週間で20冊、月に40冊、年間480冊読んでいることになります。
基本的には、専門書を除いて興味のある本を読んでいますが、ただ、それだと読む分野が偏ってしまうので、意識的に興味のない分野の本も読むことにしています。
知財関係の本も特許に偏りがちなので、意識的に著作権、不正競争防止法、意匠、商標の本も読むようにしています。
論文も、どうしても興味のある、職務発明制度、均等論、先使用権、侵害論、消尽論等に偏ってしまうので、これを避けるためにパテント、知財管理、大学紀要等の論文集に掲載されている論文を全て読むことにしています。
この方法の良いところは、興味がなく知識が少ない知財分野についての知識が増えることと、思わぬ発見をして、それが論文作成の契機になることです。
例えば、ノウハウ保護についての関心が薄かったのですが、ノウハウ保護に関する論文を読んで興味を持ち、ノウハウ保護と特許出願との関係を考察する論文を作成しました。
M&Aにおける知的財産の取り扱いに関する論文も、この方法で作成しました。
さて、次に興味を引くのは何か。
自分でも楽しみですね。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
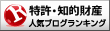
特許・知的財産 ブログランキングへ
2週間で20冊、月に40冊、年間480冊読んでいることになります。
基本的には、専門書を除いて興味のある本を読んでいますが、ただ、それだと読む分野が偏ってしまうので、意識的に興味のない分野の本も読むことにしています。
知財関係の本も特許に偏りがちなので、意識的に著作権、不正競争防止法、意匠、商標の本も読むようにしています。
論文も、どうしても興味のある、職務発明制度、均等論、先使用権、侵害論、消尽論等に偏ってしまうので、これを避けるためにパテント、知財管理、大学紀要等の論文集に掲載されている論文を全て読むことにしています。
この方法の良いところは、興味がなく知識が少ない知財分野についての知識が増えることと、思わぬ発見をして、それが論文作成の契機になることです。
例えば、ノウハウ保護についての関心が薄かったのですが、ノウハウ保護に関する論文を読んで興味を持ち、ノウハウ保護と特許出願との関係を考察する論文を作成しました。
M&Aにおける知的財産の取り扱いに関する論文も、この方法で作成しました。
さて、次に興味を引くのは何か。
自分でも楽しみですね。
ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。
特許・知的財産 ブログランキングへ














