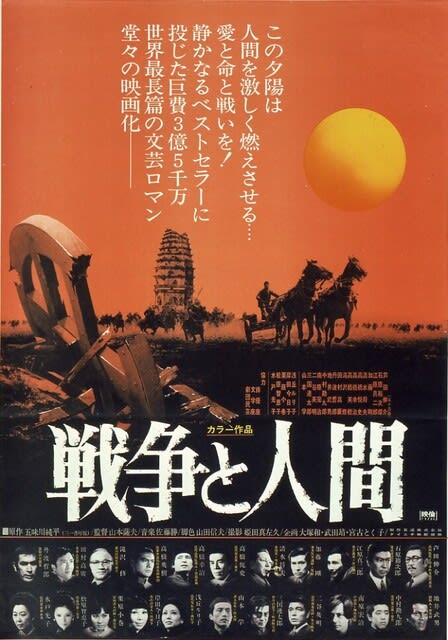太平洋戦争開戦から82年となったが、「アジア解放の聖戦であり、侵略戦争ではなかった」「戦艦大和はすごかった」など、ネットには戦争賛美と受け取れる情報が溢れていることを危惧している。
本書に登場する元特攻兵の多くは太平洋戦争を侵略戦争ではなく、アジア解放をして大東亜共栄圏を建設するための「大東亜戦争」と呼んでいるが、少年のころからの教育がまずあり、当事者として真摯に生き、多くの戦友が逝ったのだから無理からぬことで、安易に元現場将兵たちの歴史観を批判できないだろう。ところが戦後生まれは歴史を冷静に俯瞰できる立場なのだから、その悲劇を繰り返さないように努めるのが当たり前。
特攻は軍令部(海軍の大本営の名称)の発案や命令ではなく、自分は反対したが現場から要望されて許可した、というのが戦後の軍令部関係者たちの弁明。その弁明にはあらかじめ巧妙な責任逃れが仕組まれていた。実際には特攻兵器の開発をしていたし、各部隊に特攻の「員数」を割り当てていた。
大戦末期には満足な航空機やベテラン搭乗員が枯渇して、離着陸がやっとの、15歳から17歳くらいの少年航空兵も特攻要員になった。
「伏龍」は訓練で何人も事故死して、ついに実践配備されなかったが、真っ暗な海底で酸素がまわってこず息絶えていったのも少年航空兵たちで、いちどに数十人が亡くなったこともあった。身近な高校生に置き換えて想像してみて欲しい。
複葉の練習機で特攻していった少年航空兵もいたが、こちらは布張りの機体であったのでレーダーに捕捉されにくく、また被弾しても空中分解しにくいこともあり、なん機かは米艦船に損害をあたえている。
しかしながら、軍艦の上部構造に爆弾を炸裂させただけでは撃沈できないことは、日清日露以来の軍事常識だった。
また米艦船の遥か洋上でレーダーで捕捉され、数倍の迎撃機が待ちかまえていることも、運よく艦船にたどり着いてもレーダー管制された対空砲火を潜り抜けることは困難であることは、現場レベルではわかっていた。命令していていた高級軍人は現場の実情を知らなかった。
生還者の証言によると、近接するだけで爆発する砲弾(VT信管)をはじめとした砲弾銃弾が雨霰と降り注ぎ、目の前が真っ赤になるくらい激しい対空砲火だったそうだ。それでも特攻させた。
特攻兵器を開発したり、命じた高級軍人たちの多くは生き残って戦後を迎えた。隠遁生活を送った人もいるが、自衛隊幹部になったり国会議員になった人もいた。
特攻兵の遺族をまわって都合の悪いことが書かれた遺書を回収して歩き、特攻は命令ではなく自発的であった旨を書いた戦記を出版したのは、航空自衛隊の幕僚に栄達し中島元海軍中佐。
かわいそうと涙を流すなら、二度と戦争はゴメンだと思うなら、そうなった経緯と史実を学び、そのキナ臭い匂いを警戒しないといけない。