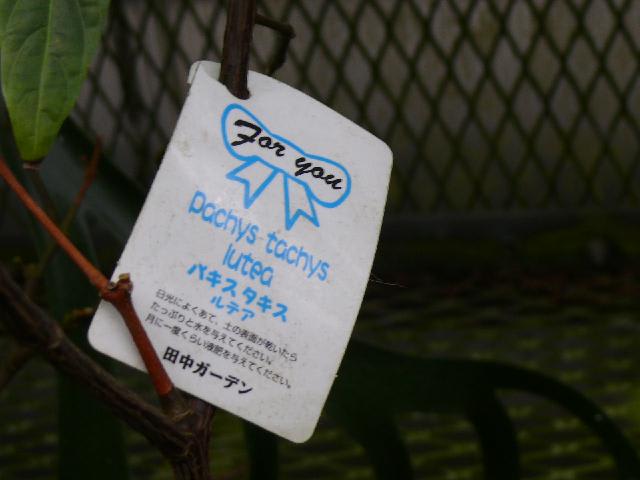2009年12月24日(木)、岩手県立花きセンター(胆沢郡金ケ崎町六原頭無2-1)の「花の館温室」内の亜熱帯温室に植えられているツンベルギア・グランディフロラ ’アルバ’が花を咲かせていました。花きセンターのホームページに「ツンベルギア”アルバ”」と紹介されていました。
http://www.pref.iwate.jp/~hp3005/migoro.html [花きセンター:花みごろ]





ツンベルギア・グランディフロラ ’アルバ’ キツネノマゴ科 ツンベルギア(ヤハズカズラ)属 Thunbergia grandiflora cv.'Alba'
ツンベルギアは、南アフリカや熱帯アジア(タイ、インドなど)に自生するつる性の非耐寒性常緑多年草で、長さ5~6mになる。熱帯各地で野生化している。苞の形からヤハズカズラ(矢筈葛)の名がある。普通に」栽培されているのは葉が革質で長卵形に近いタイプで、グランディフロラは冬から春によく開花するが、アルバは周年よく開花する。[以上、誠文堂新光社発行、日本インドア・グリーン協会編「熱帯花木と観葉植物図鑑」ほかより]
ツンベルギア・グランディフロラ Thunbergia grandifloraは、薄紫~青紫色で花冠は5~8㎝ほどの大きな花を沢山咲かせるつる性の常緑多年草、和名が「ベンガルヤハズカズラ(ベンガル矢筈葛)。英名はBlue trumpet vine(ブルー・トランペット・ヴァイン)、Sky flower(スカイ・フラワー)。「アルバ」は、ベンガル矢筈葛の園芸品種で、花は白色で直径6~8㎝と、母種よりやや大型。1mかそれ以上の長い花序を作る。周年開花性が強い。ツルは成長が早く、棚などを伝って長く伸びて、木質化する。花が非常によく似ているものに、「ローレルヤハズカズラ」と呼ばれる、同科のツンベルギア・ラウリフォリア(Thungergia laurifolia)がある。見分け方は、葉がグランディフロラ(ベンガルヤハズカズラ)の方がギザギザしているのに対し、ラウリフォリア(ローレルヤハズカズラ)の葉は月桂樹(ローレル)の葉に似て肉厚で、葉縁がツルツルしている。
ツンベルギアの仲間
ツンベルギア・アラタ(Thunbergia alata):ヤハズカズラ(矢筈葛);タケダカズラblack-eyed Susan vine;black eyed Susan;clock vine:熱帯アフリカ原産の常緑つ植物。温度があれば一年中開花する。花色は黄橙色で、のど部が黒紫色になる。
ツンベルギア・エラクタ(Thunbergia erecta):コダチヤハズカズラ(木立矢筈葛)king'smantle;bush clock vine、キンギョボク(金魚木):熱帯西アフリカ原産の常緑低木。花は径3.5~4.5㎝、濃青紫色で、のど部は濃黄色だが、開花後に淡青色に変わる。ほぼ周年開花する。
ツンベルギア・フラグランス(Thunbergia fragrans):ニオイヤハズカズラ、Sweet clock vine);angel wings;white lady:ネパール・インド・スリランカ原産の常緑つる植物。花は葉腋に単生し、径約5㎝、白色でのど部は淡黄色。栽培品では種名とは裏腹に香りがない。
ツンベルギア・グランディフロラ(Thunbergia grandiflora);Thunbergia chinensis:ベンガル・ヤハズカズラ(ベンガル矢筈葛)、Bengal clock vine;blue trumpet vine;bluesky flower;skyflower;babbler's bill;Bengal trumpet;sky vine:インド~東南アジア原産の大型になる常緑つる植物。地下部は多肉塊茎状になる。花は長く垂れる花序につき、径5~6㎝、淡青紫色でのど部は淡黄色。
ツンベルギア・ラウリフォリア(Thunbergia laurifolia);Thunbergia harrisii;Thunbergia grandiflora var.laurifolia:ローレル葛、ゲッケイカズラ(月桂葛)、ブルートランペットバイン(Blue trumpet vine)、ベンガル・ヤハズカズラ(ベンガル矢筈葛)、laurel clock vine;skyflower;babbler's vine;babbler's bill:東南アジア原産の常緑つる植物。葉はやや細長く、基部は円脚~ほこ型で、ゲッケイジュ(月桂樹)に似たタイプもある。長く垂れる花序に多くの花をつける。花冠は淡青色で、のど部は黄色味を帯びる。花期は秋~春。
ツンベルギア・グレゴリー(Thunbergia gregorii);Thunbergia gibsonii;オレンジクロックバイン(orange clock vine):熱帯アフリカ原産の常緑つる植物。葉・茎・花とも小型だが、生育は早い。花は径3.5~4㎝で明橙色。花期は春。
ツンベルギア・コッキネア(Thunbergia coccinea);ベニバナヤハズカズラ:ネパール・ブータン・シッキムに分布。つる性草本で、高さ6~9mになる。長さ30~90㎝の総状花序を下垂し、径約2㎝で、橙黄色~橙赤色の花をつける。苞は暗赤紫色。花期は冬~春。
ツンベルギア・バティスコンベイ(Thunbergia battiscombei)
http://metabolomics.jp/wiki/Species:Thunbergia [Thunbergia]
http://stewartia.net/engei/engei/Kitunenomago/Thunbergia.html [ツンベルギア]