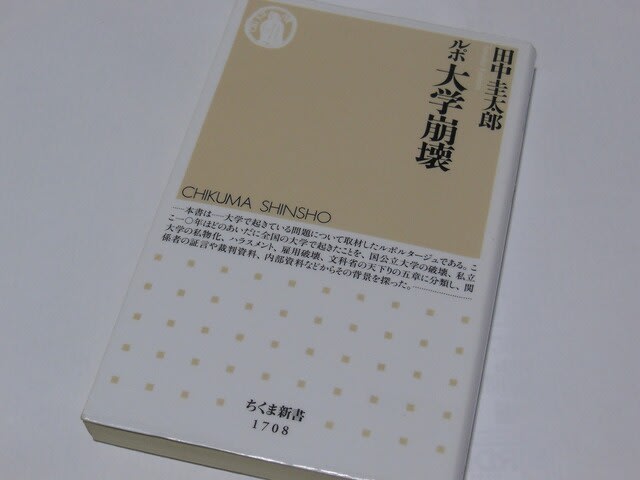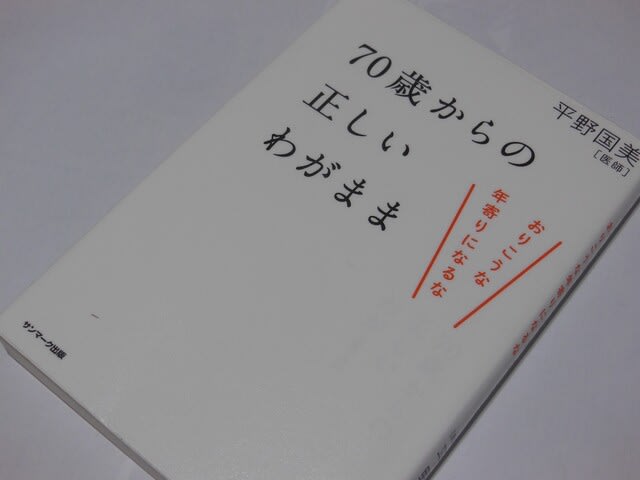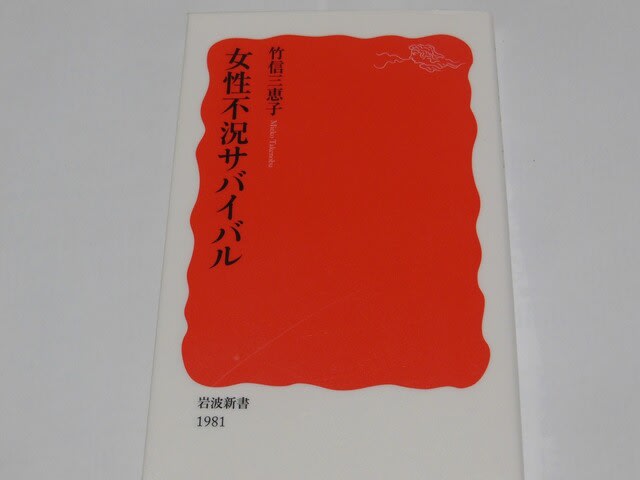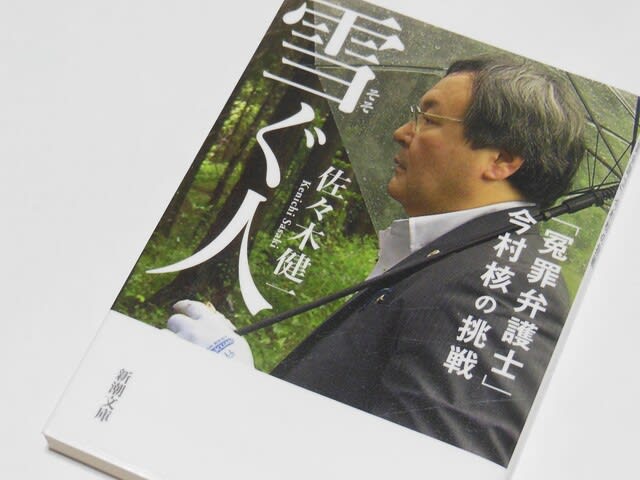独立行政法人化と運営費交付金の削減、国立大学法人法改正による学長選考方法の自由化などによって独裁化と政府による支配が進む国立大学の惨状、私立学校法の改正で(学長・総長ではなく)理事長がトップとなり理事長の思うがままに運営できることになったことで私物化が促進された私立大学の惨状、多発するハラスメント、有期雇用職員の雇止め、非常勤教職員の雇止め等の雇用破壊、文科省役人の天下り等の実情を報じた本。
最初に紹介されているのが、吉田寮自治会に対して訴訟提起して立ち退きを求め、タテカン(立て看板)を一方的に撤去して学生・教職員組合と対立している私の出身校京都大学です。私が在学していた頃には、まだノーベル賞受賞者輩出などよりも「反戦自由の伝統」を誇りに思う風潮があったのですが、落ちぶれ変わり果てた姿に悄然とします。
有期雇用の職員や教職員の雇止めに関しては、裁判上、雇止めが有効とされる(労働者敗訴)ケースが相次いでいます。それは、労働契約の条項や規則、担当業務の差替えなどを工夫して、おそらくは使用者側の弁護士の入れ知恵で大学側がうまく立ち回っているためです。判決文を読んでいるとため息が出ますが、裁判所にはそういった大学側の小ずるい手法が今のところ効いています。こういったやり方は、短期的には大学側=使用者側の勝利となっていますが、このような状態が続けば、大学での有期雇用が、「大学」という言葉/ブランドが与えるイメージとは異なり、極めて不安定な労働者・研究者にとって割に合わないものだということがいずれは世に知れ渡り、大学は有能な人材を確保できなくなると、私は憂いているのですが。

田中圭太郎 ちくま新書 2023年2月10日発行
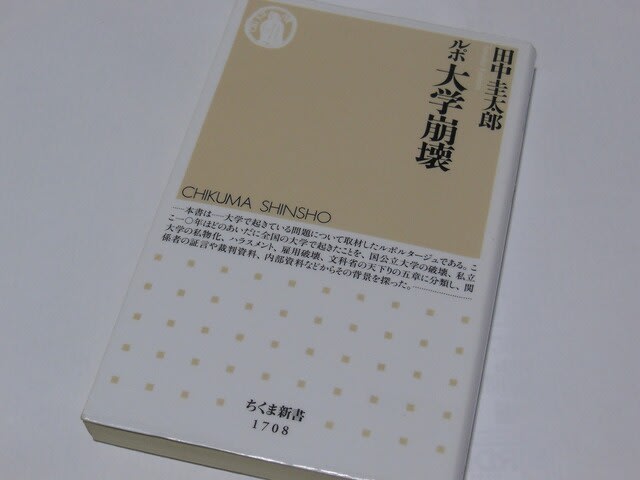
最初に紹介されているのが、吉田寮自治会に対して訴訟提起して立ち退きを求め、タテカン(立て看板)を一方的に撤去して学生・教職員組合と対立している私の出身校京都大学です。私が在学していた頃には、まだノーベル賞受賞者輩出などよりも「反戦自由の伝統」を誇りに思う風潮があったのですが、落ちぶれ変わり果てた姿に悄然とします。
有期雇用の職員や教職員の雇止めに関しては、裁判上、雇止めが有効とされる(労働者敗訴)ケースが相次いでいます。それは、労働契約の条項や規則、担当業務の差替えなどを工夫して、おそらくは使用者側の弁護士の入れ知恵で大学側がうまく立ち回っているためです。判決文を読んでいるとため息が出ますが、裁判所にはそういった大学側の小ずるい手法が今のところ効いています。こういったやり方は、短期的には大学側=使用者側の勝利となっていますが、このような状態が続けば、大学での有期雇用が、「大学」という言葉/ブランドが与えるイメージとは異なり、極めて不安定な労働者・研究者にとって割に合わないものだということがいずれは世に知れ渡り、大学は有能な人材を確保できなくなると、私は憂いているのですが。

田中圭太郎 ちくま新書 2023年2月10日発行