出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
空技廠 P1Y 銀河

銀河一一型
銀河(ぎんが)は大日本帝国海軍(以下、海軍)が開発・実用化した双発爆撃機。海軍の航空機関連技術開発を統括する航空技術廠(以下、空技廠)が大型急降下爆撃機として開発した機体だが、一式陸上攻撃機(以下、一式陸攻)の後継機として太平洋戦争後半の戦いに投入された。連合国軍によるコードネームは「Frances」(連合軍は当初本機を戦闘機と誤認して「Francis」という男性名を付けたが、爆撃機と判明した後に女性名である「Frances」に変更したという)。
開発の経緯と名称
昭和14年(1939年)頃、海軍では将来の基地航空兵力には、ヨーロッパ戦線で活躍しているような大型の急降下爆撃機を配備するのが望ましいと考えられていた。これは、日中戦争における九六式陸上攻撃機の戦訓から、今まで以上の高速と航続力、大型爆弾を用いての急降下爆撃などが求められていたためである[1]。その頃、空技廠では速度記録機Y10、航続距離記録機Y20、高度記録機Y30の研究を行っていたが(その後の国際情勢の悪化に伴い、Y10とY30は計画中止)、海軍からの要求に応えるかたちで、Y20をベースにドイツから輸入したJu 88 Aに使用されている技術を導入する(実際にはほとんど参考にならなかった)ことで高性能爆撃機を開発することとなり、十三試艦上爆撃機(D4Y1。後の彗星)試作一号機が初飛行して間もない昭和15年(1940年)末に「十五試陸上爆撃機」として開発が命じられた。開発主務者は彗星の設計主務者を務めた山名正夫技師(実際には総括主務の三木忠直技師が指揮していた)。
十五試陸爆に対する海軍の要求性能は、概ね下記の様なものだったとされる。
- 一式陸攻と同等の航続力を持つこと(約5,556km)。
- 零式艦戦と同等の速力を発揮可能なこと(約511.2km/h)。
- 雷撃並びに1トン爆弾での急降下爆撃が可能なこと(急降下制限速度648.2km/h)。
- 離陸滑走距離600m以内。
なお、日本海軍の定義では急降下爆撃機が「爆撃機」、雷撃機が「攻撃機」に分類される。本機は爆撃機として開発が始まり、途中で雷装可能であることが追加要求され、雷爆可能となった機体であるが、爆撃機に分類され、名称も爆撃機の命名基準に従ったものになっている。なお同様に急降下爆撃と雷撃を兼用する艦上機である流星(B7A1)は艦上攻撃機に分類されているが、名称は艦上爆撃機の命名基準に従ったものになっている。
設計の特徴

銀河の機首。電探(レーダー)用の八木アンテナが装備されている
機体の小型・軽量化、空力学的洗練に努めつつ、彗星で採用された技術を踏襲している。
胴体
小型・軽量化のため、一式陸攻を始めとする双発爆撃機では7名程度の搭乗員数(操縦員、電信員各2名、偵察員及び機銃員数名)を3名(操縦員、偵察員、電信員)に削減することで胴体の最大幅を一式陸攻の60%の1.2m(エンジンカウルの直径とほぼ同じ)に抑え、前面投影面積の最小化による空気抵抗の削減を図っている。また風防を低く抑えたため、彗星と同じ背負式落下傘を採用している。
爆弾倉は全長5mを超える九一式航空魚雷でもほぼ収納することができ、魚雷または800kg爆弾は1発、500kgまたは250kg爆弾は2発搭載することが出来た(各爆弾は爆弾誘導桿を介して取り付けられる)。爆弾倉には魚雷や爆弾の代わりに内蔵式の増加燃料タンクも搭載可能だが、一式陸攻の様に30~60kgの小型爆弾を多数搭載することは出来ない。爆弾倉扉も彗星と同じ胴体内側に畳み込む方式で、爆装時のみならず爆撃時における空気抵抗の増加を防いでいる。
主翼
戦闘機並みの速力と高速急降下からの引き起こしに耐える剛性を実現するため、主翼面積を一式陸攻より約30%小さい55m2に抑えている。その結果、試作機が要求性能を超える最高速度と急降下制限速度を記録する一方、翼面荷重が正規時でも一式陸攻の過荷重時を超える191kg/m2(一一型。過荷重時は245kg/m2)になっている。翼型は彗星と同じく、内翼側が層流翼に近いもので、外翼側にいくにつれて翼端失速しにくい通常の翼型に変化する半層流翼を採用しており、配置も彗星と同じ中翼である。要求性能にある離陸滑走距離を実現するため、フラップは型式こそ彗星と同じセミファウラー式だが、胴体とエンジンナセルの間の部分にスプリット式の子フラップを持つ親子式フラップを採用している。
急降下抵抗板は彗星と同じ補助フラップ兼用とすることで空気抵抗の低減に努めている。補助翼も彗星と同じ補助フラップとして使用可能になっているが、やはり主翼幅の55%を占めるフラップのため補助翼の長さを十分にとることが出来ず、夜間戦闘機として採用された際は効きの不足が指摘されている。主翼の主桁と前後の補助桁の間には片翼に7個の燃料タンクが設けられており、5個は通常の型式だが、外翼前縁側の2個のみセミインテグラル式になっている。
発動機]
試作段階だった小型高出力発動機の誉を日本軍機の中で最も初期に採用している。このため、十五試陸爆試作機の試験飛行が開始された時点では誉の完成度も低く、空技廠での性能試験中に20回を超える故障が起きている。試作機では誉一一型を搭載していたが、量産型では高高度性能を改善した誉一二型に変更している。小型の誉に合わせ、発動機直径の1.1倍という小直径で抵抗の少ないエンジンナセルが装備されている。排気管は試作機では集合式だったが、量産機では推力式単排気管に変更されている。
夜間戦闘機型の試製極光(P1Y2-S)では、生産数が不足気味の誉一二型からやや大型ではあるが生産数にやや余裕のある火星二五型に発動機を変更し、エンジンナセルも新たに設計されている。
武装と防弾
小型・軽量化という設計方針に従い、一式陸攻では5挺程度搭載されていた防御用旋回機銃も前方と後上方の各1挺ずつ(試作機は7.7mm機銃。量産型は20mmまたは13mm機銃)に削減されている。但し、後上方用旋回機銃を使用するために後部風防を開けると速度が低下することと、防御火器の増強が求められたため、後上方旋回機銃を動力式の13.2mm連装機銃に変更した型も試作されている。また夜間戦闘機型では後上方旋回機銃を廃止して、胴体後部に20mmまたは30mm斜銃を装備している。
防弾装備はかなり充実しており、操縦員後方には折畳式の防弾板、戦闘・離脱時に使用する通常型燃料タンクを自動防漏式とした上で自動消火装置とセミインテグラル式の外翼前縁側燃料タンクへの炭酸ガス充填装置も装備されており、一式陸攻で問題となった被弾時の脆弱性の改善に努めている。その他 操縦員の負担軽減のため、自動操縦装置やリクライニング機能付きの操縦席が装備されている。また大航続力を得るため、両主翼下に容量600Lの大型落下式増槽を各1本懸吊することも可能。主脚やフラップ、爆弾倉扉の開閉には電動を採用した彗星で不具合が続出したこともあり、本機では油圧を採用している。彗星での反省を元に生産性に配慮した設計が行われたが、生産を担当する中島飛行機の実情とあわない点があり、十分な効果を上げることは出来なかった。
実戦
試作機の審査と量産への移行 ]
昭和17年(1942年)6月から完成し始めた試作機は、最高速度566.7km/h/5,500m、航続距離5,371km、急降下最終速度703.8km/hという海軍の要求を超える高性能を発揮した。戦況の悪化から早期の実用化が求められたため、通常は空技廠での性能試験終了後に行われる横須賀航空隊での実用試験が性能試験と平行して行われ、昭和18年(1943年)8月には転換生産を行う中島飛行機製の試作機も完成、同年11月から本格的に量産が開始された。
部隊配備
昭和19年(1944年)10月に陸上爆撃機銀河一一型(P1Y1)として制式採用されたが、実際には最初の実戦部隊である第五二一航空隊はその1年以上前に開隊していた。第五二一航空隊はマリアナ沖海戦とニューギニア戦線に投入されたが、アメリカ海軍の猛攻により壊滅した。その後も、台湾沖航空戦、レイテ戦、九州沖航空戦、沖縄戦等に投入された。
銀河による戦果としては、昭和20年(1945年)3月に実施された丹作戦(ウルシー環礁のアメリカ艦隊奇襲攻撃)において、二式大艇に誘導された梓特別攻撃隊の銀河24機が九州の鹿屋基地から長駆2,300km(これは直線距離であり、実際の飛行経路は約2,930km)を飛行した後、薄暮特攻攻撃を決行、福田幸悦大尉機といわれる1機がタイコンデロガ級航空母艦「ランドルフ」の艦尾を大破させたことと、同じく昭和20年(1945年)3月の九州沖航空戦時に第五航空艦隊第七六二航空隊の銀河1機が、急降下爆撃により四国南方沖でエセックス級航空母艦「フランクリン」に250kg爆弾2発を命中させて、同艦を沈没寸前まで追い込んだことが有名である。
高性能を追求した本機の機体や発動機の構造は複雑なものがあり、生産性・整備性はあまり芳しいものではなかった。特に誉の故障が多く、稼動率の低下に拍車をかけ、搭乗員や整備員にとって大きな負担となったが、一式陸攻に代わる主力爆撃機として終戦まで戦い続け、各型合計で約1,100機生産された。終戦時の残存機数は182機。
夜間戦闘機への転用
現用の夜間戦闘機月光(J1N1-S)より高速かつ搭載能力に優れていたことから、比較的早い段階から夜間戦闘機への転用が構想されており、月光が夜間迎撃で初戦果を挙げた昭和18年(1943年)5月、川西に対してP1Y1夜戦改修型(後の試製極光)の開発が命じられている。主な改修点は火星二五型への発動機換装と20mm斜銃の追加装備で、昭和18年(1943年)7月に設計終了、昭和19年(1944年)5月に試作一号機が完成している。その後、少数が部隊配備されたもののB-29の迎撃には速度や高高度性能が不足と判定され、ほとんどの機体は爆撃機型の銀河一六型に再改修されている。
海軍正式の開発計画である試製極光とは別に、実戦部隊である第三〇二航空隊において、銀河一一型または一六型に20mmまたは30mm斜銃を追加装備した夜間戦闘機型への改修が行われている。この改造夜間型は試製極光とは異なり、斜銃の他に三号爆弾を搭載してB-29の夜間迎撃に投入され、撃墜戦果を報じている。
戦後
戦後、銀河設計陣の一人であった三木忠直は、初代新幹線「0系」の開発にあたり、銀河の胴体形態をデザインモチーフに用いたと述べている。なお、アメリカ軍により戦後接収された一一型が1機だけスミソニアン博物館に分解保存されている。
派生型
銀河の主要な派生型には以下のようなものが存在するが、この他に爆弾倉に下向きの20mm斜銃を10数挺備えた襲撃機型や試作ジェットエンジンのテストベッド型が作られ、また桜花母機型も計画されていた。
- 十五試陸上爆撃機(P1Y1)
- 誉一一型(離昇1,825馬力)を装備した試作型。
- 一一型(P1Y1)
- 高高度性能を向上させた誉一二型を装備した量産型。旋回機銃は機首、後部とも20mm。試作機では引き込み式だった尾輪を固定式に変更。後期の機体では風防形状を変更し、H-6型レーダーを追加した。後部旋回機銃を20mmから13mmに変更した一一甲型(P1Y1a)も生産され、後部旋回機銃を動力式の13mm連装に変更した仮称一一乙型(P1Y1b)、仮称一一乙型の機首旋回機銃を13mmに変更した仮称一一丙型(P1Y1c)も試作された。
- 仮称二一型(P1Y1-S)
- 一一型の夜間戦闘機型。当初は銀河一一型の航続距離及び搭載量の向上を図った性能向上型だったが、夜間戦闘機型に変更されている。搭乗員数を2名に削減する代わりにレーダーを搭載し、20mm斜銃を4挺搭載する計画だった。昭和20年(1945年)7月の海軍航空本部の資料では、仮称一二型(P1Y4)の夜間戦闘機型とされているが、同じ文書に仮称二一型の発動機は誉一一型または一二型と明記されていることと型式名が発動機変更を示していないことから誤記と思われる。
- 一六型(P1Y2)
- 発動機を火星二五型に変更した型。試製極光からの転用。一一型と同じ武装変更を施した仮称一六甲型(P1Y2a)、仮称一六乙型(P1Y2b)、仮称一六丙型(P1Y2c)も試作された。
- 仮称三三型(P1Y3)
- 発動機を誉二一型(離昇1,990馬力)に変更、主翼をやや大型化し、胴体を太くして副操縦員席を追加した性能向上型。機体が一回り大型化し、航続距離が大きく向上する予定だった。防御火器は一一丙型と同じで、爆弾倉も小型爆弾を多数搭載できるように変更。設計中に終戦。
- 仮称一二型(P1Y4)
- 発動機を燃料噴射装置を追加した誉二三型(離昇1,990馬力)に変更した性能向上型。試作のみ。
- 仮称一四型(P1Y5)
- 発動機をハ四三-一一型(離昇2,200馬力)に変更した性能向上型。計画のみ。
- 仮称一七型(P1Y6)
- 一六型の発動機を火星二五丙型に変更した型。試作のみ。
- 試製極光(P1Y2-S)
- 銀河をベースに開発された夜間戦闘機型。火星二五型への発動機変更、20mm斜銃2挺の追加等の改修が川西で施されている。一部が実戦配備されたが夜間戦闘機としては性能が不足していたため、大半が一六型に再改修された。
諸元
| 制式名称 | 銀河一一型 | 銀河一六型 |
|---|
| 機体略号 |
P1Y1 |
P1Y2 |
| 全幅 |
20.0m |
同左 |
| 全長 |
15.0m |
同左 |
| 全高(水平) |
5.3m |
同左 |
| 主翼面積 |
55.0m2 |
同左 |
| 自重 |
7,265kg |
7,138kg |
| 正規全備重量 |
10,500kg |
同左 |
| 過荷重重量 |
13,500kg |
同左 |
| 発動機 |
誉一二型(離昇1,825馬力) |
火星二五型(離昇1,850馬力) |
| 最高速度 |
546.3km/h(高度5,900m) |
522.3km/h(高度5,400m) |
| 実用上昇限度 |
9,400m |
9,560m |
| 航続距離 |
1,920km(正規)/5,370km(過過重) |
1,815km(正規) |
| 爆装 |
250~500kg2発又は800kg爆弾1発 |
同左 |
| 雷装 |
九一式航空魚雷1発 |
同左 |
| 武装 |
20mm旋回機銃2挺(機首・後部) |
同左 |
| 乗員 |
3名 |
同左 |
銀河と飛龍
銀河と同時期に開発・実用化された日本製双発爆撃機として陸軍の四式重爆撃機「飛龍」(以下、四式重爆)がある。この二機は、共に雷撃と急降下爆撃の両方が可能な双発爆撃機として登場している。
しかし、銀河は実験機をベースに開発されたこともあり、
- 高性能ではあるが大量生産を想定していない。
- 「国滅びて銀河あり」と揶揄される[2]ほど機体や発動機に余裕が無いため整備が難しかった。
- 最低限の防御火器(機首及び後部に20mmまたは13mm機銃各1挺)しか装備していなかった。
のに対し、四式重爆は
- 最高速度や搭載力が銀河とほぼ同じであるにも拘らず、大量生産を考慮されていた。
- 機体や発動機の信頼性が高かった。
- 強力な防御火器(機首、左右胴体側面、尾部に12.7mm各1挺、背部に20mm1門)を備えていた。
という対照的な設計がなされていることから、銀河より四式重爆を高く評価する意見も一部にある。
生産機数についてみると、初飛行や量産開始時期がほとんど同時期であるにも拘らず、銀河が約1,100機であるのに対し、四式重爆は約700機と銀河の約6割に留まっている。生産機数を見る限り、銀河の生産性が四式重爆に大幅に劣っているとは断言しにくい(生産に当たった中島飛行機が銀河専門の設計課を設置して生産性向上のための設計変更を行っていることを指摘する意見もあるが、同様の設計変更は雷電や流星等でも行われている)。
銀河一一型と四式重爆一型の燃料搭載量を比較すると、四式重爆は銀河の7割以下(機内搭載量のみ。銀河が落下増槽を装備した場合6割以下)であり、これがそのまま航続力の差となって現れている。このため、大戦末期に四式重爆を長距離攻撃に投入するには航続力が不足となり、防御火器を大幅に削減(尾部12.7mm2挺のみ)する代わりに燃料タンクを増設した長距離攻撃型(発動機出力が変わらずに重量が約1割増加している上に主翼も大型化しており、一式陸攻二四丁型等の例から最高速度等は低下していると推定される)の開発に着手したものの、試作段階で終戦を迎えている。
また銀河・四式重爆は共に高速力と搭載能力を買われて対B-29用の戦闘機型も作られている。しかし、20mmまたは30mm斜銃を搭載しただけの銀河の急造夜間戦闘機型が確実と思われる撃墜戦果を複数挙げているのに対し、75mm高射砲を搭載するという大改造が施された四式重爆の特殊防空戦闘機型(キ一〇九)はB-29と交戦した試作機が一度不確実な撃破を報じただけに終わっている。
長距離攻撃やB-29の迎撃において銀河が大きな戦果を挙げている訳ではない。しかし、低稼働率であったB-29がその高性能を活かして日本軍を苦しめたことに代表されるように、必要とされる時に必要とされることが出来たという点も、四式重爆で高く評価される実用性と同じくらい兵器においては重要であり、この点においては銀河に軍配が上がると考えられる。
この他にも、銀河と四式重爆だけでなく、陸海軍が零戦と一式戦「隼」、雷電と二式単戦「鍾馗」、月光と二式複戦「屠龍」、紫電改と四式戦「疾風」など類似した機種を個別に開発・生産したことについて、機種数が少ない方が開発、生産、整備とそれに必要な部品供給が効率的・合理的に行えるとの観点から人的・物的資源の浪費ではないかという指摘がなされている。
開発面においては、陸海軍からの多数の開発発注のため、各航空機メーカーの設計陣に大きな負担がかかっていた(例えば、堀越二郎は過労と診断されて二ヵ月の休養を余儀なくされている)のは事実である。しかし、航空機開発においては複数社による競作という形でバックアップ体制を整えていることが一般的であるにも拘らず、不採用機が無駄になることから、陸海軍とも昭和10年代初めに単独指名開発に移行している(F6FとF4U、B-29とB-32に見られるように、アメリカは競作開発のまま)。陸海軍ともバックアップ機の廃止により効率化を図っている以上、類似機種の並行開発を一概に非効率と断定することは難しい。
生産面では、工場担当者が闇市で原材料を入手したという話がある様に、戦時下の日本での航空機生産においては原材料や電力の供給がネックとなって、生産機種の限定や性能を犠牲にして生産性を高める設計をしなければならないほど、生産ラインを稼働させられなかったのではないかという意見もある。また、生産される機体数に対して不足気味であった発動機については陸海軍共ほぼ同じもの(装備する機体に合わせた仕様の変更などは行われている)を使用しており、性能を犠牲にしてまで機体の生産性を上げる意義は見出し難い。また生産機種を絞った場合には転換生産を大規模に行う必要があるが、生産が軌道に乗るまでにはかなりの時間を要す場合が多く、転換生産メーカーが生産しやすいように微妙な変更を加える例も多数見られるため、生産や整備の効率化、部品の共通化が大幅に進むとは必ずしも言えない。また生産を固定した機種に大きな欠陥が認められた場合、対策が取られるまで戦力が大幅に低下することは避けられず、戦力維持の面からはある程度の機種を揃えることも必要である。
銀河と四式重爆は開発・生産メーカーや装備発動機ばかりか設計思想まで異なっていたという意味では、両者は理想的なバックアップ体勢の関係にあり、両者とも開発に成功したために機種統一されることなく生産・実戦配備に至ったと言える。
参考文献
- ^ 保存版 軍用機メカ・シリーズ13「銀河/一式陸攻」光人社 刊
- ^ 「帝国陸海軍用機ガイド」 安東亜音人 著 新紀元社 刊 ISBN 4883172457
![]()










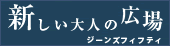

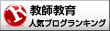

 〔PHOTO〕gettyimages
〔PHOTO〕gettyimages












