外務省の外交史料館に行ってきました。
外交文書を保存し、外交史の編纂を行う
一風変わった役所と言えます。
外務省とは離れた場所にあると同時に、
業務内容も外務省本省とは異なります。
ミニ博物館(兼)研究所と言えます。
外務省のいわゆる外交官ではなくて、
研究者として別枠で採用された人が、
研究に携わっています。
博物館のように修学旅行生が来れば、
職員が丁寧に説明をしてくれます。
とても勉強になると思います。
歴史の教科書に出てくる外交文書が、
展示されています(複製ですが)。
高校生には良い見学先だと思います。
展示物の説明文が、日本語だけでした。
外国人にも興味深い展示が多いのに、
とても残念な気がしました。
私は、以前に英国の国立公文書館に行って、
日英修好通商条約の英国側保管文書を見て、
ちょっと感動した覚えがあります。
外交文書は双方の国で保管しているので、
相手国の外交官が日本側の資料を見て、
とても感動する例もあるそうです。
例えば、リトアニアという国があります。
戦前は独立していたのに、ソ連に併合され、
独立を回復するまで数十年かかりました。
戦前のリトアニア外務省の資料の大半は、
ソ連に持ち出され、返還されていません。
当時の史料を見る機会も少ないそうです。
リトアニアの外交官が外交史料館に来て、
戦前のリトアニア大統領の署名文書を見て、
とてもよろこんでいたそうです。
各国の大使館員や留学生、研究者などに、
もっと開かれた外交史料館にすべきです。
そのためにはせめて英語の説明を増やし、
在京各国大使館に広報すべきです。
昨日はちょうど杉原千畝の展示をしていて、
杉原千畝の研究者として有名な職員の方に、
詳しい説明をしていただきました。
外交史料館の白石仁章さんという研究者で、
新潮選書「諜報の天才 杉原千畝」という、
読み応えのある本を書かれている方でした。
白石さんの説明を聴き、杉原さんのお陰で、
イスラエルやユダヤ人の対日イメージが、
いかに改善されたかがわかりました。
杉原千畝という外交官が残した貴重な遺産は、
いまでも日本外交に大いに役立っています。
もっと活用すべきだと思います。
最近では「アンネの日記」破損事件もありましたし、
某大臣のナチス肯定と見られかねない発言もあり、
日本のイメージアップが必要な時期です。
ユダヤ人コミュニティは世界中にあります。
アメリカやヨーロッパのいろんなところに、
ホロコースト記念館があります。
そういう記念館に杉原千畝関係の歴史史料を
貸し出して展示してもらうといったことは、
安上がりで効果的な広報活動だと思います。
外交史料館という地味な外務省の組織は、
うまく活用すれば、役に立つと思います。
十分活用していないのが、残念に思います。
引用元http://yamauchi-koichi.cocolog-nifty.com/blog/










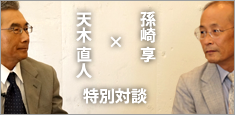
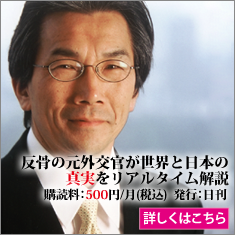






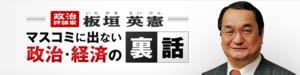


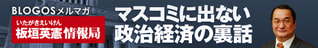
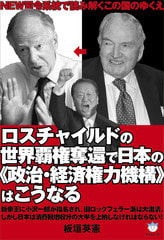
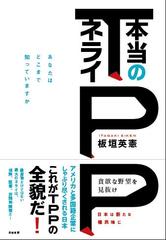
 2月開催の勉強会がDVDになりました。
2月開催の勉強会がDVDになりました。

 コメントは受け付けていません。 |
コメントは受け付けていません。 | 

 投稿: hamousa
投稿: hamousa 





