現在、 『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
本日、 ドキドキ
ドキドキ 。
。
今日は、昨日の自然菜園スクールの自然菜園/実践コースに引き続き、自然稲作発酵コースの稲刈りです。台風18号の影響が小さく、かなり稲刈りできる可能性が高くなってきました。ありがたいことです。

昨日は、自然菜園スクールの自然菜園/実践コースでした。
来月からは、入門コースとの合同なので、単独の実践コースとしては今年最後の講座でした。

実践コースは、継続できるように今年から本格的になりましたので、越冬を今月はテーマにし、夏野菜などは片づけ=来春の準備。イチゴやキャベツ、ニンニク、タマネギなど越冬野菜についていろいろお伝えしました。

自然菜園2年目は、不耕起1年目の年になります。蓄えもなく、草や生き物のバランスも安定しないので、最も厳しい1年になることが予想されるので、そのために霜が降りる前から来年の菜園がよりよくなるようにお世話することがとても重要です。

先週の自然育苗種採りコースの入門編として、夏野菜の代表のトマトの自家採種もご紹介させていただきました。

現在、初秋を迎え、夏草の最後の勢いがあり、タネを残し枯れて行く夏草の中に、

イチゴを植えました。

イチゴと相性の良いニンニクは、不耕起や寒冷地にぴったりの「つるつる」植えをご紹介しました。
薄皮を剥いて植えることで、越夏したニンニクのように、自然に育つことができ、越冬するのによい根を張ってくれます。

タマネギは、菜園スクールの畑がタマネギに向いていない火山灰土ということもあり、ミニタマネギ(500円サイズ以下10円以内)の球根を植える方法をご紹介。
ちょっとしたコツを知っておくととても植えるのが簡単です。


ペコロスサイズよりも小さい、茎の部分(固い部分)と葉(可食部)がくっついている極少タマネギを使います。
自然農法のタマネギの真価は、玉の大きさではなく、葉の結球が固くしっかりしており、葉の枚数が多いことにあります。
その結果、通常のタマネギよりはちょっと小さくなりますが、保存性が高く、美味しいタマネギになってくれます。

自然菜園・実践コースは、雑穀も育てており、今はソバの花が見ごろです。

タカキビの収穫を今回収穫し、

モチキビは、鳥に食べられ全滅。
糸を張ったのですが、風でずれてしまっていたので、残念です。
トリは「実を取り逃がさない」が、一説に語源だそうです。

アマランサスは収穫後、種を落とさないように、運び、土や石が混ざらないようにすぐに脱穀し、脱穀後の穂を乾燥させ、さらに後日2回目の脱穀を行います。

自然菜園実践コースでは、農園そのものをどのように維持したり、よくしていく食べ物が自給でき、自足可能な方法なのかも学びます。
ちょっとしたスペースの場合、広すぎる場合、畦草の管理(刈るタイミング、刈った草の活用法、近所・地域との付き合い方)も含まれます。
雑穀は、痩せ地でも肥えていても、元休耕地でも育てやすいもので、後は収穫、食べられるところまでのタイミングとコツを抑えれば、OKな長期保存可能な主食(穀類)になります。
今朝は、台風と稲刈りが気になって3時に起きてしまいましたので、久々のブログを書いてみました。
お盆を過ぎると一気に忙しくなりいよいよ稲刈りスタートです。
2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回10/4(水)
・秋野菜の収穫のポイント?/ダイコン、カブ、サツマイモなどの収穫
・秋の土づくり/堆肥の造りと施し方、緑肥作物の導入法
・越冬野菜の定植・種まきのコツ/タマネギ、キャベツ、エンドウ、ムギなど
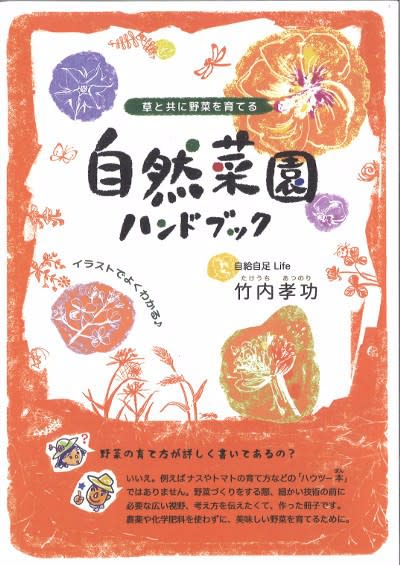
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中~
 『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~本日、
 ドキドキ
ドキドキ 。
。今日は、昨日の自然菜園スクールの自然菜園/実践コースに引き続き、自然稲作発酵コースの稲刈りです。台風18号の影響が小さく、かなり稲刈りできる可能性が高くなってきました。ありがたいことです。

昨日は、自然菜園スクールの自然菜園/実践コースでした。
来月からは、入門コースとの合同なので、単独の実践コースとしては今年最後の講座でした。

実践コースは、継続できるように今年から本格的になりましたので、越冬を今月はテーマにし、夏野菜などは片づけ=来春の準備。イチゴやキャベツ、ニンニク、タマネギなど越冬野菜についていろいろお伝えしました。

自然菜園2年目は、不耕起1年目の年になります。蓄えもなく、草や生き物のバランスも安定しないので、最も厳しい1年になることが予想されるので、そのために霜が降りる前から来年の菜園がよりよくなるようにお世話することがとても重要です。

先週の自然育苗種採りコースの入門編として、夏野菜の代表のトマトの自家採種もご紹介させていただきました。

現在、初秋を迎え、夏草の最後の勢いがあり、タネを残し枯れて行く夏草の中に、

イチゴを植えました。

イチゴと相性の良いニンニクは、不耕起や寒冷地にぴったりの「つるつる」植えをご紹介しました。
薄皮を剥いて植えることで、越夏したニンニクのように、自然に育つことができ、越冬するのによい根を張ってくれます。

タマネギは、菜園スクールの畑がタマネギに向いていない火山灰土ということもあり、ミニタマネギ(500円サイズ以下10円以内)の球根を植える方法をご紹介。
ちょっとしたコツを知っておくととても植えるのが簡単です。


ペコロスサイズよりも小さい、茎の部分(固い部分)と葉(可食部)がくっついている極少タマネギを使います。
自然農法のタマネギの真価は、玉の大きさではなく、葉の結球が固くしっかりしており、葉の枚数が多いことにあります。
その結果、通常のタマネギよりはちょっと小さくなりますが、保存性が高く、美味しいタマネギになってくれます。

自然菜園・実践コースは、雑穀も育てており、今はソバの花が見ごろです。

タカキビの収穫を今回収穫し、

モチキビは、鳥に食べられ全滅。
糸を張ったのですが、風でずれてしまっていたので、残念です。
トリは「実を取り逃がさない」が、一説に語源だそうです。

アマランサスは収穫後、種を落とさないように、運び、土や石が混ざらないようにすぐに脱穀し、脱穀後の穂を乾燥させ、さらに後日2回目の脱穀を行います。

自然菜園実践コースでは、農園そのものをどのように維持したり、よくしていく食べ物が自給でき、自足可能な方法なのかも学びます。
ちょっとしたスペースの場合、広すぎる場合、畦草の管理(刈るタイミング、刈った草の活用法、近所・地域との付き合い方)も含まれます。
雑穀は、痩せ地でも肥えていても、元休耕地でも育てやすいもので、後は収穫、食べられるところまでのタイミングとコツを抑えれば、OKな長期保存可能な主食(穀類)になります。
今朝は、台風と稲刈りが気になって3時に起きてしまいましたので、久々のブログを書いてみました。
お盆を過ぎると一気に忙しくなりいよいよ稲刈りスタートです。

2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回10/4(水)
・秋野菜の収穫のポイント?/ダイコン、カブ、サツマイモなどの収穫
・秋の土づくり/堆肥の造りと施し方、緑肥作物の導入法
・越冬野菜の定植・種まきのコツ/タマネギ、キャベツ、エンドウ、ムギなど
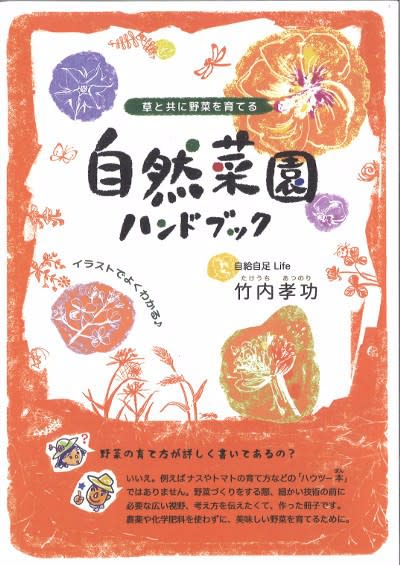
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中~





















