
現在、『竹内孝功さんの自然菜園講座』オンライン動画サイト試験発信中~
本日、
 のち
のち 。
。
スクールの田んぼ

来年不耕起に切り替える田んぼ(自給用の田んぼ)


育苗ハウスに植えたイネ
昨日は、台風の雨の間を縫いながら、自然菜園スクールの自然稲作・発酵コースで、稲刈りを学びました。
私自身が20年前に無農薬稲作を学び始めたのも、非農家のサラリーマンの子供でしたが、自分たちで食べるお米は絶対自給したいという想いからです。
当時は、経験もなく、無農薬稲作も今ほど市場になく、有機・自然農の農家さんが自給プラスα程度のものや、大規模化の無農薬稲作の初期でした。
関東や九州、長野の稲作を見学して、作業を手伝って、10年後に田んぼをお借りしてお米が自給できるようになった時のことは今でもよく覚えております。
自然農の師匠、川口由一さんの「お米は面白い!」というお言葉も耳に残っております。

近隣の田んぼは、今年は特にイネが倒れてしまっている場所が多く、梅雨明け後の長雨が直接の原因のようです。
けれど、その原因の原因は、去年の長雨による刈り取りの際に、ぬかるんだ田んぼでの大型機械での収穫による悪影響に始まっているように思えます。
今までいろいろな田んぼを見学し、自分でもやってみてわかることは、
田んぼは去年の影響がとても大きく出やすい。もっと言えば、田植え~稲刈りまで5カ月程度で、むしろ稲刈り後~7カ月のイネがない間の影響(お世話)はとても大切だと思います。
ぬかるんだままの田んぼでは、冬の間にワラは分解されにくく、ワラが春から発酵しガスが湧きイネの根を必要に痛め、同時にコナギなどの大発生をもたらし、病虫害や草負け、減収の負のスパイラルが始まるとどんどん収量が悪く、草取りが大変な田んぼになっていく傾向が強いからです。
今回の勢力の強い台風18号で、直接の被害と、来年への負の遺産にならないか全国の農家さんは気が気でないはずです。

今回は、台風の影響の前日からの雨で、万全なタイミングではありませんでした。
無理に稲刈りすると、田を足で練ってしまい来年負のスパイラルに入りがちな傾向が強く、でも人が集まって稲刈りするのは、昨日と来週しかないという条件の中で、
もし自分の田んぼだったら、今日の稲刈りを断念するか、何を作業するのかを入念に考えて、3年後の田んぼが草もなく、イネも美味しく増収するようにするにはどうしたらいいのか、みんなで考えました。

イネの状態は、穂の実つきは上々で、平均120~130粒穂につき、健康そうで、穂の3分の1が枯れて、刈りどきでした。
そこで、今回は、手刈りする場所のみを行い、バインダーという刈り取り機を使う大部分の場所は、刈るのを明らめました。
人がいるときに、無暗に稲刈りすると、足がはまって大変なだけでなく、春まで乾かない負のスパイラルを避けるためでした。


稲刈りは段取りが大切で、当日稲刈りがすぐできるように、はざ木、はざ足、結束用のワラ、麻紐、機械の整備を当日までに行っておきます。


各地で、地域風土に合わせて「はざがけ」(天日干し)の方法は違いますが、うちでは、自然農の師匠、川口由一さんのやり方が基本にあり、誰でも習得できるように、毎年苦心しております。
扇のように結束した稲束を2対1に交互に「はざがけ」していきます。

実際の説明を聞いてもらってから、みんなで実習しながら、その方の癖などを観ながら、お一人ずつご指導させていただきます。
途中雨が強くなったので、


育苗ハウスの中の無農薬ブドウ狩り?ブドウを食べながら大雨を避け、休憩しました。
育苗ハウスは、とても立派なので、育苗だけに使うのはもったいないので、私は1年を通じて、いろいろなことに利用させていただいております。

ブドウ効果か、その後の稲刈りは雨もおさまり順調でした。
雨が降ってぬかるんだ田んぼでの昔ながらの工夫通称「北の屋方式」もご紹介させていただきました。



ぱっと見ると普通に見えますが、一つ目のワラと切り株の上にワラを重ねながらおいていくことで、ぬかるんだ田んぼでも穂が泥で汚れず、進行方向にどんどん並べて行きます。
あとは引き帰ってくるように、ワラを束ねながら戻ってくるので、田んぼの中で無駄な動きが少なく身体も楽で、お米もきれいに収穫できます。
昔のお百姓さんは、雨でも悪天候でも身体一つで毎日稲刈りしても大丈夫なような身体の無駄のない動かし方と創意工夫、卓越した技術を磨いてきたことを感じます。


今回は、近所で離農した農家さんから頂いたはざ足、はざ棒を使わせていただいたので、とても楽チンでした。

「はざがけ」は、最低3名の協力で進みます。
はざにかける人、渡す人、もってくる人といった感じです。




お昼は、稲刈りでとても楽しみな時間です。
今回は、去年のササニシキに、夏野菜とタカキビが入った合鴨カレーでした。
今年収穫した大量のキュウリも、九ちゃん漬けでカレーのお伴です。



午後は、午前中の続きと、写真はありませんが、小さな田んぼの鳥よけの糸やネットはずしをみんなで協力しながら行いました。
雨だったので、無理して稲刈りせずに、もう一枚の小さな田んぼの稲刈り準備をしたわけです。
うちでは2~3段にはざがけしていきます。
そして、薄く短いブルーシートが雨よけ兼ゆっくり乾燥に適しているので、みんなで協力して、その後訪れる台風の風速10m越えにも耐えるようにしっかり野良仕事いたしました。


稲刈りした田んぼの空き地(耕作していない)場所では、自然生えの稲が綺麗に育っております。
今年から田んぼを使わせていただくことになったので、去年まではコンバイン収穫の慣行の田んぼでした。
秋に田んぼを起こして(耕して)春に耕したところ、去年のワラについていたこぼれダネから勝手に育った稲たちです。
自然生えのイネは美しく、1粒が10本位に分けつし、風通し良く光も十分に当たる無駄のない立ち姿です。
稲本来の姿を垣間見たような気がして、今後の自然稲作の先生です。
来年から久々に不耕起栽培も始めますので、ますます自給用の自然稲作が楽しみです。
自給稲作にとって大切なのは、日常や他の本業と兼業できる自然稲作であるという点です。
1年に1回しかできないので、来年のために、今何をしておき、何をしない方がいいのか見極めながら、天気と稲と手伝ってくれる仲間がみんな喜ぶところで野良仕事をしたい限りです。
2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回10/4(水)
・秋野菜の収穫のポイント?/ダイコン、カブ、サツマイモなどの収穫
・秋の土づくり/堆肥の造りと施し方、緑肥作物の導入法
・越冬野菜の定植・種まきのコツ/タマネギ、キャベツ、エンドウ、ムギなど
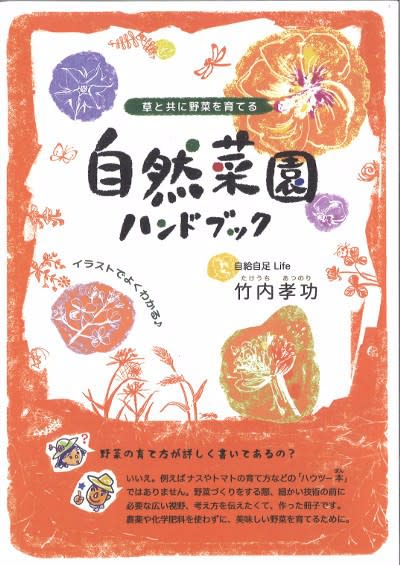
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中~





















