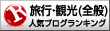2024年9月30日(月)
群馬県甘楽町小幡地区は、織田家ゆかりの小幡藩の城下町。町人が暮らしていた地区には明治に入って盛んになった養蚕農家群が雄川堰に沿って残り、桜並木がある。
小幡地区を流れる雄川堰。織田信長の次男「信雄(のぶかつ)」が初代藩主となり、その後8代152年間織田家が統治した。 雄川堰は、織田家統治時代に一級河川雄川より取水して造られた用水路。

雄川堰沿いをまっすぐに行くと桜並木があり、養蚕農家が連なる。桜の季節でないので残念だが、桜の木の根元に彼岸花が咲いていた。

雄川堰は名水百選にも選ばれている。


屋根の上に小さな屋根(越屋根)があるのが養蚕農家の特徴。蚕のために換気機能がある。



レンガ造りの建物は、蚕の繭倉庫(現在は歴史民俗資料館)であり、それより先に行くと武士が暮らしていた武家屋敷エリア。桜並木もここまで。雄川堰もここから東(写真左方面)へ曲がる。

武家屋敷群に行くため、東へ曲がる雄川堰に行かずまっすぐ行く。

武家屋敷群。白壁の塀や石垣が結構長く続く。