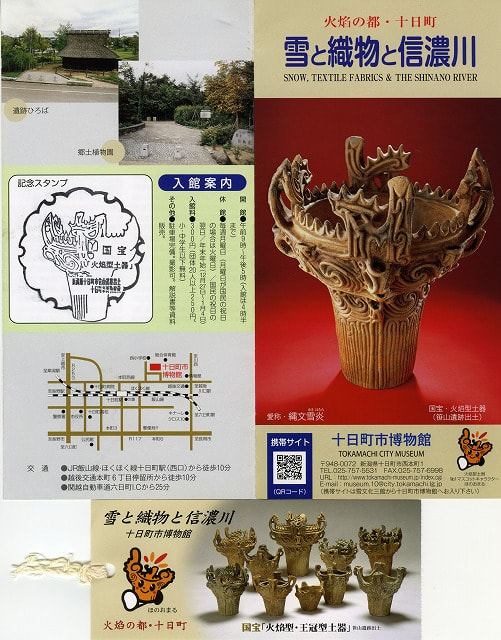「フラグシップ」という言葉があります。
本来の意味は軍事用語の「旗艦(指揮官が乗って軍事行動の指揮を行う軍艦)」ですが、その意味から転じて企業の商品の中で最上級的な商品を指すような使われ方もしています。
当然、カメラにも「フラグシップ」と呼ばれる機種があります。
そのカメラメーカーが発売している最上級カメラ、端的に言えばプロのカメラマンが使うような機種です。
もちろんプロだけが使うわけではなくて、懐さえ何とかなれば誰でも購入して使うことができます。
本当かどうかは分かりませんが、フラグシップカメラの上得意はプロよりもアマチュアのカメラマンだと聞いたことがあります。
まあ、それだけアマチュアのカメラマンにとっては憧れのカメラです。
ただし、このフラグシップカメラを所有する場合、ちょっとした不文律があるように感じます。
フラグシップカメラがレンズを交換可能な機種(いわゆる一眼レフカメラ)の場合、カメラに組み合わせるレンズは、そのカメラメーカーが発売している最上級のレンズ、いわゆるフラグシップレンズにすべしという不文律です。
まあ、最低でもカメラメーカが販売してる、純正レンズを装着していないと、格好がつかないようです。
先日、とあるところで撮影をしていたら複数の同業者に声をかけられました。
一人の方はフラグシップカメラを首から下げていました、しかもフィルムタイプのカメラでした。
販売されているフィルムの種類がどんどんと削られている上に、フィルム自体の価格や現像代が上昇しているご時世ですから、フィルムカメラを使っている事自体が尊敬に値します。
そのような場合、どうしてもレンズにも目が行ってしまいます。
私は、そのレンズが純正ではないこと、しかもどこのレンズメーカーであるかが分かりました。
理由は、以前中古のフィルムカメラを購入した際に、同様のレンズがついていたからです。
カメラは趣味の世界ですから、フラグシップカメラを使っているからと言って、絶対に純正レンズを使う必要はありません。
実は、カールツァイスブランドで主要カメラメーカー向けにに販売されているレンズは、純正レンズよりも高価です。
完璧に純正神話が刷り込まれた状態の自分自身が、いささか恥ずかしくなりました。
どうしても、男は道具に目が行ってしまう人種のようです。
写真は、新発田市剣龍峡で撮影しました。
一番上の写真、太陽を画面に入れたので、完璧にフレアなどが発生しちゃいました。
下の一枚目も、フレア気味です。
最近のレンズは、こんな状況でもフレアなどが発生しづらいようになっています。
やはり、道具に目が行ってしまいます。