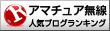過去、日本では車道から自転車を排除したくて歩道を走らせてきました。
最近は、自転車を歩道から締め出す方向に変わりました。
自転車は免許も要らないから歩行者に毛が生えたもん、みたいな感覚で乗ってますが、れっきとした軽車両。つまり車両、車の仲間なんです。大型トラックトレーラーと同じ車両ジャンルです。
電動アシストの子乗せ3人乗りなんて、パワーもあり総重量はバイク同等で、人にぶつかったら大事故になります。
これが幼児も歩く歩道をガンガン飛ばしていくのですからそりゃ危ない。
今、自転車は、
車道の左端が原則で歩道は例外
とされています。
例外は、
13才以下65才以上の人なら歩道を走れます。
でなくても、自転車歩道通行可とされている歩道は走れます。
実は今、歩道走行可の標識がいつの間にか無くなって来ているの、ご存じですか。気をつけましょう。
(例の特定小型原付の特例モードが歩道ならどこでも走るのを阻止する動きでもあります。)
もうひとつ、車道を走ることが危険な場合、と言うのがあります。
これ、自分が怖いと思えばそうなのでしょうが、人によって解釈が変わる半端な決まりです。警官が危険だと思わなければ違反に問われる可能性があります。
で、共通していることは、もし歩道を走るにしても、そこは歩行者の聖域である、と言うこと。
歩行者が居たら飛ばしてはいけない(徐行、つまり直ちに止まれる速度)。歩行者のために止まらなければいけない。ベルを鳴らして蹴散らすなんてもってのほか。
安全運転意識、歩行者への思いやりがあれば当然の運転ですが、悪く言えば肩身狭い思いで走らなければならない、と言うことです。
車道の左もなんか肩身狭いし、安全でいいなと思った歩道も肩身狭い。
これが自転車の乗り方です。
車道は自転車が走りやすく作ってこなかったので、自転車は走りにくく、車から見ても邪魔でしかありません。
道路を何とかしないで決まりだけ変えてきた感はぬぐえませんね。
あとは自転車の乗り手と、車のドライバーの意識改革にかかっています。
自転車は車両なんだ。
車両として交通ルールを守ろう。
堂々と車道の左を走ろう。
車の人は、自転車も車両として車道を走る仲間なんだ、と認識しよう。
自転車の悪いところ(良いところか?)は、車両、歩行者を自分の都合で身勝手に使い分けること。
これ、ひどいヤツ居ますよね~。
赤信号なのに、青の横断歩道渡って歩道走ってまた横断歩道渡って信号の先に出て赤信号クリアしていくヤツとか。
あれ、厳密に言うと信号無視しています。
狭い道では右側通行していたり、右側通行のまま見通しの悪い交差点を止まらずに右折する。これ、ホント危ない。
路側帯の中は歩道だと思って右側通行しても良いと思っているバカも多い。あなた車両だからそれはダメよ。降りて押して歩いているならアリだけど。
実は自転車の左側通行の徹底だけで、交通事故はかなり減るんだそうです。
金沢市は取り組みの成果が出ているとか。
来年かな?青切符切られるようになるのですが、警官が増えるわけではないので時折見せしめの一斉取り締まりがある程度でしょう。
おそらくスマホ見ながらとか、イヤホンつけてる人を待ち伏せして取り締まるくらいか。自転車を追いかけてまで捕まえる能力は今の警察にはありません。白バイが歩道走って自転車を追いかける、なんてやりませんからね。
撮影しまくって違反常習者を待ち伏せする、ならできそうですが。
交通ルールを学校教育でしっかり教えないとダメですね。必修単位として。
ママさん達がルール守らないから子も守らなくなるんだよね~。