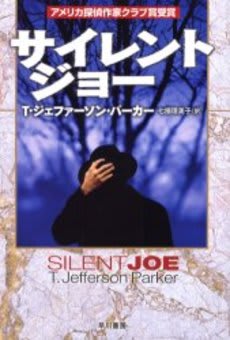
つい読んでしまった、アメリカのハードボイルドミステリ小説。手持ちの本を読んでしまい、飛び込んだ古本屋の特価コーナーでつかんだ。ババではなかった。読み出したら、止まらない上出来本だった。
『サイレント・ジョー』(T・ジェファーソン・パーカー 早川書房)
舞台は南カリフォルニア、メキシコからの不法移民がコミュニテイをつくっているオレンジ郡。赤ん坊のときに、実父に硫酸をかけられ、母親の育児放棄から施設に預けられたジョーは、郡政委員の養父に引き取られ、24歳の新米保安官補となり、州立刑務所に看守として勤務している。勤務が終わった後は、養父のボディガード兼政治の裏工作にも携わっている。
そんなある夜、養父が銃撃に倒れ、守れなかったジョーは自責に打ちのめされるが、深い悲しみを胸に犯人を追いはじめる。 州の政治を牛耳る強欲な富豪や権力欲と私腹を肥やす役人、絶大な人気を博すTV伝道師などがめぐらす策略と罠。貧しいメキシコ移民たちと下手人と目されるベトナム系のギャング団のつながり。やがて、偉大だったはずの養父の意外な顔がジョーを困惑させる・・・。
とまあ、よくある勧善懲悪の「西部劇」の焼き直しなのだが、だからこそ、西部劇映画とウェスタン小説の美学を踏まえて、泣かせる場面がいくつかある。その白眉がこれ。
わたしはひどく疑り深くずいぶん臆病な五歳の子供で、本に夢中だった。いや、夢中という言葉では正確に言い表わしたことにならない。本を読んでいるときは下を向いているから誰もわたしの顔の悪いほうの半分を見ることはできない。皮膚と筋肉がおぞましく痛々しいどろどろした赤いかたまりになっているのを誰にも見られることはない。普段はその顔で世界と向きあわねばならなかった。
だが、顔を見られないようにしていればそんなことは忘れることができた。心の中で自由に時間と空間を行き来することができた。ヒルヴュー・ホームから何千マイルも離れたところへ、二百年前のアメリカの平原へ行くことができ、シャグというすばらしい野性の生き物がグリズリーと戦い、狩りをする人間たちの矢を受け、生き残ったわずかな仲間たちとともにイエロ-ストーンへ逃げ込むさまを見ることができた。
あのときもわたしはシャグとともにイエローストーンにいた。
だから、誰かが図書室に入ってきて向かいの小さなテーブルに腰をおろしたときもまったく注意を払わなかった。シャグと一緒にいたからだ。その男は-足音とコロンのにおいから男だということはわかっていた-テーブルをこつこつと指でたたいた。それでもわたしはシャグと走り続けた。
「ぼうや」彼はようやく口を開いた。「こちらを見なさい、きみを見ている者がここにいるんだから」
言われたとおりに顔を上げた。そこにはこれまで見た中で最も思慮深く思いやりにみちた顔があった。悲しみとユーモアを漂わせたとてもハンサムな顔だった。そんなことはそれまで一度も考えたことがなかったにもかかわらず、その男を見たときに男とはどうあるべきかわかった。彼だ。それはシャグにとってイエローストーンに逃げ込まなければならないのと同じくらいわたしにとって明らかなことだった。
「そいつはただの傷痕だ。誰だって持っている。きみのは外にあるというだけのことだ」 もちろん、そう言われたときにはすでに顔をそむけていた。だが、何とか勇気を振り絞ってささやくような声で答えた。「シャグもクマと戦ったときの傷が脇腹にあるんだ」
「ほらね? 全然恥じるようなことじゃないんだよ」
いったい何がわたしに次のセリフを言わせるような途方もない勇気を与えてくれたのか今でもわからない。とにかくわたしはこう言った。「あなたのはどこにあるの?」
「きみがもう一度わたしを見てくれたら答えよう」
わたしはそうした。
彼は拳(こぶし)で軽く自分の胸をたたいた。「わたしはウィル・トロナというんだ」 そう言って立ち上がると部屋を出ていった。
(p163~)
養父ウィル・トロナと後の養子ジョー・トロナがはじめて会う場面だ。
「だが、何とか勇気を振り絞ってささやくような声で答えた。」とこれは日本の小説でもあり得ない場面ではない。殻に閉じこもる子どもが、かたくなな心を開いて他者を受け入れる場面として。しかし、日本の小説なら、そのすぐ後のような展開にはきっとならない。「いったい何がわたしに次のセリフを言わせるような途方もない勇気を与えてくれたのか今でもわからない。とにかくわたしはこう言った。」とこれはまっすぐに、父子間の勇気の契りの場面になるのだ。こんな勇気を語る場面は、日本の小説ではちょっとない。日本で「泣かせる」場面となると、どうしても母子間の情愛に訴えるものになりがちだ。
この場合の「勇気」とは「傷痕」をめぐる男と男の対話として示されるのだが、実は父にとって息子こそ自らの傷痕そのものであったことが、最後の最後にわかる。父と子は、男と男は、情愛によってではなく、むしろ傷痕によって深く結ばれている。傷つけ、傷つけられる行為がなされた後に、はじめてお互いをつなぐ絆に気がつく。愚行や過誤の末に、大切なものを失う代わりに、醜い傷痕を得るという連鎖。それを断ち切る「勇気」の物語であることが明らかにされる。
ようするに、どうしようもない父親と健気な息子の話なのだが、アメリカの小説や映画では、それでも息子はどうしようもなく父親を愛している場合が多い。アメリカ人にはご先祖というものはなく、建国した移民者が初代の父親であり、それから後は「アメリカの息子」が続くだけなので、こんな近親憎悪と紙一重の父子の物語ができるのだろうか。
また、郡政委員ウィルと保安官補ジョーを通して、アメリカの政治の原点が、西部劇時代に保安官が活躍するような「スモールタウン」にあることがよくわかる。さしあたり中央集権以外に記憶がない日本からみると、勇気と暴力が一体になったアメリカの正義や友愛には、違和感があるが、アメリカ人が勇気という言葉に弱いということだけはよくわかった。アメリカ人が心動されるキーワードは、どうも勇気らしい。「勇気ある撤退」とか「わが国は勇気を示す用意がある」とか、勇気をまぶした文言を使うなど、そこいらへんを日本も外交的な戦術に加えると、日米関係も少しは噛み合うような気がする。



















