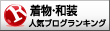先週読んだ原田マハの「リーチ先生」、些か気になる所があって
実際にバーナード・リーチの日本での心情はどんなだったのかとの思いから、
「バーナード・リーチ日本絵日記」を読んでみました。
昭和28年、19年ぶりに日本を訪れた彼の日本滞在記。
原文は英語で書かれ、翻訳は柳宗悦です。
2年足らずの間に日本各地を訪れて講演、陶作活動を積極的に行い、
柳宗悦、濱田庄司、棟方志功、志賀直哉、鈴木大拙らと交遊を重ねた様子が子細に書かれています。
戦後日本の文化の混乱への、手厳しい批判も随所にあります。
街中に溢れる低級な音楽、無秩序なネオンや広告、まがいものの西洋建築。
”こんな山村でさえ、日本の婦人がみんな洋服を着て、まっすぐな黒髪にパーマをかけ、一日中働きながら、日本式ジャズという外国音楽に耳を傾けるとは、いったいどういうことなのか?
確かに奥床しい日本らしさの感情が失われて、日本自体の魂、生まれながらの権利が無視され、方向が変えられてしまったのだ”
”すべてがめちゃめちゃであべこべであり、本当の日本の「内面」などは全然ないーちょうど、まがい物の漆器に観られる陳腐な日本的意匠の、最も薄っぺらな虚飾そっくりだ”
という具合。
でも全体的には、日本文化への尊敬と愛情、藝術仲間への友人との友情、
自分を温かく迎えてくれる日本人への感謝の気持ちで溢れていました。
一番驚いたのは、
「リーチ先生」で架空の存在だと思っていた「亀之助」が出てきたこと。
”今日はまた思いがけないことに亀ちゃん(森亀之助)の従妹が私を訪ねてくれた。彼女が語る所によると、私たちは40年前に彼女の家を訪ねたことがあるという。彼女はまた亀ちゃんが肺病で彼の父親の家で息を引き取ったことを話してくれた。
気の毒な亀ちゃん!君の人生の目的はなんだったのだろう。
かつて君がまだ十三歳の頃、私のエッチング画の載っている新聞を片手に握りしめ、ぜひ私の弟子か下働きにしてくれと頼みにやって来なかったら、君の一生はもっと幸福だったのではなかろうか。
彼はいつも「そうじゃない」と言っていた。
あの頃私にもっと洞察力と将来への見通しがあったら、一文無しの子供が外国人のもとで藝術の修業をするということは、彼の将来をただ困難にするだけだということがきっと分かったに違いない。しかし、それに気が付いたのはその後二、三年してからで、時すでに遅かったのだ。
私は当時、その結果が早発性痴呆症やこのような孤独や失敗をもたらそうとは夢にも考えなかった。
亀ちゃんは藝術を愛し、ウィリアム・ブレークやセザンヌやゴッホを愛した。
そして、精神病院に引き取られる前には、うまい絵を何枚か描いた。
可哀想な亀ちゃん!”
亀之助が出て来るのはここだけ。
他には何の説明もありません。
この本の終りの方に、金沢の美術学校長である森田亀之助が筆者のもとを訪れ、二人の若い頃の思い出を語りに語ったとありますが、それはまた、全く別人であるようです。
原田マハは上の文章から触発されて「リーチ先生」に出て来る亀之助を生み出したのかしら?
謎です。
バーナード・リーチ日本絵日記