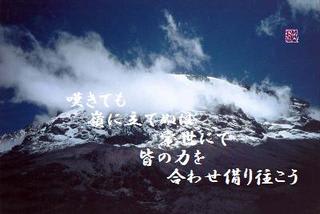嘆きても 嶺に立てぬは 常世にて 皆の力を 合わせ借り往こう
■
【どこまで突破できるかバイオサイエンス】
加藤純一広島大教授の基礎研究によれば、石油化
学プロセスの反応の(1)酸化還元反応と(2)
重合反応のうち、バイオプロセスの応用展開でき
るのは(1)の酸化還元反応であるという。石油
は極めて優れた原料だが、問題は石油を原料や化
学反応の条件(例えば高温・高圧条件)を整える
ために多量消費している。これを、バイオプロセ
ス転換できれば、大きな運転コスト削減が可能に
なると期待される。
いくつかの石油化学産業では、脱石油化を図り、
バイオマス(糖質)からの疎水性ケミカル生産を
手掛けている。また、生化学反応は反応特異性に
優れていて、合成化学的には生成が困難な疎水性
ケミカルの生産が可能になり、新規な疎水性ケミ
カルを原料として新たな機能を有する製品を開発
することも期待されている。一方、発酵産業は「
疎水性の世界」への進出ととらえられる。これま
で、アミノ酸、有機酸、アルコールなど親水性の
ケミカルの生産で大きな成功を収めてきたが、も
う一方の「疎水性の世界」では成果は上がってい
るとは言えず、広大な領域が発酵生産の進出が期
待されている。 ベンゼン酸化細菌
ベンゼン酸化細菌
生物による酸化還元反応では、反応の進行に還元
力の供給が必要で、さらに酵素の安定性を勘案す
ると、疎水系での酸化還元反応は精製酵素よりも
菌体そのものを生体触媒として用いるのが有利で、
原料は石油炭化水素およびそれ由来の疎水性物質
であるので、反応は水相(培地もしくは緩衝液)
に原料及びその有機溶媒を重層する二相反応系が
想定される。
図 二相反応系バイオリアクターによる
非水系バイオプロダクション
このプロセス開発の中核である「耐有機溶媒性の
細菌」のベンゼン酸化細菌やトルエン酸化細菌の
培養し、これを遺伝子組換え技術に成功。これを
使い、トルエン→o-クレゾールの水酸化反応に成
功する。これはほんの1例でモデル反応系である
が、非水系でのバイオ酸化プロセスの可能性を探
るものである。今後は、実際的な反応系をターゲ
ットに開発研究を進めて行きたいと、加藤純一は
貴重な基礎・応用研究の一歩を進めてこう結ぶ(
『有機溶媒耐性細菌を利用した疎水性ケミカル生
産技術の開発』,バイオサイエンスとインダストリ
ー Vol.68 No1)。
※特許:P2005-58048
「プラスミド、形質転換体およびその製造方法、
フェノールの製造方法」
■
イサザ(魦、鱊、学名 Gymnogobius isaza )は、ス
ズキ目ハゼ科に分類される魚の一種。ウキゴリに
似た琵琶湖固有種のハゼで、昼夜で大きな日周運
動を行う。食用に漁獲もされている。現地ではイ
サダとも呼ばれる。琵琶湖沿岸以外での「イサザ」
「イサダ」は、シロウオやイサザアミなど本種以
外の動物を指す。成魚の全長は5~8cmほど。頭が
上から押しつぶされたように平たく、口は目の後
ろまで裂ける。体は半透明の黄褐色で、体側に不
明瞭な黒褐色斑点が並ぶ。第一背鰭後半部に黒点
がある。同属種のウキゴリ G. urotaenia に似るが、
小型であること、体側の斑点が不明瞭なこと、尾
柄が長いことなどで区別される。
琵琶湖の固有種で、北湖に産する。琵琶湖にはウ
キゴリも生息しており、イサザはウキゴリから種
分化が進んだものと考えられている。成魚は昼間
には沖合いの水深30m 以深に生息するが、夜には
表層まで浮上して餌を摂る。琵琶湖の環境に適応
し、ハゼにしては遊泳力が発達しているのが特徴
である。食性は肉食性で、ユスリカ幼虫などの水
生昆虫やプランクトンを捕食する。
![]()
産卵期は4~5月で、成魚は3月になると沖合いから
沿岸に寄せてくる。この季節はまだ水温が低いた
め他の魚類の活動が鈍く、卵や稚魚が捕食されな
いうちに繁殖を終わらせる生存戦略と考えられて
いる。オスは岸近くの石の下に産卵室を作り、メ
スを誘って産卵させる。メスは産卵室の天井に産
卵し、産卵・受精後はオスが巣に残って卵を保護
する。卵は1週間で孵化し、仔魚はすぐに沖合いへ
出る。
北陸地方でシロウオをイサザとよぶが、標準和名のイサザは、
ハゼ科に属する琵琶湖固有種のことを指します。
しばらくは浮遊生活を送るが7月頃から底生生活に
入り、成長に従って深場へ移る。秋までに全長4.5
cmに達したものは翌年の春に繁殖するが、それに
達しなかったものは次の年に繁殖する。寿命は1年
か2年で、繁殖後はオスメスとも死んでしまう。琵
琶湖周辺地域では食用になり、12~4月に底引き網
や魞(えり:定置網)で漁獲される。佃煮・大豆と
の煮付け・すき焼きなどで食べられる。
ブルーギルやオオクチバス(ブラックバス)によ
る捕食が影響し個体数は減少。漁獲量は変動が大
きい。1950年代に一旦激減した後、1962~86 年に
は160~590tまで回復したが、1988年以降に再び漁
獲が激減、1993~95年には 1t 以下にまで落ち込ん
だ。その後再び漁獲されるようになったが以前ほ
ど漁獲されていない。 琵琶湖の美味しい湖魚料理あれこ
琵琶湖の美味しい湖魚料理あれこ
イサザの料理は、イサザ豆、佃煮(甘露煮)、す
き焼き(じゅんじゅん)卵とじで量も少ないので
口にすることも少なくなったが、色白と言うより
も透明で、内臓が飴色に透けて見え、踊り食いは
鉢入れのイサザを小網ですくい、ポン酢と卵の入
った器に移し、タレごとツルツルと呑み込む。ピ
チピチとはねながら、口から喉を通過してゆくの
がたまらないらしい?プチプチとした歯応えがあ
り、ほのかな甘さが広がるという。イサザを吸い
物にすると、味が淡白なので卵とじや唐揚げが、
お勧めだが、醗酵食品には向かない。さて、新年
会だ。
■