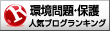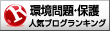尾花地区を抜け、再び林道にでてきたものの、地図を持っていないのでどちらの方向に行けば分かりません。とりあえず直感で下り方面を選択し、相当長い間歩きました。正直に言って、いったいどこに出るのかも分かりませんでしたが、とりあえず山を抜けて町に出たらどうするか考えようということで、構わずどんどん歩き続けました。
やがて四王寺川(これも当然後になってわかったことですが)に突き当たり、川のせせらぎに耳を傾けながら歩いていくと、突然百間石垣に辿り着きました。これはぜひ見て帰りたかったので、見つけたときは非常に嬉しかったです。

こんな図を見ると、太宰府駅からスーツと革靴でどれだけ歩いてきたのか自分でも嫌になってしまいます(クリックすると拡大します)。しかし、この時はまだこれから宇美まで延々歩くことになるとは知る由もありませんでした。

さて大野城は四王寺山の尾根に沿って土塁を巡らし山城としたわけですが、四王寺山は起伏が激しいために谷間はどうしても弱点になってしまいます。そこで谷間は土塁ではなくより堅固な石塁としました。この百間石垣は四王寺側に沿った部分を石塁とし、それに続く山腹部の石垣がちょうど百間(約180m)ほどであることから名付けられたものです。この四王寺川からは礎石も発見されており、この辺りに城門もあったのではないかと考えられています。

百間石垣は平成15年7月の集中豪雨で甚大な被害を受けましたが、現在ではここまで復旧しています。繰り返しになりますが、7世紀に築かれた石塁がこれほどの規模で残っているとは本当に驚きです。この時代に北九州から瀬戸内海沿岸にかけて築かれたいくつかの古代山城以降、僕の知る限り日本で築かれた大規模な石塁には13世紀末の元寇防塁がありますが、それらは今では崩れ去ってほとんど残っていません。その後になりますと、沖縄を除けばこの規模かつこの技術水準の石塁は近世、16世紀まで待たなければならないでしょう。
この百間石垣をもって、僕の大野城見物は終わりました。Face Bookにチェックインした履歴によれば、宇美駅に着いたのは、太宰府口城門を出てから1時間後のことです。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
 ブログをご覧いただいたすべての皆様に感謝を込めて。
よろしければクリックおねがいします!
ブログをご覧いただいたすべての皆様に感謝を込めて。
よろしければクリックおねがいします!
↓