
2月22日、日本交渉協会主催の第16回ネゴシエーション研究フォーラムに参加してきました。
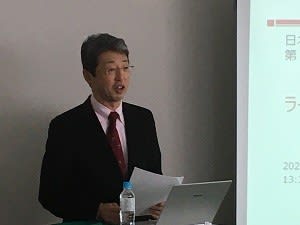
今回は、日本交渉学会副会長であり、一橋大学法科大学院特任教授、そして国際弁護士の射手矢好雄様より「ライシャワー博士の思い出と交渉の極意」と題してお話しいただきました。ライシャワー博士とは、故エドウィン・O・ライシャワー元駐日大使(1910‐1990)のことです。ライシャワー博士は占領時代の色が濃く残る1961年に駐日大使として赴任。「イコール・パートナーシップ(対等な日米関係)」を掲げ、日米関係の改善と強化に尽力されました。1972年の沖縄返還も博士の努力が大きく影響したと言われています。
日本交渉学会も日本交渉協会も共に日本における交渉学のパイオニアである藤田忠先生が設立された団体であり、ライシャワー博士を交渉のロールモデルとしている点では同じです。射手矢先生は、ライシャワー博士と親交のあった、今や数少ない日本人のお一人であり、貴重なお話を伺うことができました。
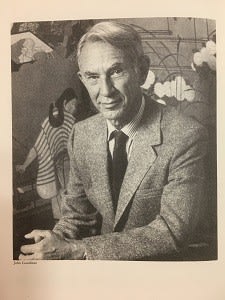
エドウィン・O・ライシャワー博士(『ライシャワー自伝』(文藝春秋)より)
先生とライシャワー博士との出会いは1986年。奥様のお父様が博士と京都帝国大学時代に親交があり、ハーバード・ロースクールの推薦状をもらうために博士宅を訪問されたのが始まりだそうです。博士は4年後の1990年に逝去されていますので、晩年の頃の出会いだったと言えます。博士が亡くなられた後も、お子さんたちとは現在も親交が続いているそうです。また、翌1987年には、後にハル・ライシャワー(松方春)夫人が「生涯最高の時」と述懐されたという、皇太子ご夫妻(現在の上皇・上皇后様)のライシャワー博士宅のご訪問のお手伝いもされ、その時の写真やエピソードも交えてお話しいただきました。
射手矢先生によるライシャワー博士の人柄は、一言で言うと「凛として優しい」。先生が博士から学んだ一番のことは、「人生の質、相互理解が大事、常に複数の次元で考えよ」の3点。これを博士は事あるごとに繰り返しおっしゃっていたそうです。
前述のように、学会と協会がロールモデルとするライシャワー博士ですが、博士ご自身は歴史学者であり交渉の専門家ではありません(ハングル文字のローマ字表記は博士が考案したと『ライシャワー自伝』で読んだ記憶があります)。しかし、博士は「世界は本当に一つになってきています。こうした世界では、私達はお互いに交渉で課題を解決する豊かな技術を育てなければなりません」と述べておられ、交渉を重視されていたことが分かります。そのことは亡くなる前年に札幌で行われた第2回日本交渉学会における基調講演でも表れています。以下は、射手矢先生が挙げられた講演の重要なポイントです。
1. 交渉の重要性
先の言葉に加え博士は、「交渉はかつてのようにゼロサムゲームではない。我々は協力することで利益を得ることができるのである」と述べておられます。
2.イコール・パートナーシップ
「有効なパートナーシップは、お互いの建設的交渉を通じてのみ達成され得る」
イコール・パートナーシップは世界平和、環境問題、貿易摩擦、第三世界の問題等、あらゆる分野の交渉においても重要だとおっしゃっています。
3.交渉スキルを高めるための主要な分野
①コミュニケーション力、語学を磨くことである。
②しかし、それよりも重要なのは、互いを知り、理解することである。
③ゼロサムではない、新たな交渉姿勢。我々は互いに歩み寄り、ある程度折れることで、お互いの理解と心の通い合いに至ることが可能となる。交渉を成功させるために必要なあらゆる物事の中で最も重要なのは、(ゼロサムから脱却するという)根本的な姿勢の変化である。
確かに、『ライシャワー自伝』を読んでも、日米間の表面的な諸問題に対処するためであっても、博士はその背後にある当事者の思想、文化、メンタルモデルにまで踏み込んで理解しようとしていたことが分かります。

まとめると、ライシャワー流交渉術とは以下の3点であると射手矢先生はおっしゃっていました。
1.互いの利益を高める
2.相互理解が重要
3.協力して発展の方法を探り、イコール・パートナーシップを築く
ここには、後に実践的な交渉研究の嚆矢となり、一世を風靡したロジャー・フィッシャー、ウィリアム・ユーリー、ブルース・パットンによる『ハーバード流交渉術』の原型が見られます。前述のように、ライシャワー博士は駐日米大使として来日した1961年には既に「イコール・パートナーシップ」を標榜されていましたから、『ハーバード流~』に先立つこと少なくとも20年ということになります。
さて、フィッシャー、ユーリーらによって提唱された、交渉プロセスを評価するフレームワークに「交渉の7要素」があります。これは交渉の準備段階で非常に有用なものです。

交渉の7要素(上図をクリックすると拡大します)
引用:R. フィッシャー、 D. シャピロ著 『新ハーバード流交渉術 論理と感情をどう生かすか』(講談社)
これら7つの要素を「自分」と「相手」についてそれぞれ評価します。同じハーバード大学のJ.セベニウスは、特に「利益」、「オプション」、「BATNA」の3要素は必ず評価せよと述べています(注)。
注:セベニウスはこの3要素に「交渉相手」を加えています(参考:『最新ハーバード流 3D交渉術』)。フィッシャーらの交渉の7要素においては「交渉相手」は所与と思われます。

交渉の7つの鍵(上図をクリックすると拡大します)
引用:第16回ネゴシエーション研究フォーラム配布資料
上図は、射手矢先生がハーバード大学で学んだロバート・C・ボルドーネの”Circle of Values”をベースに先の交渉の7要素を編成しなおしたものです。先生は、この図をぜひ名刺大にコピーして持ち歩き、身に着くまで繰り返し確認すると効果的だとおっしゃっていました。先生の経験から、これは米国人や中国人相手の交渉でも役立つそうです。交渉は理論と実務の両輪を回すことが大事だとおっしゃっていました。なお、さらにお知りになりたい方は、この図の出典である『うまくいく人はいつも交渉上手』をご覧ください。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした


























