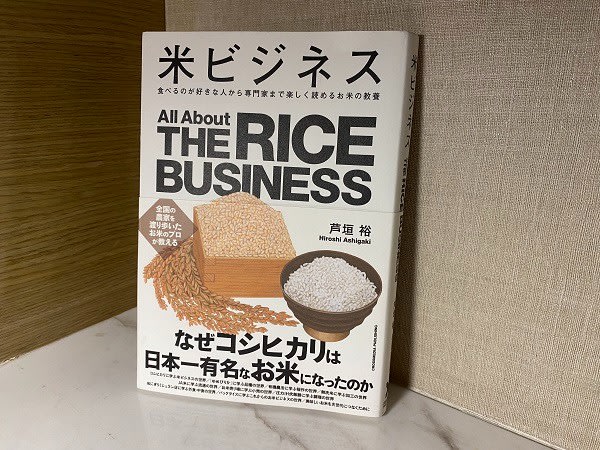
海外出張中に、奥歯が欠けていることに気づいた窪田です。帰国したらまた歯医者さんのお世話にならなければなりません。
さて、行きの機内で芦垣裕さんの『米ビジネス』を読みました。アメリカのビジネスではなく、文字通りお米(ご飯)の話です。読み終わっての感想ですが、日本人の主食といわれ、これほどまでに身近な存在にもかかわらず、ほんのちょっとしたことさえ全く知らなかったのだなという、自身の無知を再認識させられました。
本書は、僕のような素人でも楽しく読めるように書かれ、まるでお米の博物館を見学しているような気にさせられる、お米に関する豆知識、生活に役立つヒントの宝庫です。まず開くと、小さな字がびっしり。予想以上の充実した内容に驚きました。
1章:米ビジネスの概要
2章:品種について
3章:稲作について
4章:加工について
5章:流通について
6章:小売について
7章:炊き方について
8章:外食とお弁当について
9章:お米のこれからについて
個人的な見解ですが、大まかに見て、お米は米単体として食べることを前提に「美味しいご飯」を追求した縦方向の発展と、加工の多様化といった横方向の展開があったように思います。前者の美味しいご飯の追求は、淡白な穀物であるお米の繊細な味や香りに深く拘る。それと付随して、美味しく炊けるお釜の開発も繊細な方向に深まっていく。結果として、そうしたことが日本の米食文化の特徴となっていくわけですが、そういう姿勢はこれからも失わないで欲しいなと思います。例えば、カレーライスのためのお米のブレンドとか、まったく驚きました。
本書を通じて初めて知ったことですが、それぞれの品種に大まかな特徴がありつつも、気候、土壌、水、肥料、育て方などによって、違った味わいのお米になってしまう。安定した品質を出すためにお米をブレンドすることもあれば、1農家で個性的なお米を生産することもある。品種によって、合うおかずも異なる。これらのような特徴は、まるでワインやウィスキーのようであり、お茶碗に盛られた、見慣れた白いご飯に、それほどまでの繊細さ、奥深さがあろうとは本当に思いもよらぬことでした。こうしたことを知ると、これからのご飯の見え方が変わってきますし、本書がくれるちょっとしたヒントを頼りに、日々の食事がもっと楽しくなっていくと思います。
現在、東南アジアにいますが、ここにはまた日本と異なるお米の文化があります。芦垣さんの本を読んだことで、異国のお米文化についても相対的に見えるようになると思いますし、それもまた楽しみです。

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした



















