都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「オンラインミュージアム」で楽しむ國學院大學博物館
臨時休館中の國學院大學博物館が、常設展や企画展をWEBで楽しめる「オンラインミュージアム」を公開しています。
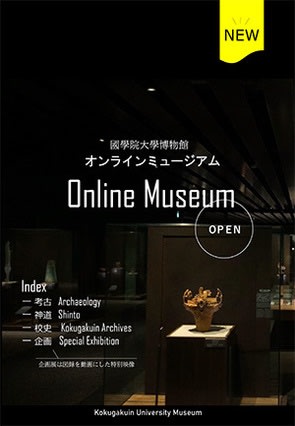
オンラインミュージアムOPEN
http://museum.kokugakuin.ac.jp/event/detail/online_museum
まず先行してアップされたのが常設展示の「考古ゾーン」で、現在、「先史時代の造形-縄文・弥生-」、「国家形成と神道-古墳・古代-」、「日本宗教の原型-古代・中世-」の3つの動画をyoutubeを通して見ることが出来ました。
このオンラインミュージアムで充実しているのは、単に展示風景を配信するのではなく、同博物館の准教授で考古学が専門の深澤太郎さんが資料を前に解説していることでした。例えば先史時代ではまず火炎型土器を取り上げていて、土器の内部のアップを交えつつ、用途などについて触れていました。
さらに土偶の変遷では「かたち」に着目していて、手や足がもげてバラバラになった資料の存在から、宗教的な儀式が行われていた可能性があることなどを知ることが出来ました。ともかく聞きやすく、分かりやすい内容で、あたかもオンラインで講義を受けているかのようでした。また日本語字幕が付いているのも、内容の理解を深めるのに有用かもしれません。
続く「国家形成と神道」で興味深いのは、古墳時代の埴輪の原型は、一般的に知られた動物や人物の埴輪ではなく、飲食物を象徴する壺型の土器にあるということでした。また被葬者に捧げる飲食物から埴輪は成立したことから、埴輪に表現された動物や人物も被葬者の財産を象徴していたと考えられるそうです。
3本目の「日本宗教の原型」では、仏教の受容に伴う火葬の導入について言及していて、それまでの古墳時代の死体を保存するあり方から、大きく葬送観念が変化したことを理解出来ました。また中世の和鏡に刻まれた男神像の精緻な画像も見どころではないでしょうか。そもそも古来の日本の在来の神は姿を顕すことをしなかったものの、仏像の影響を受け、8世紀頃には神像が作られるようになったとのことでした。
以降、「神道ゾーン」、「校史ゾーン」も順次公開されるそうです。そちらも楽しみにしたいと思います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、長らく臨時休館していた國學院大學博物館ですが、7月2日より再開することが決まりました。しばらくは常設展の観覧、及びミュージアムショップのみ利用することが出来ます。そして当面は木曜、金曜、土曜のみ開館し、日曜から水曜日は休館します。また開館時間も12時より16時までと大幅に短縮されます。
次回企画展「モノで読む古事記」は7月16日より開催され、展示もオンラインで配信される予定だそうです。まずはyoutubeに公開された予告編を楽しむのが良いかもしれません。
「モノで読む古事記」 國學院大學博物館(@Kokugakuin_Muse)
会期:2020年7月16日(木)~9月26日(土)
休館:毎週日・月・火・水曜日。8月9日(日)~26日(水)。
時間:12:00~16:00
*入館は閉館の30分前まで。
*短縮開館を実施。
料金:無料。
住所:渋谷区東4-10-28 國學院大學渋谷キャンパス 学術メディアセンター 地下1階
交通:JR線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線渋谷駅より徒歩15分。渋谷駅東口バスターミナル54番乗り場より都営バス「学03日赤医療センター行き」で「国学院大学前」下車すぐ。JR線、東京メトロ日比谷線恵比寿駅西口ロータリー1番乗り場より都営バス「学06日赤医療センター行き」で「東四丁目」下車。徒歩5分。
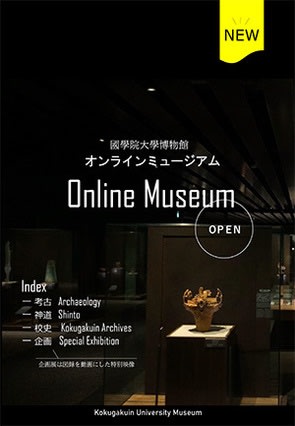
オンラインミュージアムOPEN
http://museum.kokugakuin.ac.jp/event/detail/online_museum
まず先行してアップされたのが常設展示の「考古ゾーン」で、現在、「先史時代の造形-縄文・弥生-」、「国家形成と神道-古墳・古代-」、「日本宗教の原型-古代・中世-」の3つの動画をyoutubeを通して見ることが出来ました。
このオンラインミュージアムで充実しているのは、単に展示風景を配信するのではなく、同博物館の准教授で考古学が専門の深澤太郎さんが資料を前に解説していることでした。例えば先史時代ではまず火炎型土器を取り上げていて、土器の内部のアップを交えつつ、用途などについて触れていました。
さらに土偶の変遷では「かたち」に着目していて、手や足がもげてバラバラになった資料の存在から、宗教的な儀式が行われていた可能性があることなどを知ることが出来ました。ともかく聞きやすく、分かりやすい内容で、あたかもオンラインで講義を受けているかのようでした。また日本語字幕が付いているのも、内容の理解を深めるのに有用かもしれません。
続く「国家形成と神道」で興味深いのは、古墳時代の埴輪の原型は、一般的に知られた動物や人物の埴輪ではなく、飲食物を象徴する壺型の土器にあるということでした。また被葬者に捧げる飲食物から埴輪は成立したことから、埴輪に表現された動物や人物も被葬者の財産を象徴していたと考えられるそうです。
3本目の「日本宗教の原型」では、仏教の受容に伴う火葬の導入について言及していて、それまでの古墳時代の死体を保存するあり方から、大きく葬送観念が変化したことを理解出来ました。また中世の和鏡に刻まれた男神像の精緻な画像も見どころではないでしょうか。そもそも古来の日本の在来の神は姿を顕すことをしなかったものの、仏像の影響を受け、8世紀頃には神像が作られるようになったとのことでした。
以降、「神道ゾーン」、「校史ゾーン」も順次公開されるそうです。そちらも楽しみにしたいと思います。
【再開のお知らせ】國學院大學博物館は7月2日より、まずは週3日程度、12:00~16:00の短縮開館での再開が決定しました!入館にあたっては、検温やカードの記入など様々な対策を実施。詳しくはこちらをご覧ください。→https://t.co/ij6hxAoJr5 お出迎えの埴輪 #こくぴょん もマスク着用です!#再開 pic.twitter.com/olmZcmAvHD
— 國學院大學博物館 (@Kokugakuin_Muse) June 25, 2020
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、長らく臨時休館していた國學院大學博物館ですが、7月2日より再開することが決まりました。しばらくは常設展の観覧、及びミュージアムショップのみ利用することが出来ます。そして当面は木曜、金曜、土曜のみ開館し、日曜から水曜日は休館します。また開館時間も12時より16時までと大幅に短縮されます。
次回企画展「モノで読む古事記」は7月16日より開催され、展示もオンラインで配信される予定だそうです。まずはyoutubeに公開された予告編を楽しむのが良いかもしれません。
「モノで読む古事記」 國學院大學博物館(@Kokugakuin_Muse)
会期:2020年7月16日(木)~9月26日(土)
休館:毎週日・月・火・水曜日。8月9日(日)~26日(水)。
時間:12:00~16:00
*入館は閉館の30分前まで。
*短縮開館を実施。
料金:無料。
住所:渋谷区東4-10-28 國學院大學渋谷キャンパス 学術メディアセンター 地下1階
交通:JR線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、東急東横線・田園都市線渋谷駅より徒歩15分。渋谷駅東口バスターミナル54番乗り場より都営バス「学03日赤医療センター行き」で「国学院大学前」下車すぐ。JR線、東京メトロ日比谷線恵比寿駅西口ロータリー1番乗り場より都営バス「学06日赤医療センター行き」で「東四丁目」下車。徒歩5分。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










