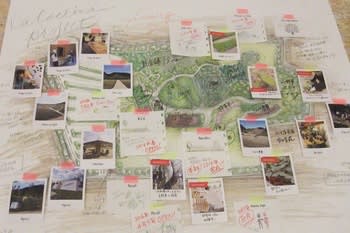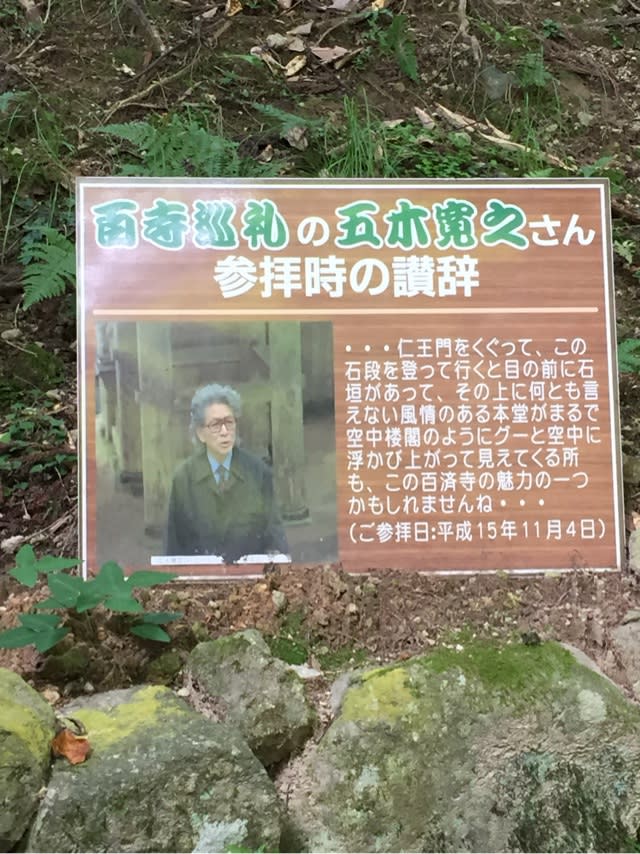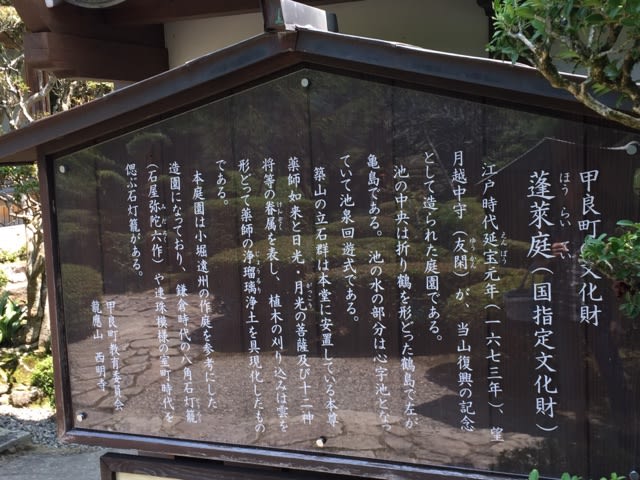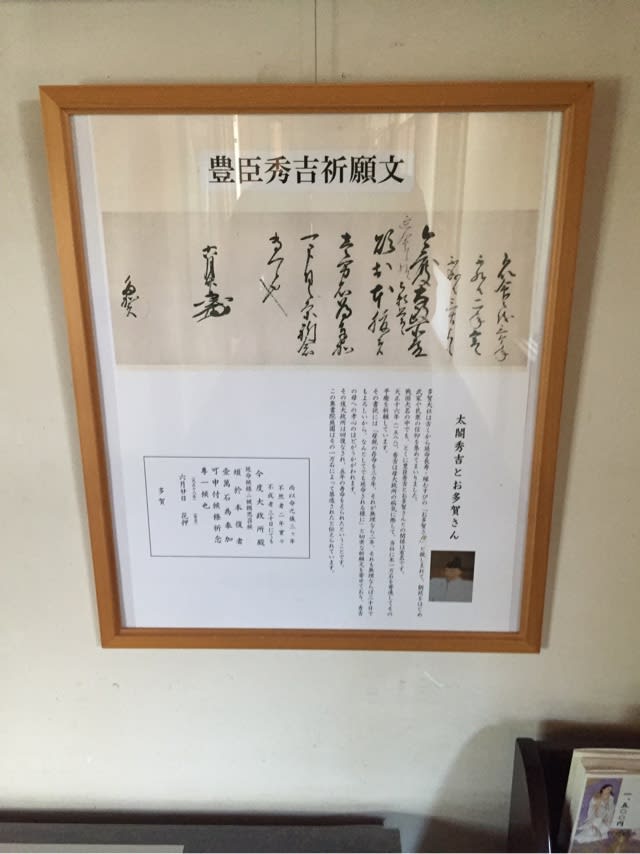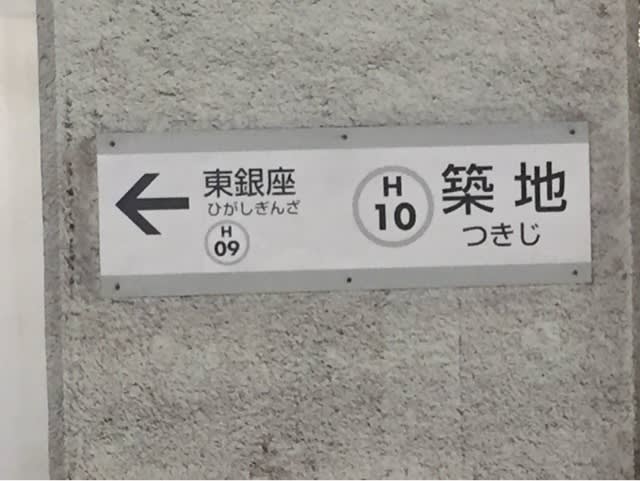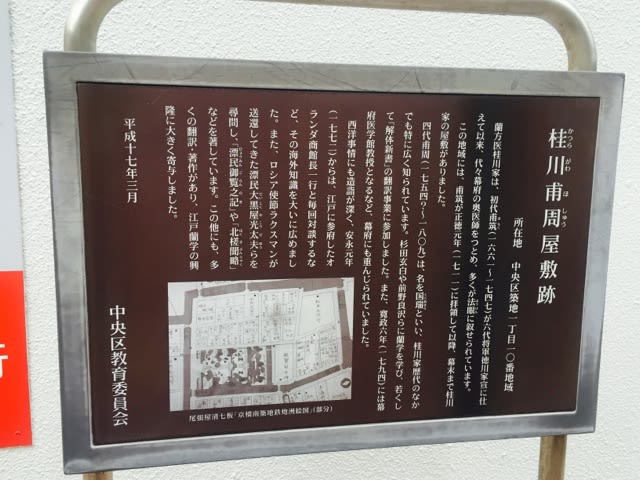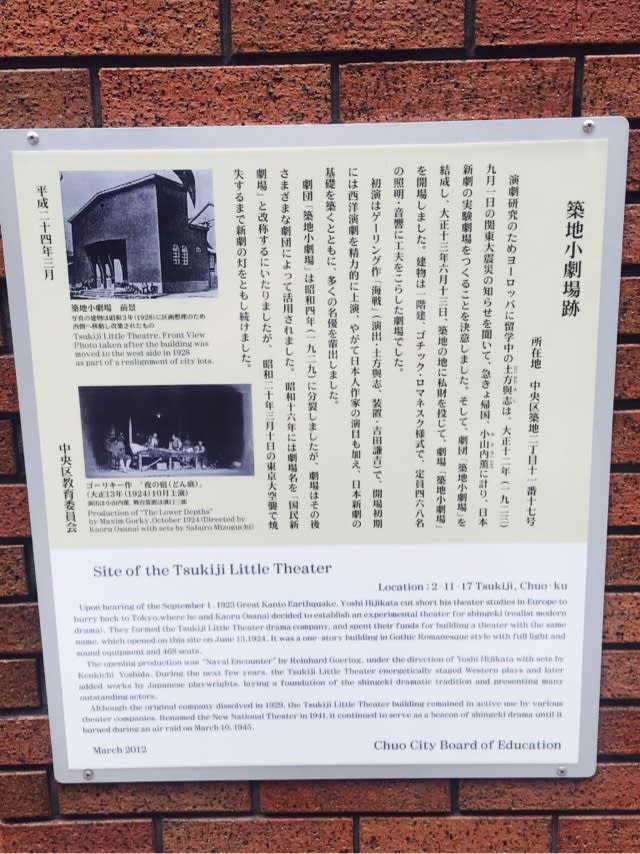『鉄道シリーズ』その147。4月にオープンした京都鉄道博物館を訪問する。JR西日本などが運営する博物館でその前身は大阪にあった鉄道科学博物館(2014年4月閉館、大正駅)とこの地にあった梅小路蒸気機関車館(2015年8月閉館)を統合して今年春にオープンした。

梅小路公園から歩くと左側には山陰本線の旧二条駅舎、その右側には1200円の入場料を払い入館する。


すると左からC62、クハ80(3つ窓タイプ)、0系新幹線がお出迎え。ほかにも食堂車や旧マロネフ38型一等寝台車、DD54型ディーゼル機関車、103系大阪環状線の電車などが並んでいる。



さらに建物に入ると新幹線122系、月光のヘッドマークがついた581系電車寝台車、雷鳥のヘッドマークがついた489系電車、さらに230型蒸気機関車、EF52型電気機関車、キハ80など懐かしい車両がオンパレードで一々写真を撮るため、中々前に進まない。

小生は博物館に来ると懐かしい車両と対面するたびに時刻表の表紙や博物館、さらに乗った時の思い出に浸ってしまうのである。中には子供の頃絵本で読んだEH10型電気機関車に連結はされていたコンテナ特急たから号の車掌車などもある。

2階に上がると電車だけでなく、各種鉄道機器の展示や駅弁、修学旅行列車なども展示されている。さらに人気なのはジオラマ、動いてはいなかったが子供たちには人気がある。

2階のデッキに出て旧梅小路蒸気機関車館のおうぎ形車庫には従来と同様に蒸気機関車が20両が並んでいる。動態保存されているC622蒸気機関車がその真ん中にあるターンテーブルに乗せられ、回転しているところに遭遇。

煙を吐いているC622の勇姿をしばらく見ている。そしてこのイベント終了後、蒸気機関車を一両ずつ眺めていくが、一番人気はお召列車の菊の紋章をつけたC53。


小生の好きなC55やカウキャッチャーのついた弁慶号などいくら見ていても見飽きることはない。

その後、トゥワイライトエキスプレスの横を通り、グッズの販売をしている二条駅舎に行く。閉館が近いこともあり、凄い人。とにかく、楽しい鉄道博物館であった。
後ろ髪を引かれながらバスに乗り京都駅に向かうが、渋滞に巻き込まれ何と30分も掛かってしまう。歩けば20分なのに、恐るべし京都駅周辺の渋滞。