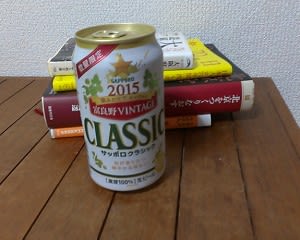○橋爪紳也編著;大阪検定1級合格者+α、大阪旅∞チーム執筆『大阪府謎解き散歩』(新人物文庫) 中経出版 2013.4
 NHK朝ドラ『あさが来た』が面白い。10月の放送開始から(オンデマンドを使って)完走中である。11月に関西に出かける機会があったときは、ぜひ物語の舞台や関連の史跡めぐりをしてみたいと思ったのだが、もう少し物語が進んでからにしようと考えて、思いとどまった(無料配布の地図だけはGETしてきた→大阪「あさが来た」推進協議会が作成)。
NHK朝ドラ『あさが来た』が面白い。10月の放送開始から(オンデマンドを使って)完走中である。11月に関西に出かける機会があったときは、ぜひ物語の舞台や関連の史跡めぐりをしてみたいと思ったのだが、もう少し物語が進んでからにしようと考えて、思いとどまった(無料配布の地図だけはGETしてきた→大阪「あさが来た」推進協議会が作成)。
さて、1月の三連休には、大阪の文楽公演(嶋大夫の引退公演である)を聴きに行く。そのついでに、少し街歩きをしたいと思い、下調べのつもりで本書を読んでみた。内容は「風土・地理編」「歴史編」「文化・民俗編」など5章に分かれるが、章ごとのテーマはあまり明確でない。各章には10~20くらいの項目が収められている。各項目はカラー写真つきで2~4ページほど。編著者の弁によれば、他の都道府県では歴史学や郷土史の専門家が分担執筆しているケースが多いそうだが、本書は「なにわなんでも大阪検定」の上級合格者や、街歩きのアテンドをしているプロのガイドさんが執筆している。そのせいか、語り口がとっつきやすく、魅力的で面白い。
歴史的に、古くは、なぜ「なにわ」と呼ばれたかという説明がある。「浪速(なみはや)」の転訛だというのは聞いたことがあったが、「魚庭(なにわ)」説もあるそうだ。大阪湾は「チヌ(黒鯛)」が多くいることから「茅渟(ちぬ)の海」と呼ばれたとか、記紀万葉の言葉だと思うがよく覚えていなかった。それから、難波宮の発見・発掘の話。仁徳天皇の高津宮はまだ特定されていないのか。堺の千利休屋敷跡は行ったなあ。家康の墓があるという南宗寺も。安倍晴明生誕地(阿倍野)は未見なので、今度行ってみたい。今年、話題になりそうな「真田丸」の位置については諸説あるそうだ。
私の最近の関心でいうと、やはり近代史が面白い。大久保利通が大阪を日本の首都にする建白書を出していたというのは知らなかったなあ。今年の朝ドラにも出てこなかったし。その後、前島密が江戸遷都案を出したことで消えてしまったようだ。明治の一時期には大阪府が現在の奈良県を統合していたというのも初耳。しかし大阪の行政は人口の多い摂津・河内・和泉地方に重点投資され、大和国(奈良県)への支出は抑えられたので、奈良県復活の運動が進められたという。行政の思惑と住民の利害は一致しないというのは、今の大阪都構想を思い出すような話。
御堂筋沿道のビルの高さは、もと31メートル(百尺以下)に統一されていたが、バブル期に50メートルに緩和された。橋下市政下でさらなる見直し検討が発表されたと本書は書いているけど、その後、どうなったのだろう。大阪府環状線が、建設の経緯や年代の異なる鉄道を組み合わせてパッチワーク的につくられたというのも興味深い。今でもその痕跡は随所に見ることができるそうだ。JR大阪駅のコンコースの床に「迷路」が描かれているというのも全然気づいていなかった。大阪人は誰でも知っているのかなあ。
この数年は、けっこう大阪に出かけているので、本書を読みながら、これ見た!知ってる!と記憶がよみがえるものもずいぶんあった。たとえば、毎年10月1~8日に大阪水上バスの淀屋橋港の桟橋に開設される「ご来光カフェ」。この時期だけ、東方の生駒山系から昇る朝日が拝めるのだという。私はこの季節に大阪中心部のホテルに泊まって「ご来光カフェ」のポスターを見た記憶があるが、なんのことだか分からなくてスルーしてしまった。残念。それからミナミにある「大阪名物 五階」の看板も、なんだろうと呆れて見た気がする。
食べ物関係の少し物足りなかった。もっと美味しいものは多数あるだろうにと思ったが、キリがないんだろうな。とりあえず「北極星」のオムライスは食べてみたい。心斎橋かー。
 NHK朝ドラ『あさが来た』が面白い。10月の放送開始から(オンデマンドを使って)完走中である。11月に関西に出かける機会があったときは、ぜひ物語の舞台や関連の史跡めぐりをしてみたいと思ったのだが、もう少し物語が進んでからにしようと考えて、思いとどまった(無料配布の地図だけはGETしてきた→大阪「あさが来た」推進協議会が作成)。
NHK朝ドラ『あさが来た』が面白い。10月の放送開始から(オンデマンドを使って)完走中である。11月に関西に出かける機会があったときは、ぜひ物語の舞台や関連の史跡めぐりをしてみたいと思ったのだが、もう少し物語が進んでからにしようと考えて、思いとどまった(無料配布の地図だけはGETしてきた→大阪「あさが来た」推進協議会が作成)。さて、1月の三連休には、大阪の文楽公演(嶋大夫の引退公演である)を聴きに行く。そのついでに、少し街歩きをしたいと思い、下調べのつもりで本書を読んでみた。内容は「風土・地理編」「歴史編」「文化・民俗編」など5章に分かれるが、章ごとのテーマはあまり明確でない。各章には10~20くらいの項目が収められている。各項目はカラー写真つきで2~4ページほど。編著者の弁によれば、他の都道府県では歴史学や郷土史の専門家が分担執筆しているケースが多いそうだが、本書は「なにわなんでも大阪検定」の上級合格者や、街歩きのアテンドをしているプロのガイドさんが執筆している。そのせいか、語り口がとっつきやすく、魅力的で面白い。
歴史的に、古くは、なぜ「なにわ」と呼ばれたかという説明がある。「浪速(なみはや)」の転訛だというのは聞いたことがあったが、「魚庭(なにわ)」説もあるそうだ。大阪湾は「チヌ(黒鯛)」が多くいることから「茅渟(ちぬ)の海」と呼ばれたとか、記紀万葉の言葉だと思うがよく覚えていなかった。それから、難波宮の発見・発掘の話。仁徳天皇の高津宮はまだ特定されていないのか。堺の千利休屋敷跡は行ったなあ。家康の墓があるという南宗寺も。安倍晴明生誕地(阿倍野)は未見なので、今度行ってみたい。今年、話題になりそうな「真田丸」の位置については諸説あるそうだ。
私の最近の関心でいうと、やはり近代史が面白い。大久保利通が大阪を日本の首都にする建白書を出していたというのは知らなかったなあ。今年の朝ドラにも出てこなかったし。その後、前島密が江戸遷都案を出したことで消えてしまったようだ。明治の一時期には大阪府が現在の奈良県を統合していたというのも初耳。しかし大阪の行政は人口の多い摂津・河内・和泉地方に重点投資され、大和国(奈良県)への支出は抑えられたので、奈良県復活の運動が進められたという。行政の思惑と住民の利害は一致しないというのは、今の大阪都構想を思い出すような話。
御堂筋沿道のビルの高さは、もと31メートル(百尺以下)に統一されていたが、バブル期に50メートルに緩和された。橋下市政下でさらなる見直し検討が発表されたと本書は書いているけど、その後、どうなったのだろう。大阪府環状線が、建設の経緯や年代の異なる鉄道を組み合わせてパッチワーク的につくられたというのも興味深い。今でもその痕跡は随所に見ることができるそうだ。JR大阪駅のコンコースの床に「迷路」が描かれているというのも全然気づいていなかった。大阪人は誰でも知っているのかなあ。
この数年は、けっこう大阪に出かけているので、本書を読みながら、これ見た!知ってる!と記憶がよみがえるものもずいぶんあった。たとえば、毎年10月1~8日に大阪水上バスの淀屋橋港の桟橋に開設される「ご来光カフェ」。この時期だけ、東方の生駒山系から昇る朝日が拝めるのだという。私はこの季節に大阪中心部のホテルに泊まって「ご来光カフェ」のポスターを見た記憶があるが、なんのことだか分からなくてスルーしてしまった。残念。それからミナミにある「大阪名物 五階」の看板も、なんだろうと呆れて見た気がする。
食べ物関係の少し物足りなかった。もっと美味しいものは多数あるだろうにと思ったが、キリがないんだろうな。とりあえず「北極星」のオムライスは食べてみたい。心斎橋かー。