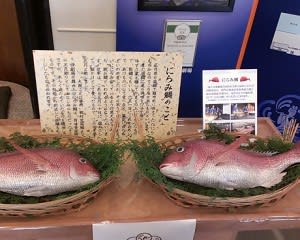○柏井壽『京都 奥の迷い道:街から離れて「穴場」を歩く』(光文社新書) 光文社 2015.10
 今年最初の京都行きの前に、京都案内本を多数執筆している著者の本を久しぶりに読んだ。半日くらいの散歩、ハイキング程度の道歩きコースが5つ紹介されている。洛中の「金閣寺から」「京都駅の南と西」に加えて、少し郊外の「洛北大原」「嵐電沿い」「嵯峨野」歩き。各コースに「食べる愉しみ」が紹介されているのがうれしい。
今年最初の京都行きの前に、京都案内本を多数執筆している著者の本を久しぶりに読んだ。半日くらいの散歩、ハイキング程度の道歩きコースが5つ紹介されている。洛中の「金閣寺から」「京都駅の南と西」に加えて、少し郊外の「洛北大原」「嵐電沿い」「嵯峨野」歩き。各コースに「食べる愉しみ」が紹介されているのがうれしい。
正月に著者の柏井壽さんが出演する『京都の食 8つの秘密』という番組をやっていて、私は大原の「しば漬け」を紹介する下りだけ見たのだが、本書の「洛北大原里歩き」にほぼ同じ内容が載っていた。建礼門院に里人が献上したのが始まりという伝説があるのだという。本書には、以前の著者の本に比べると、京都の歴史に言及したところが多い。ただ、歴史といっても、特産品のパッケージに印刷されているような、民話伝説の範疇を出ないので、正直、あまり面白くない。
著者の京都案内の魅力は、地元暮らしだから書ける、生活に密着した細部なので、無理に守備範囲を拡げないでほしい。それでは、他のライターの京都案内と何も変わらなくなってしまう。やっぱり、本書で面白いなあと思うのは、『里の駅大原』の『花むらさき』で日曜の朝だけ食べられる朝膳とか、太秦の『キネマ・キッチン』で食べられるカツライス(勝新太郎と市川雷蔵にちなむ)、金閣寺に近い『おむらはうす』など。京都のオムライスはふわとろ系より、きちっと巻いたほうが人気が高いそうで、私の嗜好に合ってうれしい。京都八条口はよく利用するので『喫茶なかむら』、うどんの『殿田』覚えておこう。
気になった寺社は、仁和寺近くの立本寺。東山以外にも幽霊飴の伝説を持つ寺があるのは知らなかった。嵐電沿いに「安倍晴明公嵯峨御墓所」があるというのも知らなかった。この墓所、室町時代の『臥雲日件録』にも登場する。もとは天龍寺の塔頭である寿寧院の境内にあったが、あまりに荒廃したため、晴明神社が土地を買収し、新たな墓を建立したのだそうだ。
梅林寺も興味深い。土御門家の菩提寺である。私は一度塀の前を歩いてみたことがあるが「拝観するにはあらかじめ申し込んでおく必要がある」という。逆にいうと、予約すれば拝観できるのか! 知らなかった。土御門家は、一時は京都を逃れ、若狭に身を寄せていたが「関ヶ原の戦いの後、徳川家康に見出され、復権を果たして梅小路に邸宅を構える」。「きっと土御門家は秀吉に快く思われていなかったのだろう」と著者は推測している。もっとよく知りたい。
めったに知っている人はいないと思うが、私は行ったことがあって、なつかしく思い出したのは、「妖怪ストリート」と呼ばれる一条通。平清盛の西八条邸の跡と伝える若一神社など。嵯峨野の湯豆腐の店『西山艸堂』は、学生の頃「嵯峨野に行くなら湯豆腐を食べなくては」みたいに気負って食べに行った記憶がある。もう30年くらい経つが、確かに美味しかった。なつかしい。食べもののために京都に行くなんて、絶対しないと思っていたが、そういう旅行もいいと思うようになってきた。
 今年最初の京都行きの前に、京都案内本を多数執筆している著者の本を久しぶりに読んだ。半日くらいの散歩、ハイキング程度の道歩きコースが5つ紹介されている。洛中の「金閣寺から」「京都駅の南と西」に加えて、少し郊外の「洛北大原」「嵐電沿い」「嵯峨野」歩き。各コースに「食べる愉しみ」が紹介されているのがうれしい。
今年最初の京都行きの前に、京都案内本を多数執筆している著者の本を久しぶりに読んだ。半日くらいの散歩、ハイキング程度の道歩きコースが5つ紹介されている。洛中の「金閣寺から」「京都駅の南と西」に加えて、少し郊外の「洛北大原」「嵐電沿い」「嵯峨野」歩き。各コースに「食べる愉しみ」が紹介されているのがうれしい。正月に著者の柏井壽さんが出演する『京都の食 8つの秘密』という番組をやっていて、私は大原の「しば漬け」を紹介する下りだけ見たのだが、本書の「洛北大原里歩き」にほぼ同じ内容が載っていた。建礼門院に里人が献上したのが始まりという伝説があるのだという。本書には、以前の著者の本に比べると、京都の歴史に言及したところが多い。ただ、歴史といっても、特産品のパッケージに印刷されているような、民話伝説の範疇を出ないので、正直、あまり面白くない。
著者の京都案内の魅力は、地元暮らしだから書ける、生活に密着した細部なので、無理に守備範囲を拡げないでほしい。それでは、他のライターの京都案内と何も変わらなくなってしまう。やっぱり、本書で面白いなあと思うのは、『里の駅大原』の『花むらさき』で日曜の朝だけ食べられる朝膳とか、太秦の『キネマ・キッチン』で食べられるカツライス(勝新太郎と市川雷蔵にちなむ)、金閣寺に近い『おむらはうす』など。京都のオムライスはふわとろ系より、きちっと巻いたほうが人気が高いそうで、私の嗜好に合ってうれしい。京都八条口はよく利用するので『喫茶なかむら』、うどんの『殿田』覚えておこう。
気になった寺社は、仁和寺近くの立本寺。東山以外にも幽霊飴の伝説を持つ寺があるのは知らなかった。嵐電沿いに「安倍晴明公嵯峨御墓所」があるというのも知らなかった。この墓所、室町時代の『臥雲日件録』にも登場する。もとは天龍寺の塔頭である寿寧院の境内にあったが、あまりに荒廃したため、晴明神社が土地を買収し、新たな墓を建立したのだそうだ。
梅林寺も興味深い。土御門家の菩提寺である。私は一度塀の前を歩いてみたことがあるが「拝観するにはあらかじめ申し込んでおく必要がある」という。逆にいうと、予約すれば拝観できるのか! 知らなかった。土御門家は、一時は京都を逃れ、若狭に身を寄せていたが「関ヶ原の戦いの後、徳川家康に見出され、復権を果たして梅小路に邸宅を構える」。「きっと土御門家は秀吉に快く思われていなかったのだろう」と著者は推測している。もっとよく知りたい。
めったに知っている人はいないと思うが、私は行ったことがあって、なつかしく思い出したのは、「妖怪ストリート」と呼ばれる一条通。平清盛の西八条邸の跡と伝える若一神社など。嵯峨野の湯豆腐の店『西山艸堂』は、学生の頃「嵯峨野に行くなら湯豆腐を食べなくては」みたいに気負って食べに行った記憶がある。もう30年くらい経つが、確かに美味しかった。なつかしい。食べもののために京都に行くなんて、絶対しないと思っていたが、そういう旅行もいいと思うようになってきた。