桜 と紅葉
と紅葉 の名所である談山(たんざん)神社を参拝して来ました。
の名所である談山(たんざん)神社を参拝して来ました。 飛鳥の東方にそびえる多武峰(とうのみね)の山中にたたずむ談山神社には中臣 鎌足公が主祭神として祀られています。 神仏分離以前は寺院であり、多武峰妙楽寺といっていたようです。
飛鳥の東方にそびえる多武峰(とうのみね)の山中にたたずむ談山神社には中臣 鎌足公が主祭神として祀られています。 神仏分離以前は寺院であり、多武峰妙楽寺といっていたようです。
 ここは大化の改新でお馴染みの中大兄皇子(後の天智天皇)、中臣 鎌足(後の藤原鎌足公)が日本の将来について、西暦645年5月に語り合った(国家改新の密談)ことから「談い(かたらい)山」と呼ばれ神社社号の起こりとなっています。
ここは大化の改新でお馴染みの中大兄皇子(後の天智天皇)、中臣 鎌足(後の藤原鎌足公)が日本の将来について、西暦645年5月に語り合った(国家改新の密談)ことから「談い(かたらい)山」と呼ばれ神社社号の起こりとなっています。 「談い山」(566m)は本殿の裏山で山頂には大化の改新 談合の碑が立っています。
「談い山」(566m)は本殿の裏山で山頂には大化の改新 談合の碑が立っています。

「談い山」での談合とは、どんな内容  蘇我蝦夷と入鹿親子の勢力が
蘇我蝦夷と入鹿親子の勢力が 極まり、国の政治をほしいままにしていた頃、中臣 鎌足(後の藤原鎌足公)は強い志を抱いて、国家の正しいあり方を考えていました。
極まり、国の政治をほしいままにしていた頃、中臣 鎌足(後の藤原鎌足公)は強い志を抱いて、国家の正しいあり方を考えていました。 その時、飛鳥の法興寺(今の飛鳥寺)での蹴鞠会(けまりえ)で中大兄皇子に初めてまみえることができた鎌足公は、志を語り意見が一致し、多武峰の山中で「大化改新」の談合を行なったということです。
その時、飛鳥の法興寺(今の飛鳥寺)での蹴鞠会(けまりえ)で中大兄皇子に初めてまみえることができた鎌足公は、志を語り意見が一致し、多武峰の山中で「大化改新」の談合を行なったということです。

そんなことで、中大兄皇子と藤原 鎌足公が初めてお会いでき「大化改新」に至った発端は飛鳥法興寺の蹴鞠会であったことから、談山神社でも毎年4月29日と11月3日に「けまり祭」が行われています。 飛鳥時代の雅びが感じられるお祭りとのことです。見てみたいですね。
飛鳥時代の雅びが感じられるお祭りとのことです。見てみたいですね。
蹴鞠の庭から見た神廟拝所と十三重塔です。

授与所で御朱印を頂き、拝殿に移り歴史絵巻を拝観したり、幼稚園児の絵画が飾られ、格式ある神社にとても暖かいものを感じました。 これは 長岡千尋宮司
長岡千尋宮司 のお考えによるものだろうと推察致しました。
のお考えによるものだろうと推察致しました。

それは談山神社発行の『談(かたらい)』2016年1月 通刊85号に、こうありました。 平成27年12月に神社の平成の大修理事業であった奈良県指定文化財「東大門」の修理が足かけ10年を掛けて竣工した「御礼の言葉」の中であります。

この度の修理事業は、申すまでもなく氏子・崇敬者の皆様の御支援がなければ成し得ないことでした。 皆様の崇敬の真心が一つに集まって、これを成し遂げたのです。ここに重ねて御礼、感謝の言葉を申し上げます。 談山神社の1300年の歴史と文化はもとより、数々の貴重な建造物は次世代へ継承されることになりました。 古来、日本は神国である。という言葉があります。 一つのイデオロギーからの見方という考えもありましょう。・・・
談山神社の1300年の歴史と文化はもとより、数々の貴重な建造物は次世代へ継承されることになりました。 古来、日本は神国である。という言葉があります。 一つのイデオロギーからの見方という考えもありましょう。・・・  しかしこれを実際に地理的に見てみますと、北海道から沖縄まで日本列島には、点として都会の大社から地方の各村々の氏神まで合わせて八万余社が鎮座しています。 これを線として結び付けると、ほぼ列島の形を描くことができるのではないでしょうか。神国たるゆえんです。
しかしこれを実際に地理的に見てみますと、北海道から沖縄まで日本列島には、点として都会の大社から地方の各村々の氏神まで合わせて八万余社が鎮座しています。 これを線として結び付けると、ほぼ列島の形を描くことができるのではないでしょうか。神国たるゆえんです。 神社は人々の暮らしと共にあります。神社の森は人々の憩いの場であり、子供の遊び場です。 祭りの時は、そこが信仰の場になりますが、神社と人々は常に一緒にあるのです。
神社は人々の暮らしと共にあります。神社の森は人々の憩いの場であり、子供の遊び場です。 祭りの時は、そこが信仰の場になりますが、神社と人々は常に一緒にあるのです。 これが我が国の国体(くにぶり)であります。 (以上原文)
これが我が国の国体(くにぶり)であります。 (以上原文)

境内で子供たちが楽しそうに走り 回っている姿を見かけました。 明治に
回っている姿を見かけました。 明治に 官幣社
官幣社 となられた神社の現長岡宮司、格式高い神社の宮司に相応しく御立派な方であります。
となられた神社の現長岡宮司、格式高い神社の宮司に相応しく御立派な方であります。












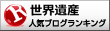

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます