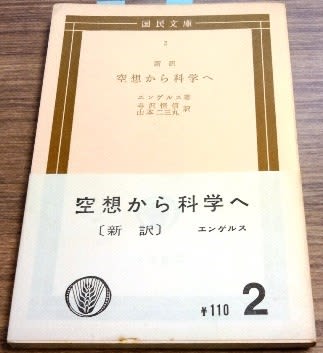ディドロ「ブーゲンヴィル航海記補遺」に続いて、森本和夫編『婚姻の原理』(現代思潮社、1977年改訂版)に収録(抄録)された婚姻論、家族論を読んでいる。
第1部は、マルクス、エンゲルスに先行する論者として、ディドロのほかにルソー『人間不平等起源論』が収録されているが、ルソーの結婚論といえば、『エミール』だろう。
エミールは家庭教師のもとを離れてヨーロッパ各地を遊学した後に、ふたたび家庭教師を訪ねてソフィーとの結婚を報告する。エミールに対する教育の最終章がエミールの結婚であり、しかもエミールは家庭教師に向かって、「自分たちの子どもは自分たちの手で教育する」と宣言する。この終わり方の含意をぼくは考えたが、森本は、ルソーは女たちを所帯に閉じ込めよと説いているというフーリエの言葉を援用して、『エミール』におけるルソーの結婚論はブルジョワ思想の枠を超えていないとして、『エミール』を採用しなかったという。
「ブルジョワ」家族法の枠内にいるぼくは、ルソーがエミールの結婚と子育て宣言によって『エミール』を結んだことに意義があると思う。家庭教師によるエミール教育の到達点がエミールの自立と結婚であり、自分たちの子どもは自らの手で育てるというエミールの結婚観、子ども観は、現在でも一般的だと思う。
第2部は、マルクス、エンゲルスおよびマルクス主義者の婚姻論、家族論が収録されている。マルクスの「婚姻論」は『共産党宣言』や『経哲草稿』などの中の短い文章であり、中心はエンゲルス『家族、私有財産、国家の起源』である。森本によって、同書のもっとも中核的部分が抄録されていて、省エネ読書には助かる。
ベーベル「職業としての結婚」(『婦人論』の一部)は、NHKテレビで放映された「ダウントン・アビー」を思い出させる。経済的に窮乏したイギリス貴族が、領主館(Manor house)を維持するために、持参金は十分あるが爵位がほしいアメリカ人女性と結婚する話だが、ベーベルは、そのような男女を斡旋する業者を「結婚取引所」と揶揄し、そのような男女の結婚を「金銭結婚」と批判する。そして、結婚関係に入ろうという男女の関係がそのような結合にふさわしいものかどうかは、「結合の本来の目的、すなわち自然衝動の満足と種族の生殖による自己の存在の延長には関係のない一切の利害をしりぞけることによってのみ」判定されるという(118頁)。
「ダウントン・アビー」では、不純な動機で結婚した2人であったが、夫婦の間に愛と信頼関係が芽ばえる経過が描かれていた。結婚における経済的側面、当事者たちの利害打算を無視することはできないだろう。
第3部は、マルクス、エンゲルスに直接影響を与えた論者としてヘーゲル『精神現象学』と『法の哲学』の一部、およびフーリエ「不統一所帯における男の倦怠」『四運動の理論』所収、モルガン『古代社会』の一部が抄録されている。ヘーゲルはぼくには読解不能なのでスルーした。
モルガン『古代社会』は、「一夫一婦制」の章だけが抄録されているのだが、荒畑寒村訳が意外にも読みやすいのに驚く。「荒畑寒村」という名前から明治時代の擬古文調の翻訳を想像したが、彼はそれほど昔の人ではなかった。まったく古さがなく、現代の文章といっても何ら違和感を感じない。例えば「(古代ギリシアでは)結婚の主要目的が正当な婚姻によって子供を産むこと・・・この結果を保証するために婦人を隔離すること」にあった、など(162頁)。
下の写真は、青山道夫新訳の岩波文庫版。

シャルル・フーリエは「空想的」社会主義者として有名だが、そう呼んだのは科学的マルクス主義を自称するエンゲルス『空想から科学へ』(冒頭の写真は大月書店の国民文庫版)である。
エンゲルスは、「空想的社会主義者」サン・シモン、フーリエ、オーウェンの3人に共通するのは、「彼らが、そのころ歴史的に生まれていたプロレタリアートの利害の代表者として登場したのではな(く)、啓蒙思想家たちと同様に、まずある特定の階級を解放しようとは思わないで、いきなり全人類を解放しよう思った」点にあるという(寺沢恒信ほか訳、国民文庫59頁)。社会主義革命がプロレタリアートを解放できなかったことが明らかになった現在からみると、エンゲルスとフーリエは人間の解放という同じ出発点に立っている。
フーリエはユートピア的な愛の世界を構想し、熱心な信奉者しか集まらなかったものの(ゲランは彼らを「ファランステェール主義者」と呼んでいる)、その端緒的な協同体を現実に立ち上げているのだから、ただの「空想家」や「ユートピアン」(夢想家)ではないと思うが、ゲランもフーリエを「ユートピアン」と呼んでいる。全ての人間の解放を夢見た点ではエンゲルスも「夢想家」ではないか。
「不統一所帯における男の倦怠」では何のことか分かりにくいが、中身を読めば「不和の夫婦における夫の鬱屈」くらいの意味ではないか。
フーリエによれば、男が結婚を躊躇する最大の理由は、「父親とは、婚姻が指し示す夫である」――つまり婚姻した妻が生んだ子の父親は妻の夫であるというローマの法諺に由来する法律であるという。「全男性の恐怖の的である」この法律のために夫は、他の男の接近を許したあげく怪しげな子どもをおしつけられないように、妻の傍らで汲々として夫の務めを果たさねばならない(153頁)。両性を不和に追い込んでいるこのような婚姻制度を打破しなければならないとフーリエは煽動する。
フーリエはニュートンの万有引力に倣って、人間関係を支配する4つの原理の1つとして「情念引力」なるものを提唱する。フーリエが「性革命」の世界でも先駆者であったことは、第5部に収録されたダニエル・ゲラン『エロスの革命』によって知ることができる。
ゲランによれば、フーリエは韜晦によって偽装しているが、多夫多妻制を肯定し、サディズム・マゾヒズムを肯定し(ケッセル「昼顔」の先駆者という)、近親相姦を肯定し、同性愛、少年愛をも肯定しているとゲランは解読する(279~80頁、283~5頁)。しかも、フーリエもまた(ディドロと同じく)タヒチに「単純な自然のままの愛の自由」の名残を見ている(277頁)。
こちらの方面でのフーリエのラディカルさは、マルクスらをはるかに凌いでいる。マルクス『共産党宣言』が唱えた「婦人の共有」(森本書68頁)を打ち消すエンゲルス『共産主義の原理』などの弁明のほうが(森本116頁)はるかに及び腰である。
ゲラン『エロスの革命』の中の「フーリエ」論が森本が編んだ「婚姻論集」の最終章の最後に置かれた意味をどう考えればよいのだろうか。
※ 長くなったので、この項は一応ここまでとして、第4部、第5部については項を改める。
2021年4月13日 記