堂目卓生『アダム・スミス--『道徳感情論』と『国富論』の世界』(中公新書、2008年)を読んだ。「どうもく」(瞠目)とお読みするのかと思っていたが、「どうめ」とルビがあった。
アダム・スミス(水田洋訳)『法学講義』(岩波文庫)を読んで、スミスの『道徳感情論』は読んでおくべき本だと思ったのだが、いきなり『道徳感情論』(もちろん翻訳)を読んでも、著者の趣旨を読み取る自信がなかったので、解説書から読むことにした。
そもそもは、今年の憲法記念日の東京新聞に載った水田洋さんへのインタビューを読んだのがきっかけで、水田訳『法学講義』を読んだのだが、残念ながら水田訳の『法学講義』の訳文には、とくに「家族法」「私法」の部分で、何か所か理解ができないところがあった。とくに指示代名詞が何を指しているのか分かりにくい個所が目立った。水田訳に問題があるのか、そもそも同書がスミスの講義を受講した学生のノートが原本になっているため、その学生のノート自体に問題があるのかは、私には分からない。
ということで、水田訳『道徳感情論(上・下)』(岩波文庫)に挑戦しても、難渋した挙句に著者の言いたいことを理解できないのではないかという不安を払拭できなかったのである。

まず手始めに、堂目『アダム・スミス』を読んだのは正解だった。
この本はその年のサントリー学芸賞を受賞したとある。サントリー学芸賞は審査員の好みがけっこう反映されているせいか、時おり「何でこの本が?」と思うような本が受賞することもあるが、この本に関してはきわめて適切な受賞だと思う。
とにかく分かりやすい。著者がスミスをよく理解していることが伝わってくる。引用される『道徳感情論』の訳文も著者自身によるもので、明快である。
今回の堂目氏の本によって、スミスの『道徳感情論』がよく理解できたつもりだったが、ここに要約を書こうとしたら筆が(キーボードが?)進まない。実は十分に理解できていないという証拠だろう。
※下の写真は、エディンバラのロイヤル・マイルに立つアダム・スミス像(2014年3月26日撮影)。スミスは晩年はグラスゴウではなく、エディンバラで過ごしたという。彼は当時のエディンバラの最高所得者だったという。そういえば2、3日前のNHK・BSプレミアムの「世界ふれあい街歩き」でグラスゴウをやっていた(再放送)。グラスゴウ大学もチラッと映ったが、意外と小さな大学だった。

『道徳感情論』は社会秩序を導く人間の本性は何かを解明しようと試みた書である。
社会秩序のために人は法を作るが、人間本性の何が法を作り、法を守らせているのかとスミスは問う。この問いに対する回答の核心にあるのは「同感」(sympathy)である。
人間は自分の幸福を何よりも優先するが(自愛心)、しかし他人の行為の適否や、自分についての他人の評価にも関心をもつ。(他人が別の他人に対して行った行為の結果を、もし)自分が受けたとしたら感謝の念をいだくか、それとも憤慨するかを、私たちは自分の心の中にある「公平な観察者」(impartial spectator)によって判断し、前者(感謝)であれば称賛し、後者(憤慨)であれば非難する。
そして人間は、自分自身の行為もこの「公平な観察者」の判断に従って律しなければならないという「義務の感覚」をもつ。「義務の感覚」に従う人は心の平静を得ることができる。しかし「義務の感覚」に従わず他人の生命や財産を侵害するなど正義に反する行為に対して、社会は「法」という強制力によって対処することになる。
国民の豊かさ(繁栄)への道を説く『国富論』も、この『道徳感情論』に示された人間の本性に基いて読まれるべきである。
スミスは、市場における自由競争に委ねておけば(神の)「見えざる手」(invisible hand)によって予定調和に達するという「市場の自由」や「自由競争(レッセフェール)」論者と言われているが、スミスはそのような趣旨で「見えざる手」という言葉を用いていない、彼の「見えざる手」を理解するためには『道徳感情論』を読まなければならないということは、ぼくのような門外漢でもどこかで聞き及んでいた。水田さんの『アダム・スミス』(講談社学術文庫)だったかもしれない。
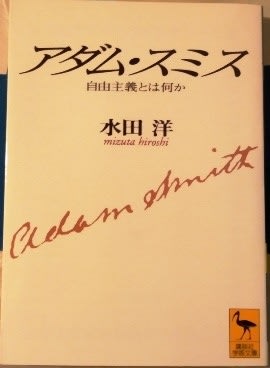
堂目氏の本書によれば、スミスが「見えざる手」(スミスは「神の」とは言っていない)という言葉を使ったのは、『道徳感情論』で1か所(水田訳・岩波文庫版(下)24頁)、『国富論』で1か所(大河内監訳・中公文庫版Ⅱ120頁)だけであり、いずれも市場における自由競争などとは全く関係ない文脈で使われている。
前者(『道徳~』)では、富裕な農業経営者が土地からの収益を利己性と貪欲の目的で使用したとしても、結局は「見えざる手」に導かれてすべての住民の間でほぼ平等に生活必需品の分配が行われることになると述べ、後者(『国富論』)も、生産者が自身の利得を目的として生産物が最大価値をもつように産業を運営したとしても、「見えざる手」によって社会の利益が増進されることになると述べたのである。
「見えざる手」は、因果の流れの原因を説明しないで済ますことができる使い勝手が良い言葉のため、スミスの本来の趣旨を離れてあちらこちらで使われることになった。げんにこの本の著者も、「称賛・非難の不規則性という、いわば「見えざる手」に導かれて、知らず知らずのうちに住みやすい社会を形成するのである」(48頁)といった具合に「見えざる手」を使っている。
数日前の東京新聞でも、浜矩子氏がスミス「見えざる手」の俗論を批判し、政府の「見えざる手」による介入への警戒を論じていた。

* * *
ぼくは法学部1年生向けの「法学」の講義を担当した際に、何回か碧海純一『法と社会』(これも中公新書だった)をテキストに指定した。
ぼくの理解では、同書によれば、「法」というのは社会秩序を維持し、社会を統合する手段の1つであり、社会統合の手段には、(個人の内面の)社会化と、(外部からの)社会統制の2つがある。
社会を構成するメンバーは生まれたときから親、兄弟、(公園の砂場から始まる)友人、教師、同僚たちと関係をもつ過程で、おのずからその社会で要求されるルールを自らの心のうちに内面化するようになる(社会化)。したがって社会のメンバーの多くは、自分の心のうちに内面化されたルールに従って生活していれば、「法」などなかったとしても社会生活を営むことができる。
しかしメンバーの中には、残念ながら家族関係の歪みなどのためにこのようなルールの内面化に失敗した者が存在する。そのような者に対しては、外部からの社会統制をかける必要がある。「法」はそのような外部からの社会統制手段の1つだが、最終手段として国家による強制力によって実現されるという点で他の社会統制手段とは異なる。
もし私たちの社会から「法」がなくなったとしても、社会化された多くのメンバーはルールに従って生活するだろうが、社会化に失敗したメンバーが存在する以上、最終手段としての「法」の発動が控えていなければならない、「たかが法、されど法」なのだ--といった趣旨を話してきた。碧海氏の論旨どおりではないかもしれないが、こんな前提の上に刑法や民法の話をした。
他者への「同感」、みずからの内なる「公平な観察者」を出発点とするスミスの『道徳感情論』は、このような法律「観」をもつ私にとって、親近感を抱かせるものであった。
ただし心の内なる「公平な観察者」というのは、かなり高徳の人間でなければ持ちえないように思われる。『ブーガンヴィル世界周航記』以来の近代人の懸案である「嫉妬」の感情などは、ぼくのような凡人が「公平な判断者」となる妨げになっている。
堂目氏が本書を執筆するきっかけになったという(鐘紡の)武藤山治に対するスミスの影響を研究したという院生の論稿も読んでみたい。城山三郎の企業小説もスミスの視点から読み直せるかもしれないと思う。この本を読むと、ついついスミスを現代に引き付けて考えがちになるが、現代の経済界でスミスの精神を継承すると目される経営者は誰かいるのだろうか。
なお、この本の謝辞の中に、このブログでも時折登場する従弟の名前を見つけた。
2021年5月27日 記










