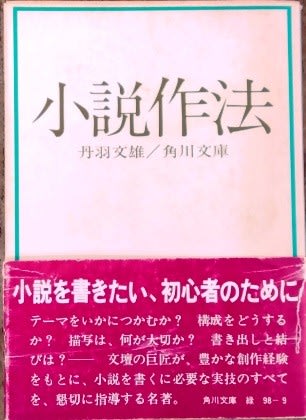
持っているはずなのに見つからなかった丹羽文雄「小説作法」(角川文庫、昭和40年、手元にあるのは昭和52年第12版)を本棚で見つけた。
志賀直哉の「小僧の神様」なら小学生が読んでも面白いかもしれないと思って、志賀「網走まで 他16編」(旺文社文庫、昭和52年)を本棚から取り出そうとしたら、その数冊隣りに、何と!探していた時には見つからなかった丹羽「小説作法」が並んでいるではないか。
ぼくの記憶通りにカバーのかかった角川文庫版であった(上の写真)。しかも、図書館で借りてきた講談社文芸文庫版には入っていなかった「小説作法・実践編」という続編も合本となって収められていた。
さらに驚いたことに、途中で投げ出したと思っていたのだが、「正編」だけでなく「続編」=「実践編」までちゃんと読み通したようで、青インクのペンで傍線まで随所に引いてある。読まなかったのは「正編」の実作例として掲載された「女靴」と「媒体」という小説だけだった。しかも、読んだ時期と動機も記憶違いだった。
ぼくは、庄司薫「赤頭巾ちゃん気をつけて」やサリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」のような青春小説を書きたいと思って、20歳前後の頃にこの本を読んだように記憶していたが、「1977年11月9日に読了」とメモがある。27歳の時に読んだのだった。さらに、最終ページには「日経・経済小説懸賞募集」の広告が切り抜いて挟んであった。「経済・ビジネスに題材を求めた長編で、400字詰め原稿用紙350枚~500枚、選考委員は江藤淳、尾崎秀樹、城山三郎、新田次郎、山田智彦の各氏、当選賞金300万円、佳作2作各50万円」とある。
27歳といえば社会人3年目で、サラリーマン生活最初の危機の渦中にあったころである。世間知らずだったぼくが大学を出て初めて経験した「サラリーマン生活」の日々を書こうと思ったのだった。自分を松山中学校の「坊っちゃん」に見立てて、悪戦苦闘の末に最後は赤シャツ連合に敗北して会社を辞めて故郷に帰るというストーリーを考えていたのだった。当時のぼくは笹川巌「怠け者の思想」(PHP)に表れたサラリーマン像に共感していて、それが主人公の造形にも影響したように思っていたが、調べると笹川の本は1980年発行だったからここでも記憶の捏造があったようだ。あるいは1980年代に入ってからも未完の小説を書きつづけていたのかもしれない。
丹羽「小説作法」(角川文庫版)で、傍線を引いてあったのは以下のような箇所である(要約して引用した個所もある)。
「私は説明という形式を極端なくらいに避ける。説明の部分が多いととかく低調になりやすい」(25頁)、「作者はつねに、どんな人間に対しても貪婪なくらいの好奇心と愛情をもっていなければならない」(28頁、嫌な奴でも愛情をもって観察するなどということは当時の(今でも)ぼくには無理だった)、「誰からもどこからも非難されないような立派な主人公は嘘である。そんな主人公に出会えば、読者は退屈をしてしまう」(35頁)、「作中人物が正義感にあふれて言動するのはいいのだが、作者までがそれと一緒になって正義感をふりまわすのは間違いであ(る)、たとえ主人公が作者であろうと、小説である以上は、別の存在でなければならない」(86頁)などの助言は、出版社で正義漢のつもりで暴れる主人公を想定していた当時のぼくにはきわめて適切な助言だっただろう。小説は書けなかったけれど、当時の現実社会(会社)で自分の行動を客観視する指針として役に立ったはずである。
「作者には自ずと限界がある、大切なことは、作者は己のよく知っている範囲内で小説を書くということである」(42頁)、「テーマはしっかりしたもの、自分の身についたものを探したほうがよい」(54頁)、「小説を書きはじめる人が、筋をどの程度に決めてかかるかと迷うのは当然である。いくつかの章に大別してかかれば安心出来る。この章には何枚ぐらい、という風に計画を立てる。書出し、発展の過程、結びと大別してかかれば、便利であろう」(67頁)、「事件または行為、人物、背景の三つが小説の三要素である。人物(には)自分のよく知っている人間をモデルに借りる」(88~9頁)、自然描写も自分の知っている場所を選ぶべきであり、丹羽は三鷹(武蔵野市西窪?)に住んでいたので熟知している三鷹駅周辺や(国木田独歩のではない)昭和戦後期の武蔵野の風景をよく登場させたという。
小説における「時間の経過」についての助言や(131頁)、小説の中の「会話」は日常生活の会話とは異なることの注意もあった。「正編」の最後では、「自分のことを書き給え、自伝を書き給え、この素材はどんな素材よりも秀れている、先ず自分のことから書くべきである。自分のことが書けないような作家は、一人まえの小説家とは言えない」と助言し、しかし「自分のことを書くのには勇気がいる」と忠告する(180頁)。
当時のぼくが自分のサラリーマン生活を書こうとしたのは、丹羽の指南に従えばテーマ設定として正解だったけれど、主人公と作者自身を分離して、正義感を振りかざす主人公を客観的に観察して叙述するといった芸当は当時のぼくにはできなかった。
結局ぼくは構想した小説を書きあげることはできず、その後転職の決断もできないまま 9年間も編集者稼業をつづけた挙句に、在職10年目の4月末に出版社を退職し、紆余曲折を経た後に教師になった。今では、教師こそぼくにとっての天職だったと思っている。もし本気で小説家などを目ざしていたら、その後の自分はどうなっていただろうと考えただけでも恐ろしい(昔の人なら「くわばら、くわばら」と胸をなでおろすだろう)。
ちなみに、丹羽「小説作法」の中には、「井伏鱒二の初期の自然描写は心にくいほど巧みであった。自然描写の名手は、その後あらわれていない」(90頁)という指摘もあった。初期の井伏とは「ジョン万次郎」あたりだろうか、今度読む時にはその自然描写にも気をつけて読んでみよう。「作者は読者の参加という問題に敏感でなくてはならない、読者は小説を補充してくれるものである」という忠告もあった。モームの小説でさえ、もっと読者を信じて、こんな描写や説明は省略すればよかったのにと思ったことがある(「凧」や「魔術師」などだったか)。
2025年1月10日 記









