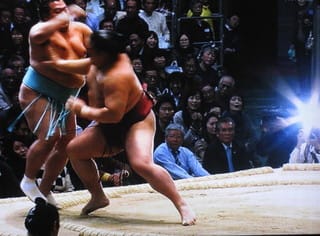彼岸過ぎまで、大阪旅行の記事を書く、第2弾(笑)。大阪市立東洋陶磁美術館で開催されている”北宋汝窯青磁 - 考古発掘成果展”をみにいってきた。2年半ほど前、台湾の故宮博物館を訪ねたとき、北宋汝窯の青磁の、雨上がりの空の色”雨過天晴”と賞される、美しい青色に感動して、それ以来フアンになっている。フアンになっても、汝窯は消滅していて、その窯の作品は世界中でも70点ほどしかなく、めったに観る機会がないのだ。
それが観られるとゆうので大阪まで来た。今回の特別展示は、最近、中国の考古学研究所が河南省の汝窯跡地の発掘調査を進め、そこで新たにみつかった作品(破片を組み合わせたものが多かったが)の、我が国初の公開なのである。楽しみにしていた展覧会だった。
ぼくは、前述の”雨過天晴”色にひと目ほれたので(汗)、あの天青色でなくては困るノダ(笑)。ちょっと緑がかったものも結構多く、それらはちらりと横目でみて(笑)、故宮博物館でみた、天青色に近いものの前で立ち止まった。汝窯のものは、模様のないのが普通だけど、今回のは、模様がついているものが主体であった(模様といっても、よくみないとわからないようなもの、どれが龍の模様?と言った感じ)。青磁印花龍浪涛文鉢とか、細かい貫入の入った、青磁印花蓮弁文鉢、明るい天青色の青磁弦文瓶等々、いくつか気に入ったものを名前を手帳にメモしてきた。それなりに満足した。
ちらしの写真から。実際はもっと青みがかっている。

知らなかったが、東洋陶磁美術館所蔵のものもあって、これは、とてもいい色で気に入った、特別展の最後の部屋に、飾られていたが、いちいち名札をみないので、てっきり、これも中国のものとして観ていた。あとで、売店で絵ハガキを買って、あっ、あれだと思って、引き返して、よくみたら、ここの所蔵品だった。もっと、はっきり示して欲しい(笑)。これが一番良かったノダ。”青磁水仙盆”とゆう名前がついている。まさに天青色で、申し分ない。故宮でも似たようなのがあったのを憶えているが、楕円形の汝窯の盆は、台湾の4点とこれしかないそうだ。お尻(底部)が、とくにうつくしい色だという説明があったが、覗きができないのが残念であった(汗)。”猫食盆”(猫の餌入れ)でなかったかという説もあるらしい。高貴なにゃんこ専用だったのだろうか(笑)。これを観ただけでも、ここに来た甲斐があった。

はじめて入った美術館だったので、常設展や初代宇野宗甕(そうよう)の陶芸の特集展などもゆっくり観て来た。とくに安宅コレクションもあり、すばらしいものばかりで、近くに住んでいれば、何度でも来たい美術館だった。いくつか気に入った絵ハガキを買ってきたので、今日はそれを紹介するにとどめたい。”彼岸過ぎまで”が近づいているので(汗)。
国宝 飛青磁花生 (龍泉窯/元13~14世紀)

青花 草花文 面取瓶 (朝鮮18世紀)

重文 青磁鳳凰耳花生 (龍泉窯/南宋時代 12世紀)


































 。大阪で買った塩昆布をつまみで”完敗”じゃない”乾杯”だ。血圧もさらにあがるだろう。
。大阪で買った塩昆布をつまみで”完敗”じゃない”乾杯”だ。血圧もさらにあがるだろう。