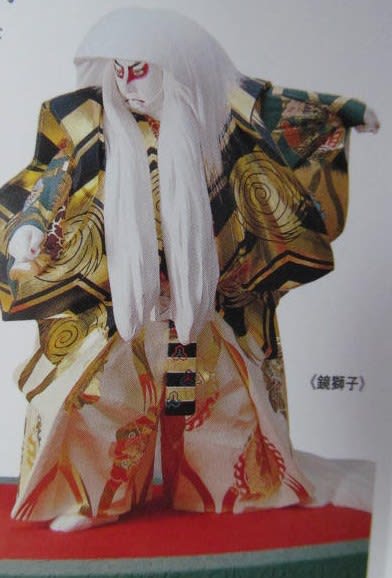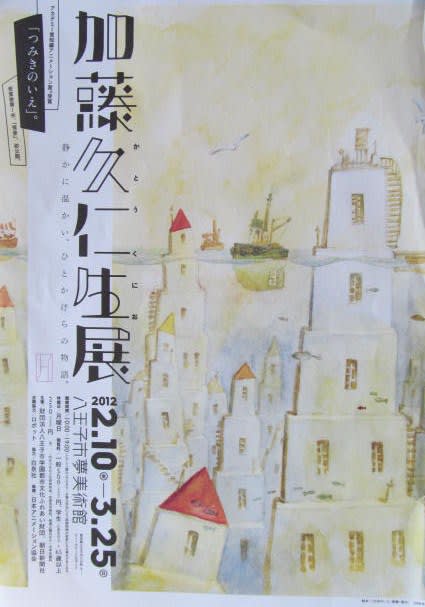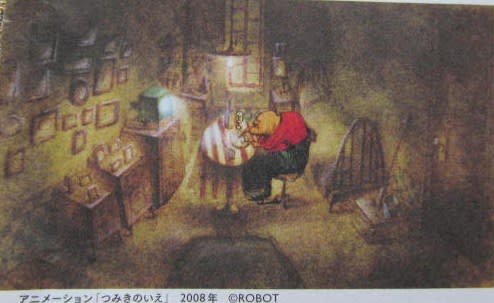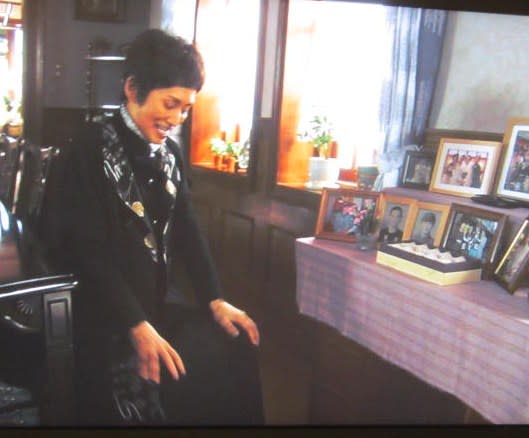科学誌の両雄、英国ネイチャー誌と米国サイエンス誌が、今週、そろって東日本大震災関連の写真を表紙に載せた。ネイチャー誌は”奇跡の一本松”で、”がれきからの復興”の見出しを添えた。そしてサイエンス誌は、原発の燃料用の冷却プールの写真を載せ、Editorialとして、”3月11日から世界が学んだ教訓”の記事を載せている。これほど、今回の大震災とそれに伴う原発事故は、科学が自然に屈した世界史的な大災害であり、大事件であった。今後、原発のような科学技術の暴走は、決して許すことはできない。両誌も自戒を込めての記事であろう。今後、倫理的観点での論文審査基準を強めていってほしい。
3.11の朝散歩はまずお寺さんに向かった。いつもより長く、3.11の追悼のお祈りをした。境内の梅は、名古屋に行っている間に、すかっりほころんでいた。
今日はこれから、友人がメンバーに入っている楽団による、3.11追悼音楽会をききに行く。