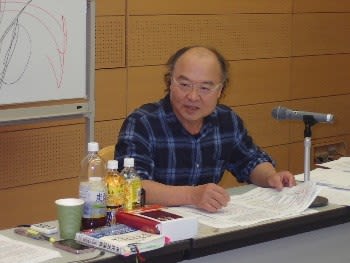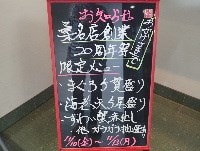「第2回 市民派議員塾」を11月11,12日に名古屋のウイルあいちで開催しました。
1日目の前半の【一般質問・政策編】はわたしが講師を担当し、
後半の【基本の講座】は寺町ともまささんの担当。
ウイルあいちの宿泊棟で夕ご飯を食べながら交流会をして一泊。
2日目はともまささんの【特別上達編】≪法やルールを使いこなす議員は仕事ができる≫。
前日は講師もしたので写真を撮るのをわすれていたのですが、
2日目はレクチャーを真剣に聞いている皆さんの様子を撮りました。



第2回 市民派議員塾:仕事ができる議員になるために、一般質問をスキルアップしよう/
直接民主主義の手法を理解する/ルールを使いこなす議員は仕事ができる》
11月11日(土)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・
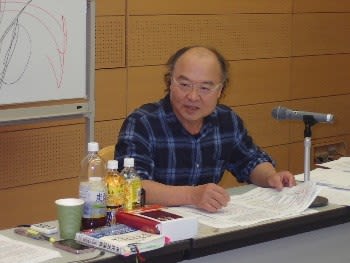
11月12日(日)
【特別上達編】
≪法やルールを使いこなす議員は仕事ができる≫
・直接民主主義の制度・手法を現場で使いこなす、スキルを磨けば仕事ができる議員になれる
・必要な情報の獲得は「何を請求するか」次第
・公開された文書をどのように見るか/「公文書の読み方」
・非公開理由の適用の是非-違法な処分は少なくない/判例との適合
・わがまちの情報公開度を高める/非公開処分の取消/立証責任の転換
・住民監査請求のじっさい~議員がすれば効果てきめん
・1年ルールと怠る事実を使いこなす(一般質問の立論にも最適)
≪実践編/テーマをどう料理し、議論として立論するか≫
・「処分取消の申立の文案」「監査請求の文案」づくりのため、
事前に送付した記入用のフォーマットを提出し、
講師と再検討して実地用に発展させる (一般質問への転用・転換も容易) |
2日間、おつかれさまでした。
応援クリック してね
してね 

 本文中の写真をクリックすると拡大します。
本文中の写真をクリックすると拡大します。
市民派議員塾も終わって、ほっと一息。
名古屋ではコンビニのものばかり買って食べていたので、
三重県まで足をのばして、「すし道場」のお寿司を食べました。

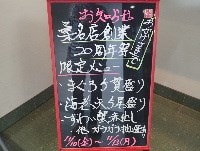
ちょうど「創業20年祭」をしていたので、
限定メニューの「上マグロの5貫盛」を注文。

ぴかぴかの「大トロ、中トロ、赤身、ピントロ、頭身」の5貫で1050円はお徳です。

このお店は、マグロが美味しいので、マグロも何皿か食べました。

市民派議員塾の講座を終えて、ぶじ講師としての務めを果たした
おいしいごぼうびでした(笑)。
最後まで読んでくださってありがとう 
 クリック してね
クリック してね 


 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね 




































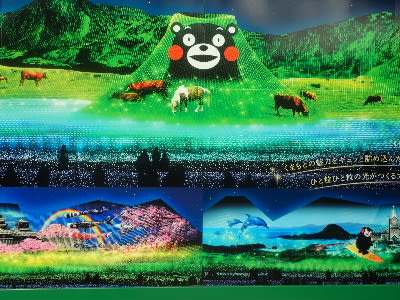

 クリック してね
クリック してね 


 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。