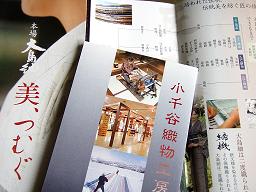
9/1(月)-9/2(火)
四条の京都産業会館で開催されていた
「本場 大島紬フェスティバル」と
「小千谷織物 匠の世界」を見学して来ました。
お客様の同行はなく、社長に引率され姉妹店と
私たちのお店の同僚6名、予定していた月1回の
お店のミーティングを中止してのお勉強会です。
今回のメインは 大島紬。
反物が出来上がるまでにたいへん手間のかかる大島紬ですが、
その工程の一部を、伝統工芸士の方が実演・説明。
体験もさせていただきました。

絣締
絣模様を染めるために専用の締機と呼ばれる機で織締される工程。
デザインにあわせて、まず細かな升目に点を描き入れる図案が作られ
それにそって、この絣締で1パターンごとに筵(むしろ)と呼ばれる
かすり糸を締めたものが織り上げられます。
締機の全体は会場には、運び込まれていませんでした。
それでも実物を拝見したり
丁寧な説明を繰り返ししていただいたのに・・・
???
説明の詳細は、情けなくなるほど理解できませんでした

すり込染
織りあがった筵を染色・加工してかすり糸が出来上がる
のですが、部分的な赤や緑などは、加工の段階で
染まった筵の所定の箇所を部分解きし、そこに
注射針を利用したもので染料をのせこすり付けて彩色します。
私は、これを体験させてもらいました。
適量を細いスペースに均等に染み込ませるのは
結構指先に神経をこめないと。。。


織り:手機
経緯絣及び緯絣の1本1本絣合わせをして
確認しながら織り上げていきます。
実演でかけられていた柄は、画像では無地に見えるほど
とても細かいものでした。
それを妥協なく1本1本の染めを見つめながらきっちり
柄をあわせていく様子は、ため息が出ました。
姉妹店の人が体験をして、ずれてしまった柄を
説明しながら丁寧に直していく姿に、実演ですら
機で創り出す紬に対する熱意と愛情を感じました。
カメラを向けることは出来ませんでしたが、2008年の
新作の大島紬も部門に分かれて陳列され無記名アンケートも
行なわれていました。
すばらしい凝った柄もありましたが私は意識的に男物の
ような出来るだけ細かい連続の単調な柄のものを選びました。
無地ライクで、年齢や時代によって余り左右されない
モノの方が購入層を厚くするような気がして。。。
+ + +
隣あって、開催されていた小千谷織物も、
ついでに観ることが出来ました。
実は私、小千谷縮や小千谷紬が大好きで。。。。ラッキー!!
+ + +
外で働いていると、時には凹むような事もありますが
こうして、物見遊山だけではない刺激が時折あるのが
うれしくて、「ここで、頑張ろう。」と思えます。
わかったような気でいたことを、少し丁寧に教えていただいて
みると、奥深さに驚いてもう少し先まで知りたくなったり・・・
出合ったもの創りにたずさわっている人を
ちょっと羨ましく思ったり・・・
たのしいお勉強会でした。
はげみになります。 ぽちっ、ぷりーず♪



























そうそう、織り機ネタ。お約束ですよね。^m^
待ってます。
キモノを来てフレンチをしゃべる陶芸作りに
いそしむおばあさん。。。
なんか、私もそーゆーのいいなぁ♪
着物着てのお仕事。どんどん詳しくなるし。
しっくり似合ってくるんだろうなー。
浴衣一枚しかもってないけど・・・目指すは着物おばあちゃん。 来るのか?
で、思い出しました。織り機ネタ・・・
今度、Upしてみます^^。