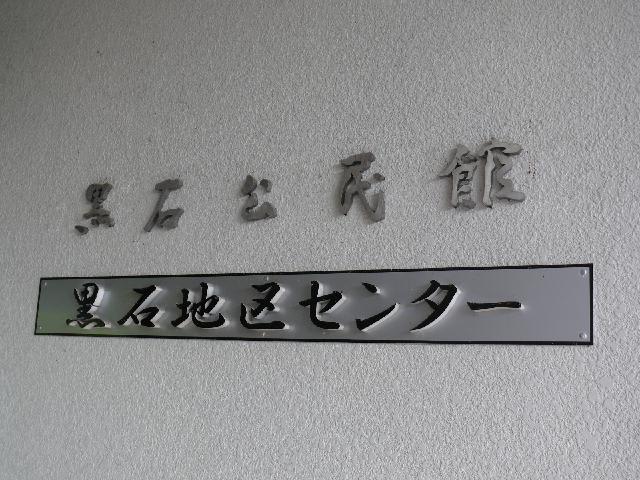2010年8月10日(火)、第2回あづま街道ウォーキング(主催:あづま街道ウォーキング実行委員会(国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、県南広域振興局、奥州市、特定非営利活動法人北上川流域連携交流会)に参加しました。「高清水」から「追分の石」がある所に到着して、いよいよ「江戸時代の追分」を歩きます。
歩き始めた所にオオハンゴンソウ(大反魂草)が咲いていました。





「あづま海道」と呼ばれていた古道は、雨が降った後ということもあり、至るところぐちゃぐちゃ道でした。(奥州市水沢区黒石)

「あづま海道」から自動車が走る現在の道路が見えます。また、古道が使われなくなった後の道路もすぐ下に見えました。



鶴城まで後700m、高清水から1.5kmの地点まで来ました。

このあづま海道には松の木が沢山植えられていたが、戦時中に「松根油」を採ためにほとんど掘り取られてしまったそうです。現在もその掘り跡が幾つも残っていました。

鶴城まで後300m、今回歩く予定のあづま海道終点です。近くには、龍門の滝がありますが、今回は省略。滝の高さはおよそ4~5mあり、舟滝、釜滝、升滝の3層からなっています。ここより少し下流にある曹洞宗藤春院の山号「龍門山」は、この滝の名からつけたといわれています。





もう少しで、終点の黒石公民館に到着します。

黒石公民館到着(16:30頃)
あづま海道<東街道>の由来:(当日配布された冊子より)大和朝廷は、奈良・京都を中心に、全国を統一しようと勢力の拡大を図っていました。そして、大化元年(645)の詔勅(しょうちょく=天皇が公に意思を示す文書)の中で、官道の設置を指令し、やがて国内に東海道、東山道、北陸道などの七つの官道がつくられました。
官道とは、今でいう国道のようなもので、東北地方にのびる道は、北陸道、東山道、東海道の3つのルートがあり、それぞれ鼠ケ関(ねずがせき)、白河の関、勿来(なこそ)の関が終点となり、その先を道の奥地(みちのおく)と呼んでいました。
東海道は、南から伊勢(三重)、尾張(愛知)、相模(神奈川)を経て陸奥(茨城)に至る道で、その延長があづま海(街)道と考えられています。
あづま海(街)道は、陸奥の菊多関、のちの勿来の関(福島)から多賀城国府(宮城県)まで延び、更に、北上川沿いを北上して、岩手の磐井、江刺、稗貫、紫波へと続く道だと考えられています。


黒石公民館のトイレに入っている間に「閉会式」は終わっていました。1班(JR水沢駅東口)と2班(JR水沢江刺駅東口)に分かれてバスに乗り込みます。(バスは17:00少し前に予定通り到着しました。)
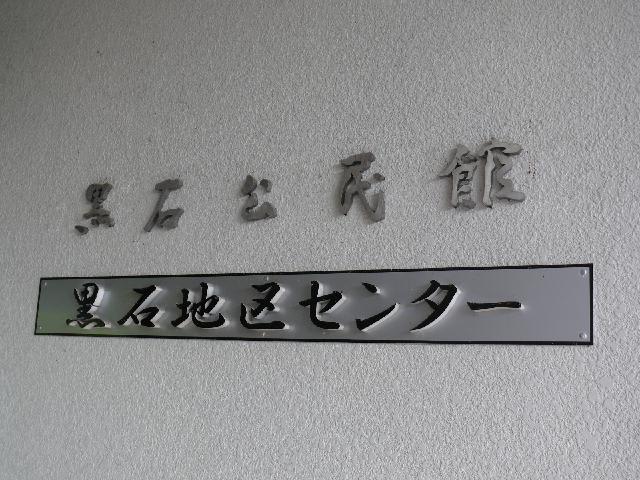



オオハンゴンソウ(大反魂草)/ルドベキア キク科 ルドベキア(オオハンゴンソウ)属 Rudbeckia laciniata
カナダからアメリカ合衆国東部が原産地の耐寒性多年草。性質が強く、広く栽培されたので、山奥の廃村などにも野生化して残っているものが見られる。高さは2m近くもあり、上部で枝分かれして、先端に鮮やかな黄色の花が咲く。花の最盛期は7~8月だが、10月頃まで咲いている。頭花は直径10㎝ほどで、10個ほどの舌状花が1列に並んだ一重咲き。和名の「反魂」とは魂を呼び戻すことで、深裂する葉を幽霊の掌に見立てたことに由来するとされる。日本でよく見られるのは万重咲きの園芸品で、ハナガサギク(花笠菊)と呼ばれている。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑2・夏の花」ほかより]
ルドベキア属 Rudbeckiaの植物は、北アメリカ原産の耐寒性多年草、秋播き1年草。別名:マツカサギク、コーンフラワー。鮮黄色の花弁が水平か反り返り気味に開き、花が終わると中心部が盛り上がってマツカサ状になる。英名をブラックアイドスーザン(黒い目のスーザン)という1年草のヒルタがよく知られるが、ほかにも、多年草のフルギダやオオハンゴンソウ(大反魂草)の八重咲き種・ハナガサギクなどが多数出回る。花期:6~11月(種によって異なる)。用途:庭植え、鉢植え、切り花。管理:日当たりと風通しのよい戸外に置く。鉢土の過湿を嫌うので表面がよく乾いたら水やりするが、水切れすると葉が傷むので注意。ひと通り花が咲いたら3分の2ぐらい切り戻す。[西東社発行「知りたい花の名前がわかる 花の事典(金田初代・文、金田洋一郎・写真)」より]