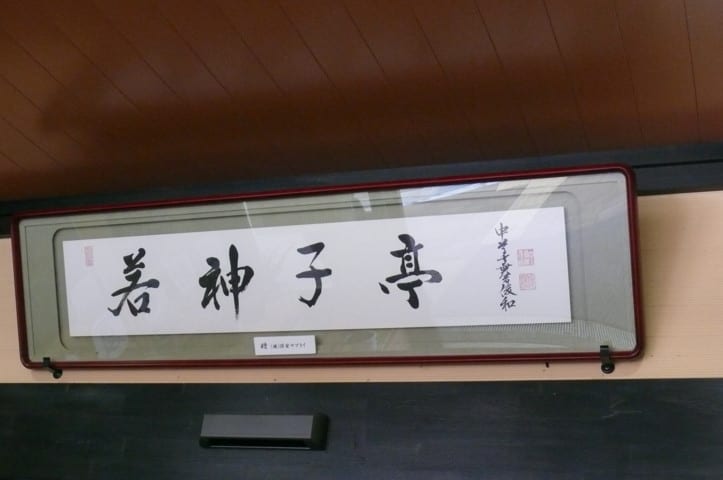2012年10月7日(日)、「野村胡堂・あらえびす記念館」(紫波郡紫波町字彦根)に行きました。出入り口の道の傍に植えられているヤマボウシ(山法師)の実が赤く色づいていました。果実の数は昨年と比べるとひんの少しだけでした。
http://kodo.or.tv/kodo/index.html [野村胡堂・あらえびす記念館(公式ホームページ)]









ヤマボウシ(山法師) ミズキ科 ミズキ(コーナス)属 Cornus kousa
別名:ヤマグワ(山桑)。各地の山野に生える落葉小高木~高木。高さは普通5~10m、大きいものは15mになる。樹皮は赤褐色(暗朱紅色)で丸い鱗片となって剥がれる。葉は対生し、長さ4~12㎝の楕円形~卵状楕円形で、縁はやや波打つ。側脈は4~5対。
6~7月、小さな花が20~30個集まった球形の頭状花序をつくる。白い花弁のように見えるのは4個の総苞片で良く目立つ。長さは3~6㎝、その中心に小さな緑色の花が多数球状に集まっている。果実は集合果で直径1~1.5㎝の球形。10月頃に赤く熟し、食べられる。実は甘酸っぱくておいしい。
総苞片が淡紅色の品種をベニヤマボウシ(紅山法師)f.roseaという。用途:庭木、器具材。分布:本州、四国、九州、朝鮮、中国、台湾。[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・日本の樹木」&同「山渓ポケット図鑑2・夏の花」より]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=35776377&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市室根町のヤマボウシ(山法師)の実]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=38224661&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:紫波郡紫波町「野村胡堂・あらえびす記念館のヤマボウシ(山法師)の実]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=40431146&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市「道の駅・厳美渓」のヤマボウシ(山法師)の花]