


(下)10月27日(土)撮影。




(上と下)2012年10月27日(土)撮影。

2012年10月27日(土)、特定非営利活動法人 野村胡堂・あらえびす記念館協力会:主催。岩手日報社、盛岡タイムス:後援の野村胡堂生誕130年記念事業・あらえびす特別講演会が、野村胡堂・あらえびす記念館ホールで行われましたので、妻と一緒に聞きに行ってきました。(定員100名)
記念館の庭に植えられているメタセコイア/アケボノスギ(曙杉)が、手が届くような高さのところに果実を沢山つけていました。
http://kodo.or.tv/guide/index.html [野村胡堂・あらえびす記念館(公式ホームページ)]
http://araebisu.exblog.jp/ [野村胡堂・あらえびす記念館:野村胡堂生誕130年記念事業・あらえびす特別講演会 のお知らせ]


この講演会は、野村胡堂・あらえびす記念館名誉館長の高橋克彦氏と内館牧子氏の特別対談で、「創作ということ」という題で対談されました。(13:30~15:00)。
対談終了後に、両氏の著書のサインセールが行われるというので、大勢の人が著書を購入していました。
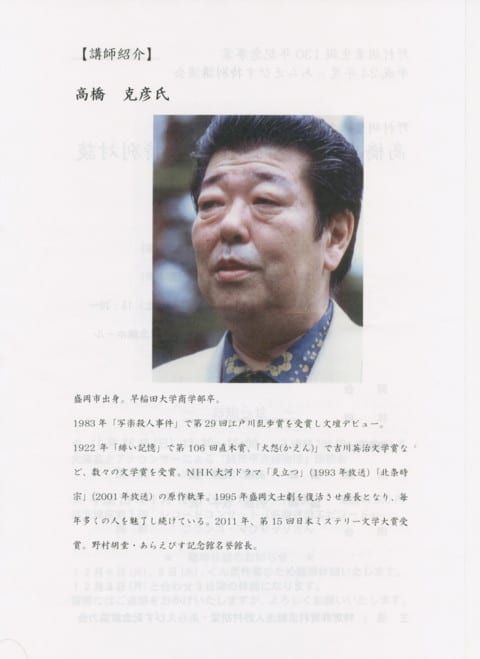








(上と下)2012年10月27日(土)撮影。

メタセコイア スギ科 メタセコイア属 Metasequoia glyptostroboides
別名(和名):アケボノスギ(曙杉)、イチイヒノキ。英名:Dawn Redwood。1945年に中国の四川省(揚子江の奥地)で発見された1属1種の落葉高木(針葉樹)。それまで化石しか知られていなかったので、「生きた化石」として有名になった。幹は真っ直ぐに伸び、整った円錐形の樹形になる。原産地では高さ35m、直径2.5mになるものがある。公園などに植えられているが、材がもろく、強風で折れやすい。
樹皮は赤褐色で縦に裂け、薄く剥がれる。枝や葉は対生し、小枝は秋に葉と一緒に落ちる。葉は長さ約2㎝の線形で対生し、秋にはレンガ色になって落ちる。花期は2~3月。雌雄同株。雄花序は黄褐色で長く垂れ下がる。雌花は緑色。球果は長さ2~2.5㎝の卵状球形で、10月頃成熟して褐色になる。種子は倒卵j形で幅の広い翼がある。良く似たラクウショウ(落羽松)Taxodium distichumは葉が互生する。用途:公園樹、並木、建築・器具材、薪炭。
[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑3・秋の花」&同「山渓カラー名鑑・日本の樹木」より]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=36658960&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市大手町のメタセコイア/アケボノスギ(曙杉)]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=36131110&blog_id=82331[peaの植物図鑑:奥州市江刺区岩谷堂のメタセコイア/アケボノスギ]

























