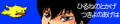脳死…脳幹を含めた全脳機能が完全に失われ再生不能となった状態。脳死をもって「人間の死」とみなす見解もあるが、一致をみない。(大辞林)
今日は都議選投票日
政治の世界から離れると、とたんになんだかホントに、候補者が「遠くのなにやってるんだかわからない人たち」に感じます。
私はちょうど去年の今頃、7年間勤めた政治家の事務所を退職しました。
在職中は、政治の側にいたし、ある時期には、議会に提出する法案の作製にかかわる会議にも代議士の代理で出席して、内容のメモをとって伝えるというようなこともやっていたので、いわば、政治の最先端、新聞が報道するよりも前のところで仕事をしていた時代もありました。
私の代議士事務所の経験の中で、いちばん印象に残っていることをひとつ選ぶとしたら、「臓器移植」に関する法案の投票の場面です。
「脳死を人の死とするか」
これは、政党、政策を超えた、「人間の死」「人間の尊厳」にかかわるとても難しい問題だったと思います。私も、投票に直接は関れないにしても、真剣に考えました。
脳死に至った人は、再び生命活動に戻ることはできない。「脳死を人の死とする」ことを法律で定義することによって、心臓移植を始めとする、多くの臓器移植の道が開かれて、大勢の命を救うことができる。日本の医療サイドからも、技術的な面での受け入れ体勢はかなり整っていて、「脳死を人の死とする」決定が、今や遅しと待ち望まれていました。
一方、脳死状態とは、身体もあたたかく、心臓は鼓動している。これを「死」といえるのか? 90年代初頭に「脳死臨調」が立ち上げられており「人の死」について真剣な議論が重ねられていました。哲学者 梅原 猛 氏も脳死臨調の一員で、脳死を人の死とすることに反対していた少数派でした。私は、議員会館で彼の講演を聴く機会を得ました。
感動的な講演でした。私の心情にいちばん近いところを語っていらした方だと思いました。
「生と死」のはっきりとした境界線って、ほんとうにあるんだろうか?
あるとしても、誰がそれを決めるのでしょうか?
今では、あの当時の経緯によって、「脳死」と「心停止」場合によって、いずれかが「人の死」と認められるという、妙な状態になっています。
私は、かつての夫の父親の死に立ち会いました。
「…反応がないようなので、御臨終です」
私が義父のところに駆けつける以前に義父の心臓は、いったん停止したそうです。それから心臓マッサージや、薬の投与で再び心臓の鼓動は始まりましたが、意識は戻ることがありませんでした。
臨終の宣告を受ける直前にも、医師は、心臓マッサージを何度か試みて下さり(これは医療行為というより、倫理的な行為と、その時私は思いました)、そのたびに少し復活するのだけれど、すぐに乱れていく…というのを何度か繰り替えし、そして、ついに
「反応がないようなので…」に至るのです。
「心停止」を人の死とする…という定義に従った「臨終」の宣告だったと思います。
人の死を法律で定義するって、どうでしょうか。
もし、自分がそれを決める権限が与えられているとしたら…
しかし、「死」とはどんな状態か、法律で定義されていなければ、様々な現場が混乱してしまう。「死の定義」これは法律的に絶対に必須事項です。
「臓器移植法案」に関しては、殆どの政党が「党議拘束」を外し、自由投票となりました。議員ひとりひとりが「人の死」の鍵を握るのです。
今日は都議選投票日
政治の世界から離れると、とたんになんだかホントに、候補者が「遠くのなにやってるんだかわからない人たち」に感じます。
私はちょうど去年の今頃、7年間勤めた政治家の事務所を退職しました。
在職中は、政治の側にいたし、ある時期には、議会に提出する法案の作製にかかわる会議にも代議士の代理で出席して、内容のメモをとって伝えるというようなこともやっていたので、いわば、政治の最先端、新聞が報道するよりも前のところで仕事をしていた時代もありました。
私の代議士事務所の経験の中で、いちばん印象に残っていることをひとつ選ぶとしたら、「臓器移植」に関する法案の投票の場面です。
「脳死を人の死とするか」
これは、政党、政策を超えた、「人間の死」「人間の尊厳」にかかわるとても難しい問題だったと思います。私も、投票に直接は関れないにしても、真剣に考えました。
脳死に至った人は、再び生命活動に戻ることはできない。「脳死を人の死とする」ことを法律で定義することによって、心臓移植を始めとする、多くの臓器移植の道が開かれて、大勢の命を救うことができる。日本の医療サイドからも、技術的な面での受け入れ体勢はかなり整っていて、「脳死を人の死とする」決定が、今や遅しと待ち望まれていました。
一方、脳死状態とは、身体もあたたかく、心臓は鼓動している。これを「死」といえるのか? 90年代初頭に「脳死臨調」が立ち上げられており「人の死」について真剣な議論が重ねられていました。哲学者 梅原 猛 氏も脳死臨調の一員で、脳死を人の死とすることに反対していた少数派でした。私は、議員会館で彼の講演を聴く機会を得ました。
感動的な講演でした。私の心情にいちばん近いところを語っていらした方だと思いました。
「生と死」のはっきりとした境界線って、ほんとうにあるんだろうか?
あるとしても、誰がそれを決めるのでしょうか?
今では、あの当時の経緯によって、「脳死」と「心停止」場合によって、いずれかが「人の死」と認められるという、妙な状態になっています。
私は、かつての夫の父親の死に立ち会いました。
「…反応がないようなので、御臨終です」
私が義父のところに駆けつける以前に義父の心臓は、いったん停止したそうです。それから心臓マッサージや、薬の投与で再び心臓の鼓動は始まりましたが、意識は戻ることがありませんでした。
臨終の宣告を受ける直前にも、医師は、心臓マッサージを何度か試みて下さり(これは医療行為というより、倫理的な行為と、その時私は思いました)、そのたびに少し復活するのだけれど、すぐに乱れていく…というのを何度か繰り替えし、そして、ついに
「反応がないようなので…」に至るのです。
「心停止」を人の死とする…という定義に従った「臨終」の宣告だったと思います。
人の死を法律で定義するって、どうでしょうか。
もし、自分がそれを決める権限が与えられているとしたら…
しかし、「死」とはどんな状態か、法律で定義されていなければ、様々な現場が混乱してしまう。「死の定義」これは法律的に絶対に必須事項です。
「臓器移植法案」に関しては、殆どの政党が「党議拘束」を外し、自由投票となりました。議員ひとりひとりが「人の死」の鍵を握るのです。