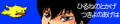フラミンゴの女性メンバー3人で、「風の鈴」というグループをつくっています。
ピアノとコーラスで、童謡、日本歌曲、なつメロ…などを高齢者の福祉施設で歌う、ボランティアのグループ。
来週、そのミニコンサートなので、今日は練習に集まりました。
何度かミニコンサートをやりましたが、その度に、先人達の「名曲」の素晴らしさを再認識します。
子供の頃、耳にした曲、学校の音楽の時間に習った曲、その当時は、意味もわからず、感動もなく、なーんとなく歌っていた曲を、今になってくちずさむと、ふっか~~~い味わいを味わうことができます。
ぜひみなさん、声に出してうたってみてください。
「故郷」「我は海の子」「砂山」「赤とんぼ」…などなど、私の大好きな曲です。
まだまだあります。
今回のコンサートの中で、「荒城の月」をやることになりました。
リーダーのリクエストです。
そうそう、このグループのリーダーはピアニストのまゆこちゃん。私達は「バンマス」と呼んでいます(^_^;)
「ね~~この曲長いし、高音がツラいし、せめて2番までにしようよー」…と私。
実は、この曲、あまり思い入れがありませんでした。
PCでの連絡掲示板にも、「荒城」ってイッパツで出てこないし、
「工場の月」などと平然と間違えていたりして(^_^;)
「そうですか~、じゃっ、まあ一応そーいうことで…」と、バンマス。
荒城の月
瀧 廉太郎 作曲 土井 晩翠 作詞
春高楼の 花の宴
巡る盃 かげさして
千代の松が枝 わけ出でし
昔の光 いまいずこ
秋陣営の 霜の色
鳴きゆく雁の 数見せて
植うる剣に 照りそいし
昔の光 いまいずこ
いま荒城の 夜半の月
替わらぬ光 誰がためぞ
垣に残るは ただ葛
松に歌うは ただ嵐
天上影は 替らねど
栄枯は移る 世の姿
写さんとてか 今もなお
嗚呼荒城の 夜半の月
このうたには、こんな美しい3、4番があったのか…
これはもう、ぜひとも歌いたい…と思いました。ツラくてもキツくても。俄ではありますが、節酒、発生練習で、がんばろう!!
自分の曲は自分にキーを合わせてつくる。
イタリア古典歌曲もスタンダードジャズも、自由に移調できるのに、オペラと日本歌曲は、キイが決まっています。
でもまっ、それはコンサートでのハナシで、なにも、一般の人がこれを絶対に二短調でうたわなくてはいけないってことはありません(^_^;)
ぜひ、口ずさんでみてくださいませ。
そうすれば、私がごちゃごちゃ書かなくてもわかっていただけます。
子供の頃、私の祖母は、中山晋平の「砂山」を子守唄がわりに歌ってくれました。
その頃はもちろん曲の名前もまして作曲者も知りません。
「海は荒海 向こうは佐渡よ 雀鳴け鳴けもう日が暮れる…」
この哀愁にみちたメロディーが、なんとなく好きだった…
10代後半になって、日本歌曲集の中に、この曲をみつけたとき、亡くなった祖母の思いでが突然鮮やかに蘇りました。夏の夜、蚊帳の中、夜中に目覚めて、喉が乾いたという私に飲ませてくれた麦茶、そのときのグラスの群青色の細い線の模様…それらが全部どどど~~っっ!!とくるのです。
まるで祖母に突然再会したような…懐かしさと嬉しさ。
これが「うた」が持っている力や優しさなのでしょう。
自分のつくった曲で自分を表現する…だけでなく、先人たちの名作を歌い継いでいけることも、ミュージシャン冥利につきます。
でも、祖母はミュージシャンだった訳じゃありません。
ほんとにうたい継いで伝えることができるのは、子供を、孫を愛おしむ気持ちなんでしょうねぇ…
ピアノとコーラスで、童謡、日本歌曲、なつメロ…などを高齢者の福祉施設で歌う、ボランティアのグループ。
来週、そのミニコンサートなので、今日は練習に集まりました。
何度かミニコンサートをやりましたが、その度に、先人達の「名曲」の素晴らしさを再認識します。
子供の頃、耳にした曲、学校の音楽の時間に習った曲、その当時は、意味もわからず、感動もなく、なーんとなく歌っていた曲を、今になってくちずさむと、ふっか~~~い味わいを味わうことができます。
ぜひみなさん、声に出してうたってみてください。
「故郷」「我は海の子」「砂山」「赤とんぼ」…などなど、私の大好きな曲です。
まだまだあります。
今回のコンサートの中で、「荒城の月」をやることになりました。
リーダーのリクエストです。
そうそう、このグループのリーダーはピアニストのまゆこちゃん。私達は「バンマス」と呼んでいます(^_^;)
「ね~~この曲長いし、高音がツラいし、せめて2番までにしようよー」…と私。
実は、この曲、あまり思い入れがありませんでした。
PCでの連絡掲示板にも、「荒城」ってイッパツで出てこないし、
「工場の月」などと平然と間違えていたりして(^_^;)
「そうですか~、じゃっ、まあ一応そーいうことで…」と、バンマス。
荒城の月
瀧 廉太郎 作曲 土井 晩翠 作詞
春高楼の 花の宴
巡る盃 かげさして
千代の松が枝 わけ出でし
昔の光 いまいずこ
秋陣営の 霜の色
鳴きゆく雁の 数見せて
植うる剣に 照りそいし
昔の光 いまいずこ
いま荒城の 夜半の月
替わらぬ光 誰がためぞ
垣に残るは ただ葛
松に歌うは ただ嵐
天上影は 替らねど
栄枯は移る 世の姿
写さんとてか 今もなお
嗚呼荒城の 夜半の月
このうたには、こんな美しい3、4番があったのか…
これはもう、ぜひとも歌いたい…と思いました。ツラくてもキツくても。俄ではありますが、節酒、発生練習で、がんばろう!!
自分の曲は自分にキーを合わせてつくる。
イタリア古典歌曲もスタンダードジャズも、自由に移調できるのに、オペラと日本歌曲は、キイが決まっています。
でもまっ、それはコンサートでのハナシで、なにも、一般の人がこれを絶対に二短調でうたわなくてはいけないってことはありません(^_^;)
ぜひ、口ずさんでみてくださいませ。
そうすれば、私がごちゃごちゃ書かなくてもわかっていただけます。
子供の頃、私の祖母は、中山晋平の「砂山」を子守唄がわりに歌ってくれました。
その頃はもちろん曲の名前もまして作曲者も知りません。
「海は荒海 向こうは佐渡よ 雀鳴け鳴けもう日が暮れる…」
この哀愁にみちたメロディーが、なんとなく好きだった…
10代後半になって、日本歌曲集の中に、この曲をみつけたとき、亡くなった祖母の思いでが突然鮮やかに蘇りました。夏の夜、蚊帳の中、夜中に目覚めて、喉が乾いたという私に飲ませてくれた麦茶、そのときのグラスの群青色の細い線の模様…それらが全部どどど~~っっ!!とくるのです。
まるで祖母に突然再会したような…懐かしさと嬉しさ。
これが「うた」が持っている力や優しさなのでしょう。
自分のつくった曲で自分を表現する…だけでなく、先人たちの名作を歌い継いでいけることも、ミュージシャン冥利につきます。
でも、祖母はミュージシャンだった訳じゃありません。
ほんとにうたい継いで伝えることができるのは、子供を、孫を愛おしむ気持ちなんでしょうねぇ…