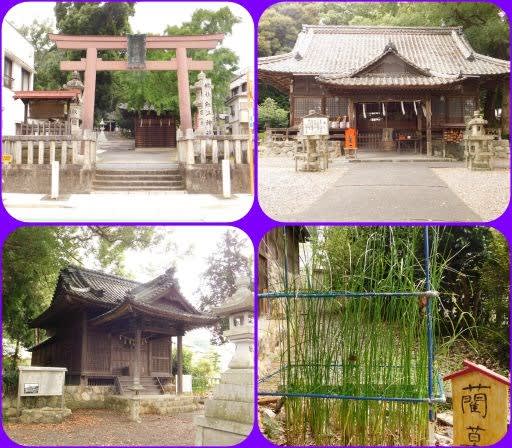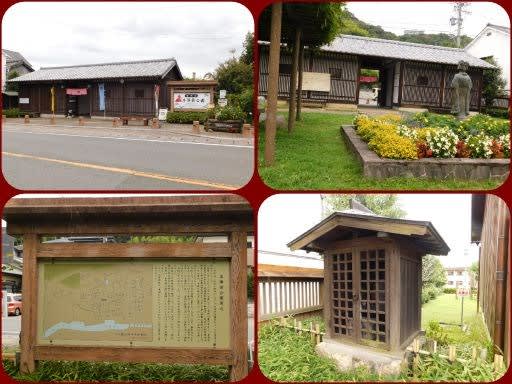今年も家庭菜園のショウガが採れました。(上の小画像参照)
さっそく生姜の佃煮作りに挑戦です。
掘り起こしたショウガを根と葉を切り落としブラシ等で、土や余分な皮部分を落としきれいにします。
整理後のショウガは約800gとなりました。


次の作業は、スライサーと包丁を使って細かく切り分け、それを桶に入れ塩を一つかみ加え混ぜ合わせます。30分ほどなじましてから水洗い。それを10~15分湯がき、ざるに挙げ水気を切ります。


いよいよここからが本番。煮詰めの開始です。
その前に調味料を作ります。使った品名は、砂糖、しょうゆ、みりん、だしの素、めんつゆ、日本酒及び昆布と干しシイタケです。(使用量は省略)
昆布と干しシイタケは先に水でもどしておきます。
大き目の鍋に、水気を切った生姜と上記の調味料を加え、常時かき混ぜながら約25分間煮ていきます。水気が少なくなったころにさらにかつをぶしと白ごまを加え、煮詰めて完成となりました。

(煮詰めの順を左上から四コマにしました)
冷まして完成です。早速パックに詰めました。

四パックに分けて半分は冷凍保存しました。早く食した方がいいのですが冷凍すれば半年間は保存できます。(昨年事例)

さっそく生姜の佃煮作りに挑戦です。
掘り起こしたショウガを根と葉を切り落としブラシ等で、土や余分な皮部分を落としきれいにします。
整理後のショウガは約800gとなりました。


次の作業は、スライサーと包丁を使って細かく切り分け、それを桶に入れ塩を一つかみ加え混ぜ合わせます。30分ほどなじましてから水洗い。それを10~15分湯がき、ざるに挙げ水気を切ります。


いよいよここからが本番。煮詰めの開始です。
その前に調味料を作ります。使った品名は、砂糖、しょうゆ、みりん、だしの素、めんつゆ、日本酒及び昆布と干しシイタケです。(使用量は省略)
昆布と干しシイタケは先に水でもどしておきます。
大き目の鍋に、水気を切った生姜と上記の調味料を加え、常時かき混ぜながら約25分間煮ていきます。水気が少なくなったころにさらにかつをぶしと白ごまを加え、煮詰めて完成となりました。

(煮詰めの順を左上から四コマにしました)
冷まして完成です。早速パックに詰めました。

四パックに分けて半分は冷凍保存しました。早く食した方がいいのですが冷凍すれば半年間は保存できます。(昨年事例)