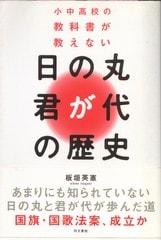心の不安定を抱えながら「憂うつ」な毎日を過ごしてしまっている人は、ただ単に「運動不足」なだけかも知れません。と言うのも、体を動かすことが脳の活動に大きな影響を及ぼすからです。
●「憂うつ」になる仕組み
不安、悲しい、憂うつといった感情はどうやって生まれるのでしょうか。
それは、海馬(かいば)と扁桃体(へんとうたい)と呼ばれる脳部位の連携プレーにより生まれます。海馬は扁桃体に対して、どんな時にどんな感情を生みだすのかという情報を提供する器官。その情報を基に、扁桃体で感情が認知されます。
ストレス状態が続くと、海馬は、「不安」、「つらい」「悲しい」と言った感情を生み出す情報を扁桃体へ送り続けるため、だんだん気分が落ち込み、「憂うつ」な状態へ入ってしまうのです。
●ストレスで脳機能が低下
この海馬は、ストレスに弱いため、精神的負担がかかると機能が低下してしまいます。極度のストレス状態で、うつ病になると海馬は萎縮(いしゅく)し、神経細胞まで死滅してしまいます。
海馬は欲望やストレスをつかさどる視床下部の暴走をとめる役割もあります。つまり、海馬を鍛えることで、ストレスに耐えられる強い脳を作ることができるのです。
この海馬を活性化させるのは、そう難しくはありません。その究極のレシピは「運動」。運動により分泌される神経伝達ホルモンが海馬を刺激し、脳神経そのものが増えるのです。
運動をさせたマウスと運動なしのマウスを使った実験によると、運動していたマウスの脳では、ストレスのかかった状態で、海馬を刺激する脳神経細胞の活動が非常に活発だったことが確認されました。
マウスを使った実験が示すとおり、運動によって海馬の機能が活性化され、ストレスにあっても余裕を持って反応できるようになるのです。
効果があるのは、極度の運動より、スローペースの運動だそうです。速く歩く速度ぐらいのジョギングが最適とか。気分が優れず「憂うつ」な人は、毎日少し体を動かしてみてはいかがですか。
※当記事は、ハイブリッド翻訳のワールドジャンパー(http://www.worldjumper.com)の協力により執筆されました。
鬱病の医学的な解明が、総て出来ている訳ではないと思います。1日一時間以上の散歩が、心の安定に役立つと『病は気から』の著者慶応大学医学部講師の故阿部正先生は言われました。 今の体温以上に上がる気温では、 熱中症になりますので、気温が安定するまで待つ方が良いと思います。
「病いは気から」の医学
阿部正著
価格:(税込)
発売日:










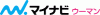





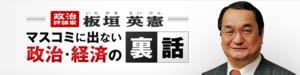


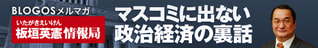
 6月開催の勉強会がDVDになりました。
6月開催の勉強会がDVDになりました。