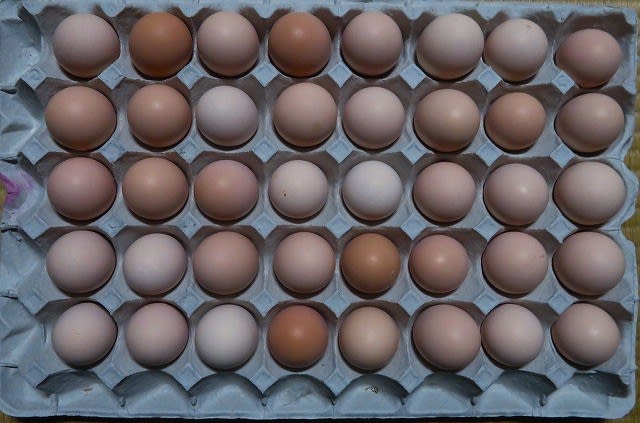お正月になってまもなく、近所からことしも ヤマノイモ(自然薯)の芋汁をいただく。さっそく麦飯に芋汁をかけて飲み込むようにいただく。こだわりがあるようですり鉢で何度もすり潰すという。だから粒が感じられないほど細かくスープのようにのど越しがいい。昨年の年末には、里芋をダンボールいっぱいにもらったばかりだった。

芋汁をいただいたたとき、たまたま掘り出したキクイモで唐揚げを料理したばかりだった。なんとタイミングがいいことか。酒・ニンニク・醤油・片栗粉・トウバンジャン・ごま油の中にキクイモを投入する。それをサラダ油の中に少しずついれて揚げていく。レシピどおりやらない・やれないのがオラの流儀だ。でも面白いようにキクイモの唐揚げができていく。食べてみると衣はカリカリ中身はホクホクで甘い。これなら喜んでもらえそうだと芋汁への返礼品に化けた。

そういえば、10月の半ばにキクイモを試掘してみて、まだ収穫には早いと様子をみることにした。成長が早いのでいつもびくびくしながら大量に出ませんようにとも思いつつその収穫を期待する。

12月上旬になってついに本格的な収穫となる。久しぶりのキクイモの収穫だ。かつては食べきれなくて困っていたが、冬場の食材が不足気味だったので栽培を再開したのだった。いつもは凍えながら水洗いして泥を落としていたが、今回は陽当たりの良い所へ移動してやったので寒さに震えることはクリアする。そしてこれら大量の収穫物は糖尿病予備軍兵士に贈られることになった。さて、そろそろ次の収穫を急がないと霜にやられてしまう。体には抜群のキクイモだが手間がかかるのでスーパーなどでは市販されないことが多い。キクイモさまさまになりそうな冬になりそうだ。