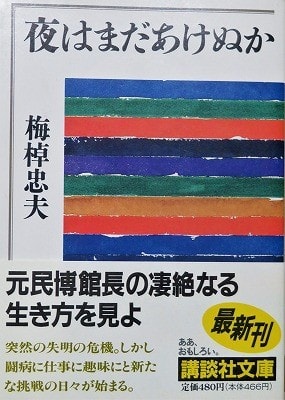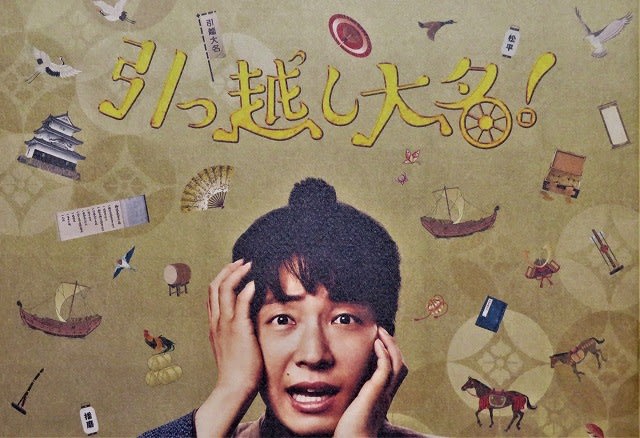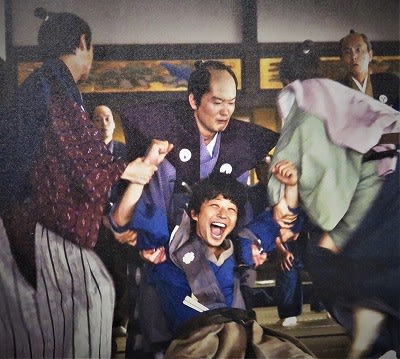「もし自分が失明したら生きる望みはなくなっちゃうよなー」というようなことをひょいと思うことがある。そんなとき、日本の文化人類学の先駆者の梅棹忠夫さんが64歳(1986年)で失明したことを知る。国立民族学博物館の創立にかかわり、1974年初代館長に就任してからまもなくの突然の原因不明の失明だった。そのあらましを口述筆記であらわしたのが『夜はまだあけぬか』(講談社文庫、1995.1)だった。

梅棹忠夫と言えば、国語の教科書に「モゴール族探検記」から抜粋した平易な文章があったのをなんとなく記憶しているが、中身は覚えていない。氏は闘病・リハビリを続けながらも自らの著作を次々発刊していく。その過程は驚嘆という言葉しか浮かばない。普通だったら、暗黒の世界に精神的に追い込まれて自暴自棄になるか、死を選ぶかしかないようにも思える。そこを梅棹さんは学者らしく自分が置かれた境遇を受け入れつつ、周りの人の援助も糧として、自らの著作の「知的生産」を実現していく。

打つ手なしの退院だったが、梅棹さんを精神的・実務的に支えたのは妻であり、職場の同僚でもあった。そしてそれ以上に、自分の著作をまとめていくという見えないなりの作業が本人を救ったのではないかと思う。
わが人生は終わったかと漆黒の闇の中でも「目は見えなくても、いろいろやってみると道はひらけてくるものである」という境地に達する。さらに「さいわいなことにわたしの精神は比較的バランスをうしなうこともなく、病状とともにいまは安定している。また、目以外はしごく健康である。以前にもまして、気力の充実を感じている」と言い切る。
この精神力は、若いときに登山に明け暮れ、辺境の見知らぬ外国へ調査に行くパワーに裏付けられたものを感じる。西洋と東洋という分類にも異議申し立てを提起したような稀代の世界的学者の面魂がここにあった。