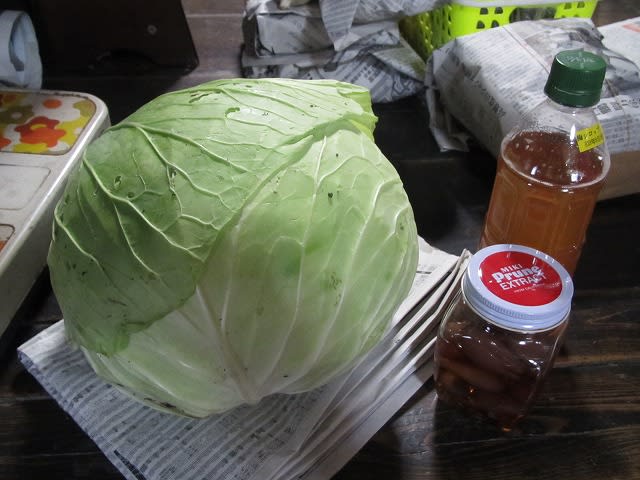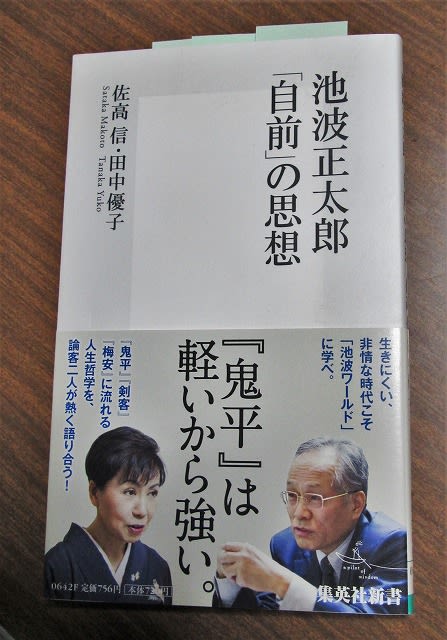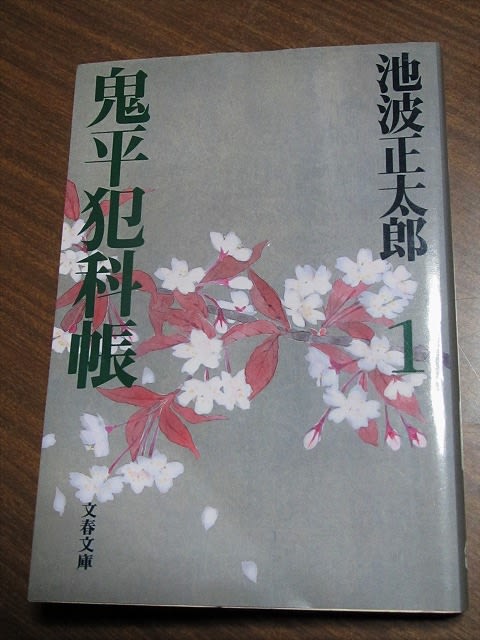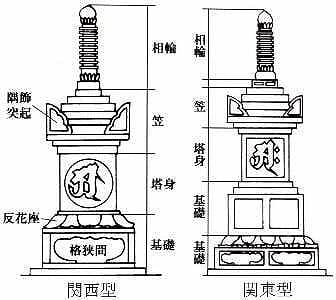夜になるとわが家に突入してくる蛾が多くなった。
その目立つ蛾は、尺取虫として身近な「シャクガ科」の蛾だった。
よく目にする「ヒョウモンエダシャク」の豹紋は、豹柄の目立つデザインで自分を守ろうというのだろうか。

シジミチョウより小さめの「シロオビアオシャク」もよく侵入してくる蛾だ。
緑の蛾は珍しいが、いろいろなパターンのデザインがあるようだ。
そのなかでこのアオシャクは地味なデザインだった。

地が真っ白で帯が茶色の「シロツバメエダシャク」もときどき目撃する。
この尾状突起がツバメの尾に似ているところからツバメとネーミングしているが、ウーン。
デザインはジャパンを感じる慎ましさがいいね。
きょうは終日、畝立てに専念。
小さな畝を6か所形成。
ぐっしょり濡れてシャワーを浴びる。
その目立つ蛾は、尺取虫として身近な「シャクガ科」の蛾だった。
よく目にする「ヒョウモンエダシャク」の豹紋は、豹柄の目立つデザインで自分を守ろうというのだろうか。

シジミチョウより小さめの「シロオビアオシャク」もよく侵入してくる蛾だ。
緑の蛾は珍しいが、いろいろなパターンのデザインがあるようだ。
そのなかでこのアオシャクは地味なデザインだった。

地が真っ白で帯が茶色の「シロツバメエダシャク」もときどき目撃する。
この尾状突起がツバメの尾に似ているところからツバメとネーミングしているが、ウーン。
デザインはジャパンを感じる慎ましさがいいね。
きょうは終日、畝立てに専念。
小さな畝を6か所形成。
ぐっしょり濡れてシャワーを浴びる。