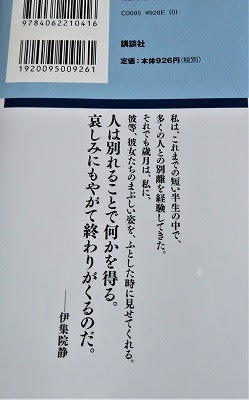『中村屋のボース』に引き続き、オイラが注目している著者の中島岳志『リベラル保守宣言』(新潮文庫、2016.1)を読み終える。「リベラル」とは、自由という意味ばかりではなく「寛容」を是とする意味も包含するという。それは、「人間の理性や知性には限界がある」ことで、「世界は永遠に不確実で、不透明」であるという認識に基礎を置く。それが保守主義の本義だという。

したがって、大国とテロに翻弄されている世界の現在、「熱狂に熱狂しないこと」が重要であり、「いま社会に必要なことは、<熱狂>ではなく<平衡>や<葛藤>」であり、それこそが保守の中庸的主体の資質だと指摘する。

「デモクラシーを原理化していくと、横並びにしようとする<平等への隷属>に陥る傾向があり」、それは「人々を<平準化>する権力を生み出し、<均一化>したマス(大衆)による<多数者の専制>を起こす」という説を紹介し、デモクラシーのもつ危うさの一面を指摘する。戦前のファシズムや日本の軍国主義化がその証左だ。オイラも進歩的な西洋思想・民主主義の限界を感じているところだったので納得のいくところだ。

その意味で、「平成」が終わるきょう、連日のマスメディアの報道の過熱ぶりが気になって仕方がない。現実の日本の「保守」は、神道推進、原発再稼働、野党への切り崩しなど膨大な権力との共同行使によって、「同質化した大衆」の産み出しに成功していることは言うまでもない。
本書も著者が橋本徹・維新の会批判を書いていたため、予定していたNTT出版社の「忖度」によって刊行できなかった経過もあった。

「結び」の部分はやや急ぎ過ぎたきらいはあるが、保守主義の本来的な思想のまともさは伝わったし、納得もいく。そこであえて言えば、「リベラル<革新>宣言」というものもあるべきではないかと思う。
フランス革命の暴力的な市民革命は今日の「民主主義」の礎となったが、もっと根源的な「革新」の潮流というものも描くべきではないかと思えた。「改良主義」と揶揄されてきた革新的な政治家・学者をもっと発掘すべきだとこのごろ痛感する。中島氏のほとばしる情念が日本を洗濯してくれることを期待している。

したがって、大国とテロに翻弄されている世界の現在、「熱狂に熱狂しないこと」が重要であり、「いま社会に必要なことは、<熱狂>ではなく<平衡>や<葛藤>」であり、それこそが保守の中庸的主体の資質だと指摘する。

「デモクラシーを原理化していくと、横並びにしようとする<平等への隷属>に陥る傾向があり」、それは「人々を<平準化>する権力を生み出し、<均一化>したマス(大衆)による<多数者の専制>を起こす」という説を紹介し、デモクラシーのもつ危うさの一面を指摘する。戦前のファシズムや日本の軍国主義化がその証左だ。オイラも進歩的な西洋思想・民主主義の限界を感じているところだったので納得のいくところだ。

その意味で、「平成」が終わるきょう、連日のマスメディアの報道の過熱ぶりが気になって仕方がない。現実の日本の「保守」は、神道推進、原発再稼働、野党への切り崩しなど膨大な権力との共同行使によって、「同質化した大衆」の産み出しに成功していることは言うまでもない。
本書も著者が橋本徹・維新の会批判を書いていたため、予定していたNTT出版社の「忖度」によって刊行できなかった経過もあった。

「結び」の部分はやや急ぎ過ぎたきらいはあるが、保守主義の本来的な思想のまともさは伝わったし、納得もいく。そこであえて言えば、「リベラル<革新>宣言」というものもあるべきではないかと思う。
フランス革命の暴力的な市民革命は今日の「民主主義」の礎となったが、もっと根源的な「革新」の潮流というものも描くべきではないかと思えた。「改良主義」と揶揄されてきた革新的な政治家・学者をもっと発掘すべきだとこのごろ痛感する。中島氏のほとばしる情念が日本を洗濯してくれることを期待している。