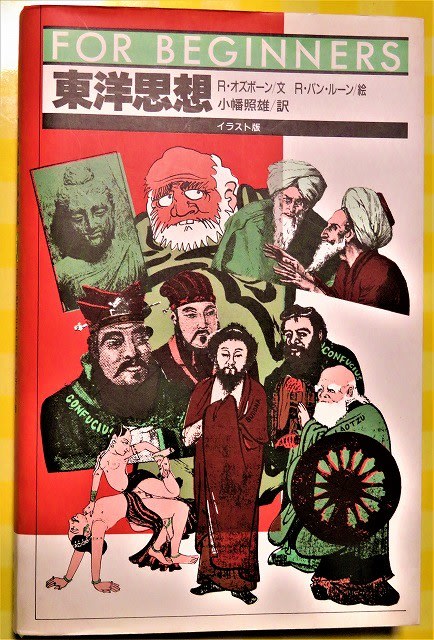自民党の総裁選挙で4候補が争っている。誰がなるにしても中枢にいる爺ちゃんたちの旧態依然とした壁は大きい。彼らはこれからの日本の羅針盤を描くのは不得意だが目先の利害には敏感に反応する。そんなときだからこそ、気鋭の学者の佐伯啓思(ケイシ)の本を読みたくなった。『<アメリカニズム>の終焉』(TBSブリタニカ、1993.4)は、期待通りの傑作だった。

本書は約30年前に執筆されたものだが、著者が描いたその後の世界はその通り進行しているのがすごい。歴史的な1991年は、ソ連の崩壊と湾岸戦争があげられるが、そのポスト冷戦は憲兵たるアメリカの後退や民族・地域間抗争の深化がいまだ進行し現代にいたる。アメリカのアフガン撤退がベトナム戦争撤退と軌を一にする。
いまの世界の混迷は、著者に言わせれば、「近代の歴史を導いてきた観念がゆきづまったということにほかならない」と指摘する。

したがって、近代を牽引してきた観念の検証がいまこそ必要だということになる。社会主義の崩壊や湾岸戦争の勝利にもかかわらず、欧米のリベラル・デモクラシー理念の衰退も問いかける。そして、著者は「真の問題は、世界を秩序だてる理念や価値にある」として、「日本がこうした価値の担い手にもならず、世界に優秀な商品ばかり提供してもそれが何になるというのだろうか」と問う。

モノを作ることが<消費者>のためだ、とする「アメリカニズム」の優等生は日本だったが、その限界が見えてきた現在、著者は近代を導いた「シビック・リベラリズム」に注目したがその踏み込みには紙数が足りない気がした。それはむしろ、渋沢栄一とは言わないが、二宮尊徳が唱えた道徳と経済との融合にヒントがあるように思えてならない。彼の影響によって社会貢献した明治から昭和初期の事業家は少なくない。それこそ、日本的シビック・リベラリズムの先駆けではないだろうか。

著者の結語は、「新しいことを起こす力は本当は徹底した保守主義からでてくるだけなのだ」と、「静かな知的な思考の変革の作業」ということだった。そこはかつて読んできた評論家・西部邁氏と同じ結論であったのも発見だった。しかしそれを説明するにはもう一冊書かなければならない。
切れ味のシャープな分析にいくども舌を巻いたが、後半はオイラの海馬はとてもついていけなかった。しかし、30年前の湾岸戦争からすぐにアメリカニズムの凋落を予感してしまう眼力には頭が下がる。こういう人をもっとマスコミは注視してもらいたいものだ。