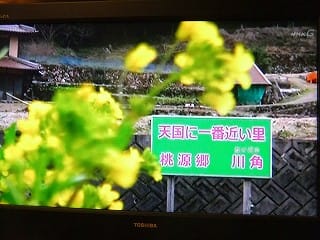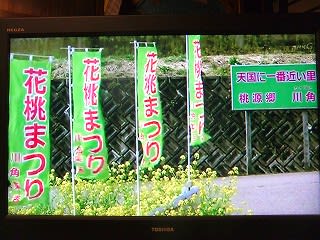どんよりした一日が続く。
これは植木を移植するチャンスとばかりに、穴を掘る。
案の定、葛の根っこが作業を阻もうとする。
そのうえ、小石どころか大石がこちらの意図を粉砕してくる。

いましかチャンスがないからと、作業を続ける。
「あせらずゆっくりやれよ」と自分に言い聞かせる。
掘るほどに石は倍近くの大きさになっていく。

汗が眼に入る。
気温は30度近いが、忘れた頃小雨もパラリとやってくる。
午前も午後もTシャツがぐっしょりする。
石や木材を使いながら大石を地上にあげていく。

ついに掘り出し成功。
最後は石を抱きかかえるようにして穴の外へ。
できるだけ力を使わないで取り出すのはまるでパズルのようだ。
この穴には「ハクモクレン」を移植する。

これはきょうの午前中に取り出した石。
掘っていくうちにどんどん石が大きくなっていく。
ここには、「キングサリ」の樹を移植する。

先日この石でてこずる。
丸い石は意外に掘りだしにくいのがわかった。
しかも、かなり重くて最後まで人力では無理だった。
それでもなんとか、鉄の棒と木材や転がっている石で取り出す。
この穴には大きくなった「梅」を掘り出して近く移植する予定だ。
これは植木を移植するチャンスとばかりに、穴を掘る。
案の定、葛の根っこが作業を阻もうとする。
そのうえ、小石どころか大石がこちらの意図を粉砕してくる。

いましかチャンスがないからと、作業を続ける。
「あせらずゆっくりやれよ」と自分に言い聞かせる。
掘るほどに石は倍近くの大きさになっていく。

汗が眼に入る。
気温は30度近いが、忘れた頃小雨もパラリとやってくる。
午前も午後もTシャツがぐっしょりする。
石や木材を使いながら大石を地上にあげていく。

ついに掘り出し成功。
最後は石を抱きかかえるようにして穴の外へ。
できるだけ力を使わないで取り出すのはまるでパズルのようだ。
この穴には「ハクモクレン」を移植する。

これはきょうの午前中に取り出した石。
掘っていくうちにどんどん石が大きくなっていく。
ここには、「キングサリ」の樹を移植する。

先日この石でてこずる。
丸い石は意外に掘りだしにくいのがわかった。
しかも、かなり重くて最後まで人力では無理だった。
それでもなんとか、鉄の棒と木材や転がっている石で取り出す。
この穴には大きくなった「梅」を掘り出して近く移植する予定だ。





















 隙間だらけのわが古民家は、夜になると虫の訪問者がにぎやかになる。
隙間だらけのわが古民家は、夜になると虫の訪問者がにぎやかになる。