本日、 。
。

現在、ウコッケイが卵を温めて(抱卵し)ています。
最近めっきり寒くなったこともあり、3羽で一緒になって温めている珍しい光景です。
今年から月一度訪れながら自然菜園に移行している長野市の様子


先月ご紹介したブログの蒔いた緑肥作物(マメ科作物:レンゲ、クリムソンクローバー、アルサイククローバー、イネ科作物:ライムギ、ライコムギ)がさらに芽吹いていました。
灰色台地土という粘土質の強い元田んぼを自然菜園に切り替えるため、1m以上深く耕してくれ、さらに根に寄生する微生物の働きで土を豊かにしてくれる緑肥作物の効果は計りしれません。
1年を通じて、様々な緑肥作物を活用することで、来年から畑として使えるように計画しております。

長野市にある実験農場では、今まで化学肥料、農薬を使っていた畑を来年から自然菜園として使えるように、こちらも準備中でした。
とても粘土質が強いこと、スギナが多く生え化学肥料を使っていたため団粒構造や腐植があまり発達していないため、
そこで、水もちがよく、水はけのよい畑になるように、エンバクを中心に緑肥作物を育て、それをすき込んだ後、
更に2年間完熟させた自家製落ち葉堆肥をすき込み、先日畝立てを友人としてきました。

畝を立てるのは、秋の温かい日中が最適で、秋のうちに畝を立てておき、
その上から、米ぬかや油かすを撒き、ワラや草などで覆っておくことで、春までに土が調います。
イメージとしては、秋に落ち葉が積り、春までに落ち葉の下で土づくりが出来ているような感じです。


更に、今回は全く新しい畑を自然菜園に切り替えるため、通路に緑肥作物のタネを混ぜて蒔いておきます。
詳しくは拙著『これならできる!自然菜園』p16、p30~35をご参照ください。


今回混ぜた緑肥作物は、6種類。
緑肥作物の組み合わせは、3種類以上が好ましく、イネ科とマメ科など季節や目的に応じて内容を吟味し、ブレンドします。
イネ科:ライムギ、イタリアンライグラス、エンバク、ペレニアルライグラス、
マメ科:アカクローバー、クリムソンクローバー


通路に溝を掘り、1~2列通路の幅に応じて条に蒔いていきます。
通路に緑肥作物を導入することで、通路も固くならず、畝間を改善でき、野菜の株元に敷く草マルチ用の草も確保でき、
様々なタイプの畑を自然に育てやすい状況を作ってくれます。
自然菜園では、最初の1~3年は畑の状況などステージに合わせ必要とあらば、緑肥作物などを積極的に使い、
緑肥作物をテコに、野菜と草が共存できるよう導きます。
秋のうちに蒔いておけば、春にはある程度育っているので、来年の春からの栽培に間に合います。
春まきする場合は、緑肥作物の内容や割合を変えて早めに蒔いておくとよいでしょう。
自然菜園を始めて数年は緑肥作物が優先しますが、ついには緑肥作物もまばらになり、
自然草に切り替わり、より自然に育てる環境に移行します。
今まで農薬・化学肥料に依存していた畑は満身創痍です。人であれば、入院状態です。
まずは、リハビリ、その後は軽い運動、本格的なトレーニングが必要です。
それに代わるのが、完熟堆肥投入や、緑肥作物導入です。
来年から、何を育てていくのか今から計画を立てるのが楽しみです。


11月30日(火)NHKカルチャー(i-City21松本教室)
「日本みつばち自然養蜂のはじめ方(秋冬編)」
同場所で、毎月行われる自然菜園講座「無農薬・ずくなし家庭菜園教室」のご案内はこちら
【拙著のご紹介】
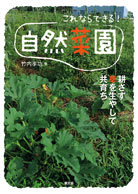
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~
 。
。
現在、ウコッケイが卵を温めて(抱卵し)ています。
最近めっきり寒くなったこともあり、3羽で一緒になって温めている珍しい光景です。
今年から月一度訪れながら自然菜園に移行している長野市の様子


先月ご紹介したブログの蒔いた緑肥作物(マメ科作物:レンゲ、クリムソンクローバー、アルサイククローバー、イネ科作物:ライムギ、ライコムギ)がさらに芽吹いていました。
灰色台地土という粘土質の強い元田んぼを自然菜園に切り替えるため、1m以上深く耕してくれ、さらに根に寄生する微生物の働きで土を豊かにしてくれる緑肥作物の効果は計りしれません。
1年を通じて、様々な緑肥作物を活用することで、来年から畑として使えるように計画しております。

長野市にある実験農場では、今まで化学肥料、農薬を使っていた畑を来年から自然菜園として使えるように、こちらも準備中でした。
とても粘土質が強いこと、スギナが多く生え化学肥料を使っていたため団粒構造や腐植があまり発達していないため、
そこで、水もちがよく、水はけのよい畑になるように、エンバクを中心に緑肥作物を育て、それをすき込んだ後、
更に2年間完熟させた自家製落ち葉堆肥をすき込み、先日畝立てを友人としてきました。

畝を立てるのは、秋の温かい日中が最適で、秋のうちに畝を立てておき、
その上から、米ぬかや油かすを撒き、ワラや草などで覆っておくことで、春までに土が調います。
イメージとしては、秋に落ち葉が積り、春までに落ち葉の下で土づくりが出来ているような感じです。


更に、今回は全く新しい畑を自然菜園に切り替えるため、通路に緑肥作物のタネを混ぜて蒔いておきます。
詳しくは拙著『これならできる!自然菜園』p16、p30~35をご参照ください。


今回混ぜた緑肥作物は、6種類。
緑肥作物の組み合わせは、3種類以上が好ましく、イネ科とマメ科など季節や目的に応じて内容を吟味し、ブレンドします。
イネ科:ライムギ、イタリアンライグラス、エンバク、ペレニアルライグラス、
マメ科:アカクローバー、クリムソンクローバー


通路に溝を掘り、1~2列通路の幅に応じて条に蒔いていきます。
通路に緑肥作物を導入することで、通路も固くならず、畝間を改善でき、野菜の株元に敷く草マルチ用の草も確保でき、
様々なタイプの畑を自然に育てやすい状況を作ってくれます。
自然菜園では、最初の1~3年は畑の状況などステージに合わせ必要とあらば、緑肥作物などを積極的に使い、
緑肥作物をテコに、野菜と草が共存できるよう導きます。
秋のうちに蒔いておけば、春にはある程度育っているので、来年の春からの栽培に間に合います。
春まきする場合は、緑肥作物の内容や割合を変えて早めに蒔いておくとよいでしょう。
自然菜園を始めて数年は緑肥作物が優先しますが、ついには緑肥作物もまばらになり、
自然草に切り替わり、より自然に育てる環境に移行します。
今まで農薬・化学肥料に依存していた畑は満身創痍です。人であれば、入院状態です。
まずは、リハビリ、その後は軽い運動、本格的なトレーニングが必要です。
それに代わるのが、完熟堆肥投入や、緑肥作物導入です。
来年から、何を育てていくのか今から計画を立てるのが楽しみです。


11月30日(火)NHKカルチャー(i-City21松本教室)
「日本みつばち自然養蜂のはじめ方(秋冬編)」
同場所で、毎月行われる自然菜園講座「無農薬・ずくなし家庭菜園教室」のご案内はこちら
【拙著のご紹介】
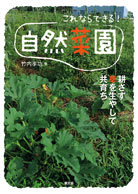
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~





















