本日、 。
。
本日は、『無農薬 これならできる!自然菜園入門講座』(長野市・城山公民館教室)夜間部の開催日です。
今月は、「8/2(水)夏野菜の延命法、秋野菜の真夏の種まき、定植のコツ」です。



ブログのつづきです。
(公財)自然農法国際研究開発センター(以後自然農法センター)は、私が10年前に家庭菜園スクールを開業する直前までお世話になっていた最後の研修先です。
ちなみに、私は、現在でいう本科研修(自家採種コース)で8カ月自然農法の種子について学ばせていただきました。
民間では、自然農法の研究を長年やっている施設です。
見学会については、こちら
から事前にご相談いただければと思います。
午後は、お弁当をいただいてから、自然農法の種子の研究をされている圃場に移動し、職員の巴 清輔さんに、育種圃場を見学させていただきました。




1mの平畝と両脇に1mの緑肥草生帯で、トマトやキュウリ、ナス、ピーマンなどの種が育てられております。
夏野菜の後は、緑肥用の麦を育て、翌年

カウピーやソルゴーで育土して、秋野菜を育てるのが特徴です。
私がいた研修させていただいた時代は、中川原さんが課長として、この圃場で草刈りや誘引など実践で教わったものです。

ナスの育種の様子です。
両脇の草生帯(通路)の草を刈って、野菜の株元に敷き草しながら育てております。
一つの品種が生まれるには5年以上もかかるのが通常で、ただ単に自家採種を重ねても美味しく育てやすい品種育成にならないことが学べました。


巴さんの担当しているメロンの採種圃場です。
何種類ものメロンが芝生草生栽培の中で育っておりました。
厳しい環境、無肥料、不耕起、草の中で、露地で雨よけがなくても育つメロンの育成について教わりました。
育種圃場を後に、


水田に移動しました。
水稲チームは三木さんという方が本来担当ですが、当日は中国出張のため、代理で大久保さんが説明してくれました。


大久保さんが指さしている色が薄い葉の一角は、印がしてあり無除草区。
つまり、一度も入らず除草していない区画です。
無除草のわりに、草が生えていなかったのが印象的です。
つまり、除草するまえに、草が生えてこない環境に田植えまでにしておくことの重要性がわかります。
当日は、中干し(土用干し)の期間中で、水田にほぼ水はなく、地面がむき出しになっておりましたが、草はほとんどなく、小さなコナギが点在する程度でした。
実際に草を抑えた田んぼで、出穂直前の自然農法で理想的な状況をみんなで見れて良かったです。


次に、無肥料区を見学させていただきました。
17年間無肥料で試験されており、収量は5~6俵/10アールだそうです。
無肥料栽培区にしか生えない「星草」です。田んぼの管理(お世話)の仕方で、生えてくる草が変わるので草は指標になります。


自然農法センターに帰って来てから、イセキさんと共同開発した乗用型除草機や


新潟農総研で開発されたチェーン除草機など実際に使っているものを見せていただきました。
チェーン除草機の作り方は、公開されております。


自然農法センターに帰って来てから、巴さんが冷やしておいてくれたメロンを試食しました。


土壌生物が専門の大久保さんから、土の中の生き物の紹介、どのような管理(お世話)でどのような生き物増えるのかなど、土壌生物による自然の豊かさ評価の仕方などを教わりました。

実際に、自然菜園1年目(左)。
2年目栽培しないと(中央)。
2年目栽培し続けていると(右)の写真のように、
野菜を育てながら、草マルチを重ねていくことで、格段に生き物は増えている様子がわかると思います。

最後に、17年間不耕起、無肥料、麦とエダマメの連作区の土を持ってきていただき、土壌生物によって作られた土「もろくなる土」を体感していただきました。
この一日で、中川原さんの圃場から始まり、午後は自然農法センターの育種圃場、水稲圃場、土壌生物勉強会と多岐にわたる有意義な見学会となりました。
私がこうして教えられるのも、自然農法センターなどの研修を経ているからで、一緒に見学した自然菜園スクール生たちにも、原点を知ってもらい、自然農法の奥深さや研究の成果を共有し、今後自分たちの菜園に活かしてもらえればと思っております。
この見学会を通じて、視野が広がり、今まで以上に作物と会話できるようになれればと思っての開催でしたが、
参加者から、いろいろな感想をいただき、それ以上の成果があった実りある見学会になったようです。
2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回9/6(水)-夏野菜の自家採種、冬野菜の種まき、定植
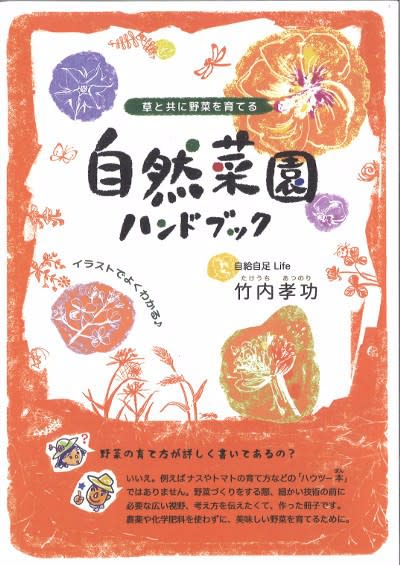
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中
 。
。本日は、『無農薬 これならできる!自然菜園入門講座』(長野市・城山公民館教室)夜間部の開催日です。
今月は、「8/2(水)夏野菜の延命法、秋野菜の真夏の種まき、定植のコツ」です。



ブログのつづきです。
(公財)自然農法国際研究開発センター(以後自然農法センター)は、私が10年前に家庭菜園スクールを開業する直前までお世話になっていた最後の研修先です。
ちなみに、私は、現在でいう本科研修(自家採種コース)で8カ月自然農法の種子について学ばせていただきました。
民間では、自然農法の研究を長年やっている施設です。
見学会については、こちら
から事前にご相談いただければと思います。
午後は、お弁当をいただいてから、自然農法の種子の研究をされている圃場に移動し、職員の巴 清輔さんに、育種圃場を見学させていただきました。




1mの平畝と両脇に1mの緑肥草生帯で、トマトやキュウリ、ナス、ピーマンなどの種が育てられております。
夏野菜の後は、緑肥用の麦を育て、翌年

カウピーやソルゴーで育土して、秋野菜を育てるのが特徴です。
私がいた研修させていただいた時代は、中川原さんが課長として、この圃場で草刈りや誘引など実践で教わったものです。

ナスの育種の様子です。
両脇の草生帯(通路)の草を刈って、野菜の株元に敷き草しながら育てております。
一つの品種が生まれるには5年以上もかかるのが通常で、ただ単に自家採種を重ねても美味しく育てやすい品種育成にならないことが学べました。


巴さんの担当しているメロンの採種圃場です。
何種類ものメロンが芝生草生栽培の中で育っておりました。
厳しい環境、無肥料、不耕起、草の中で、露地で雨よけがなくても育つメロンの育成について教わりました。
育種圃場を後に、


水田に移動しました。
水稲チームは三木さんという方が本来担当ですが、当日は中国出張のため、代理で大久保さんが説明してくれました。


大久保さんが指さしている色が薄い葉の一角は、印がしてあり無除草区。
つまり、一度も入らず除草していない区画です。
無除草のわりに、草が生えていなかったのが印象的です。
つまり、除草するまえに、草が生えてこない環境に田植えまでにしておくことの重要性がわかります。
当日は、中干し(土用干し)の期間中で、水田にほぼ水はなく、地面がむき出しになっておりましたが、草はほとんどなく、小さなコナギが点在する程度でした。
実際に草を抑えた田んぼで、出穂直前の自然農法で理想的な状況をみんなで見れて良かったです。


次に、無肥料区を見学させていただきました。
17年間無肥料で試験されており、収量は5~6俵/10アールだそうです。
無肥料栽培区にしか生えない「星草」です。田んぼの管理(お世話)の仕方で、生えてくる草が変わるので草は指標になります。


自然農法センターに帰って来てから、イセキさんと共同開発した乗用型除草機や


新潟農総研で開発されたチェーン除草機など実際に使っているものを見せていただきました。
チェーン除草機の作り方は、公開されております。


自然農法センターに帰って来てから、巴さんが冷やしておいてくれたメロンを試食しました。


土壌生物が専門の大久保さんから、土の中の生き物の紹介、どのような管理(お世話)でどのような生き物増えるのかなど、土壌生物による自然の豊かさ評価の仕方などを教わりました。

実際に、自然菜園1年目(左)。
2年目栽培しないと(中央)。
2年目栽培し続けていると(右)の写真のように、
野菜を育てながら、草マルチを重ねていくことで、格段に生き物は増えている様子がわかると思います。

最後に、17年間不耕起、無肥料、麦とエダマメの連作区の土を持ってきていただき、土壌生物によって作られた土「もろくなる土」を体感していただきました。
この一日で、中川原さんの圃場から始まり、午後は自然農法センターの育種圃場、水稲圃場、土壌生物勉強会と多岐にわたる有意義な見学会となりました。
私がこうして教えられるのも、自然農法センターなどの研修を経ているからで、一緒に見学した自然菜園スクール生たちにも、原点を知ってもらい、自然農法の奥深さや研究の成果を共有し、今後自分たちの菜園に活かしてもらえればと思っております。
この見学会を通じて、視野が広がり、今まで以上に作物と会話できるようになれればと思っての開催でしたが、
参加者から、いろいろな感想をいただき、それ以上の成果があった実りある見学会になったようです。
2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回9/6(水)-夏野菜の自家採種、冬野菜の種まき、定植
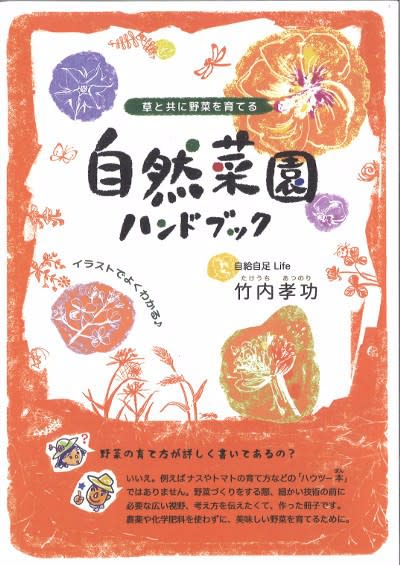
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中





















