本日、 のち
のち の予報。
の予報。
まだまだ梅雨のような日が続きます。
変な天気でも対応できる栽培方法を模索しつつ、同時にこうなったのは過度な環境破壊の結果だと思うので、持続可能な暮らしをしながら今できること未来には天気が元に少しでも戻るよう努力したいと思います。

自然菜園では、3つの柱があります。
1)野菜が自然に育つ環境づくり
野菜が育つ土を育ててくれる生き物たちとの共生(草マルチ)、野菜が自然に育つ仲間(コンパニオンプランツ)など
2)自家採種
世界各国から集まった多国籍な野菜は、品種改良をしながら旅をして今日本に来ています。日本に馴染んでもらい、無農薬でも美味しく育つ品種に育成し、在来化してもらうためには、自家採種は欠かすことの出来ないことです。
3)自然育苗
自家採種で育成された自分の畑に合ったタネたちを、一層本気が出せ、自然に育つ力を発揮できる育苗も大切な要素です。
タネが良くても育苗で失敗することが多く、野菜のやる気が萎えてしまってはもったいない限りです。
そんな3本柱の中の2つを扱うのがこの『自然育苗タネ採りコース』といったわけです。
このコースでは、自家採種の基本から自然に育つ野菜を育成する方法、そしてそのタネが本気を出せる育苗方法を1年を通して学びます。
昔は、この3つの柱がどの農家さんでも、自分で採ったタネで、苗を起こして、栽培するのが通常でしたが、
現在では、種苗会社が専門でタネを採り、
育苗会社が、苗を効率的に育て、売る
それらを我々が買って育てるのが、一般的な家庭菜園になりました。
最初は、自家採種や自然育苗の講義を聴き、見聞を広め、次に実習に入ります。


畑では、キュウリのタネ採り用の採種果が大きく実り、タネを育んでおります。




一週間前に収穫した完熟した採種果を追熟後、タネをかき出し、発酵させてから洗い流し乾燥させます。

レタスのタネもバケツで叩きながら採種します。

シュンギクのタネは手でもみほぐした後に、


フルイでふるってからゴミを飛ばします。

タマネギのタネ採りは意外と難しく、数がまだたくさん採れません。
貴重なタネをフルイでしごきとります。

雑穀などのタネ採りは、(今回オオムギの一種:裸麦)
足踏み脱穀機で脱穀後、



フルイと唐箕でゴミを分けてあげます。
昔ながらの道具が大活躍です。



以前「現代農業」(農文協)でも取り上げていただいた秋ジャガポット栽培を行いました。


ハウスに移動。
ハウスでは空いたスペースを利用して、ブドウのハウス栽培も無農薬で行っております。

通常の育苗土のブレンドに

クン炭とバッドグアノとモミガラ灰(ウエルダンクン炭)を加えて、タマネギ専用の育苗土を作りました。
タマネギの苗づくりは、ある意味最も難しく、品種改良が進んだタマネギでは、培養土に一工夫することで、誰でも簡単に育つように工夫してみました。



今回は、セルトレーで育てるタマネギ苗づくりをお伝えしました。


最後に、育苗土の切り返しをみんなで行いました。
この来年用の育苗土は、堆肥の発酵技術を利用し、育苗土を再生、自給するためのものです。
育苗土の失敗=育苗の失敗になるので、良質な育苗土作りが最も難しいと言えるかもしれません。
このコースは、自家採種と育苗とに2つに分けてもいいのですが、昔この2つがセットだったように、持続可能な暮らしという点からも2つセットで行っております。
2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回9/6(水)-夏野菜の自家採種、冬野菜の種まき、定植
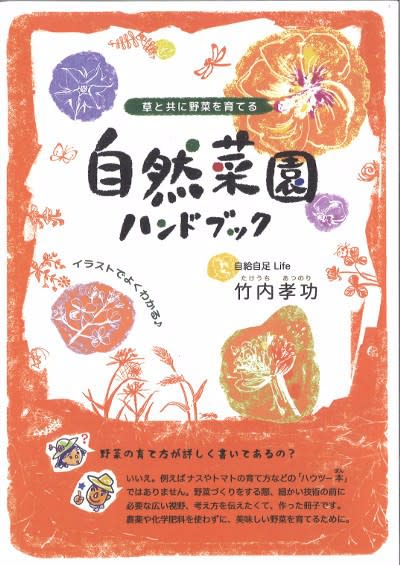
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中
 のち
のち の予報。
の予報。まだまだ梅雨のような日が続きます。
変な天気でも対応できる栽培方法を模索しつつ、同時にこうなったのは過度な環境破壊の結果だと思うので、持続可能な暮らしをしながら今できること未来には天気が元に少しでも戻るよう努力したいと思います。

自然菜園では、3つの柱があります。
1)野菜が自然に育つ環境づくり
野菜が育つ土を育ててくれる生き物たちとの共生(草マルチ)、野菜が自然に育つ仲間(コンパニオンプランツ)など
2)自家採種
世界各国から集まった多国籍な野菜は、品種改良をしながら旅をして今日本に来ています。日本に馴染んでもらい、無農薬でも美味しく育つ品種に育成し、在来化してもらうためには、自家採種は欠かすことの出来ないことです。
3)自然育苗
自家採種で育成された自分の畑に合ったタネたちを、一層本気が出せ、自然に育つ力を発揮できる育苗も大切な要素です。
タネが良くても育苗で失敗することが多く、野菜のやる気が萎えてしまってはもったいない限りです。
そんな3本柱の中の2つを扱うのがこの『自然育苗タネ採りコース』といったわけです。
このコースでは、自家採種の基本から自然に育つ野菜を育成する方法、そしてそのタネが本気を出せる育苗方法を1年を通して学びます。
昔は、この3つの柱がどの農家さんでも、自分で採ったタネで、苗を起こして、栽培するのが通常でしたが、
現在では、種苗会社が専門でタネを採り、
育苗会社が、苗を効率的に育て、売る
それらを我々が買って育てるのが、一般的な家庭菜園になりました。
最初は、自家採種や自然育苗の講義を聴き、見聞を広め、次に実習に入ります。


畑では、キュウリのタネ採り用の採種果が大きく実り、タネを育んでおります。




一週間前に収穫した完熟した採種果を追熟後、タネをかき出し、発酵させてから洗い流し乾燥させます。

レタスのタネもバケツで叩きながら採種します。

シュンギクのタネは手でもみほぐした後に、


フルイでふるってからゴミを飛ばします。

タマネギのタネ採りは意外と難しく、数がまだたくさん採れません。
貴重なタネをフルイでしごきとります。

雑穀などのタネ採りは、(今回オオムギの一種:裸麦)
足踏み脱穀機で脱穀後、



フルイと唐箕でゴミを分けてあげます。
昔ながらの道具が大活躍です。



以前「現代農業」(農文協)でも取り上げていただいた秋ジャガポット栽培を行いました。


ハウスに移動。
ハウスでは空いたスペースを利用して、ブドウのハウス栽培も無農薬で行っております。

通常の育苗土のブレンドに

クン炭とバッドグアノとモミガラ灰(ウエルダンクン炭)を加えて、タマネギ専用の育苗土を作りました。
タマネギの苗づくりは、ある意味最も難しく、品種改良が進んだタマネギでは、培養土に一工夫することで、誰でも簡単に育つように工夫してみました。



今回は、セルトレーで育てるタマネギ苗づくりをお伝えしました。


最後に、育苗土の切り返しをみんなで行いました。
この来年用の育苗土は、堆肥の発酵技術を利用し、育苗土を再生、自給するためのものです。
育苗土の失敗=育苗の失敗になるので、良質な育苗土作りが最も難しいと言えるかもしれません。
このコースは、自家採種と育苗とに2つに分けてもいいのですが、昔この2つがセットだったように、持続可能な暮らしという点からも2つセットで行っております。
2017年土内容充実で、
『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。
城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。
今年度は、いつもの第1水曜日に
城山公民館 18:30~21:25
18:30~19:45座学
19:50~21:25質疑応答
新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~
新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」
次回9/6(水)-夏野菜の自家採種、冬野菜の種まき、定植
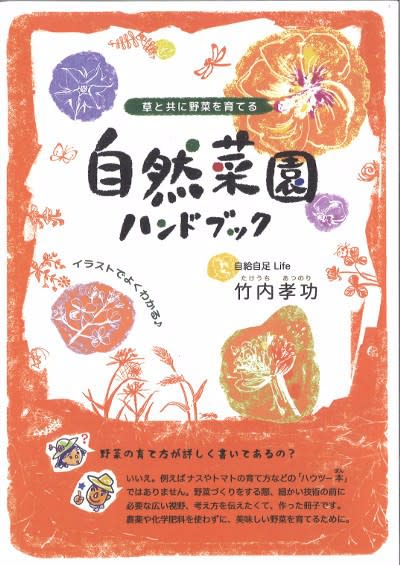
ちなみに、忙しすぎてご紹介できていない自負出版の菜園教室の公式テキスト『自然菜園ハンドブック』(自負出版)も農文協さんの「田舎の本屋さん」からネットでも書店で東京で唯一購入できます。
農閑期に入りましたら、改めてお知らせし、売っていただけるカフェ、ネットサイト、お店など募集し、なおネットからも買えるようにシステムを構築するつもりです。
現在農繁期なので、何もできておらず申し訳ございません。
現在、長野県松本にあるつる新種苗さんにも縁あって『自然菜園ハンドブック』を置かせていただいております。こちらからも購入できます。
※現在2店舗のみ販売中





















